住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。
家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
目次
光がたっぷりと差し込む住まいは、多くの方が思い描く理想の空間ではないでしょうか。部屋の中に光を採り込む“採光”は、快適性に大きく影響します。家づくりの段階から採光を意識して空間構成を行うと、明るく開放的な住まいを実現できるでしょう。
今回は採光の基礎知識、室内に光を採り込むための間取りのアイデアまで、明るく心地よい家づくりに役立つ情報をご紹介します。
採光は家づくりに重要! その理由を知ろう

家づくりにおける“採光”には、建築基準法による基準が設けられており、設計上重要な要素の1つです。
まずは、採光とは何かを解説します。
採光とは
採光とは、室外の光(主に太陽光)を、窓などの開口部を通して室内に採り込むことを指します。直射日光が室内にどれだけ入るかを指す“日当たり”と、建築計画上の採光は意味合いが異なります。
建築基準法上の採光とは
建築基準法において、採光に関する規定は重要視されており、居室(※)には “採光に有効な開口部(窓など)”の設置義務があります。採光に有効な開口部の大きさを“有効採光面積”といい、部屋の用途に応じて最低限必要とされる有効採光面積が定められています。
これらの採光条件を満たしていない部屋は、不動産広告などで居室として扱うことができません。
(※)居室:人が継続して作業や集会を行う部屋のこと。一般的には寝室・居間・台所などがこれにあたり、居室ではない廊下や浴室、トイレなどにこの規定はありません。
関連記事⇒「居間とはどの部屋のこと? 居室やリビングとの違いと、レイアウトのポイント」
住宅の場合、建築基準法 第28条1項で、有効採光面積は「居室の床面積に対して、五分の一から十分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければならない」と明記されています。そして政令である建築基準法施行令により、有効採光面積は居室の床面積の1/7以上が必要と定められました。なお、2023年2月に公表された国土交通省告示第86号により、照明設備の設置によって床面で50ルクス以上の照度を確保できる居室では、有効採光面積を1/10以上に緩和することも可能になりました(2025年7月時点)。
これらで定められているのはあくまでも最低限の基準であることを念頭に置き、自分が望む部屋の明るさを実現するために必要な開口部の大きさや位置を、設計担当者と一緒に考えることが大切です。
暮らしに大切な採光計画
朝起きてから夜眠るまで、人の何気ない生活の中で太陽光は大きな関わりを持っています。朝起きて太陽の光を浴びると、なんだか気持ちがしゃきっとして目が覚め、気持ちよく活動できるのではないでしょうか。
体内時計をリセットするためにも、朝は太陽の光を浴びて快適な1日をスタートさせましょう。
昼にしっかりと活動し、夜は質の良い睡眠をとる。採光計画は、そんな暮らしに大切なものです。
採光の工夫で光熱費を節約
採光によって十分な明るさを確保できれば、昼間は照明設備に頼ることなく生活できます。また、採光計画とあわせて日照条件を整えることで、冬場は太陽光のぬくもりを享受しながら、エアコン代を節約できるという一石二鳥の過ごし方も可能です。
このようなパッシブデザイン(自然エネルギーを活用した設計手法)を積極的に取り入れて省エネ性能を高めると、光熱費を節約しながら環境にやさしい暮らしを実現できるでしょう。
採光をうまく活用するための基礎知識
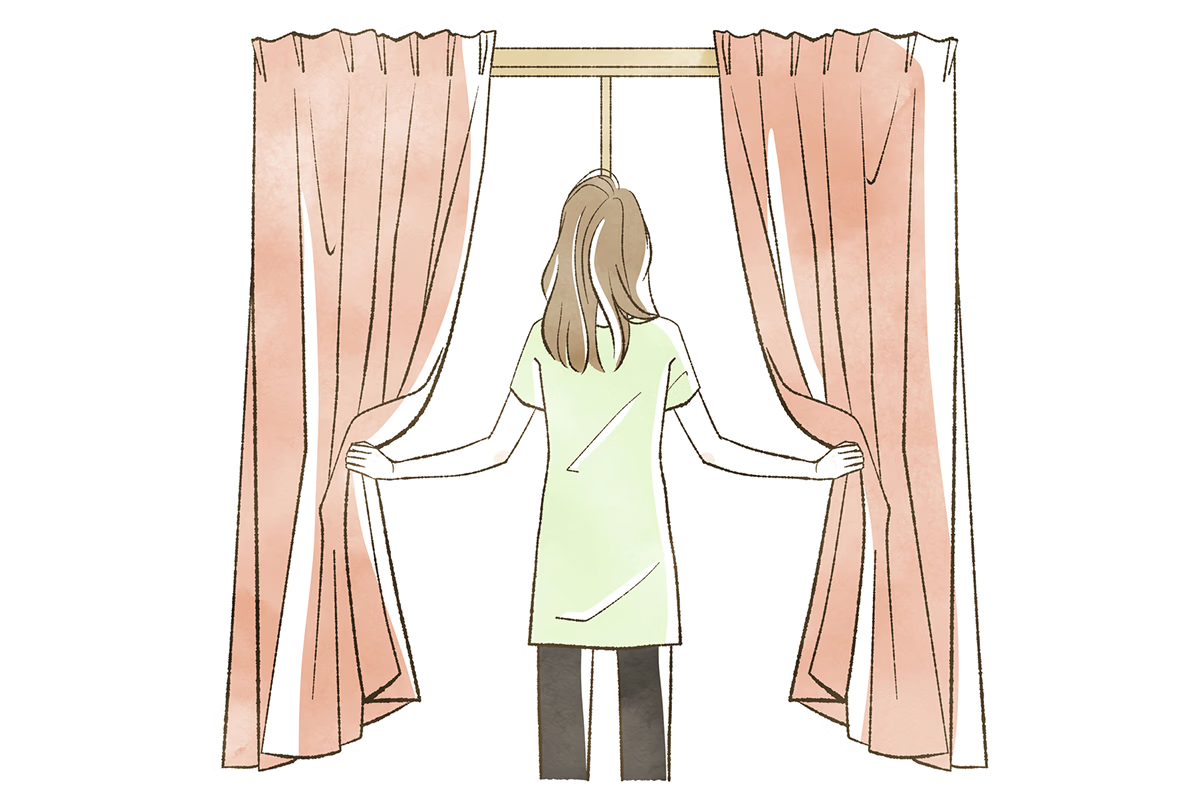
続いて、採光をうまく活用するための基礎知識をご紹介します。
方角ごとの太陽光の特徴
部屋の向きによって、室内への太陽光の入り方は異なります。
・南向きの部屋
1日を通して太陽光が差し込みやすいことから、部屋が明るく開放的な空間になります。リビングのような家族が長く過ごす部屋に適しているといえるでしょう。夏場は暑さが気になりやすいため、風通しを良くしたり、遮熱レースカーテンなどを設置したりするのがおすすめです。
・東向きの部屋
南向きの部屋に次いで日当たりが良好です。特に午前中は太陽光がよく入るため、寝室やダイニング、子ども部屋に適しています。
・西向きの部屋
日差しは午後から夕方にかけて強くなる傾向があります。特に夕方の西日によって、夏場は部屋が暑くなりやすいので、ブラインドや断熱フィルムなどで日差しをカットする対策がおすすめです。太陽光が入る角度によっては、庇(ひさし:建物の開口部の上に設置される小型の屋根)やオーニング(可動式の庇)よりも窓全体に対策を施すほうが高い効果を期待できることもあります。また室内側にロールスクリーンなどを設置すれば、日差しがきつい時間帯に合わせ採光量も調節可能になります。
・北向きの部屋
直射日光は入りにくいですが、1日を通して安定したやわらかい光を採り込めるので、作業部屋や収納スペースに適しています。夏場も暑くなりにくく、エアコン代を節約しやすいこともメリットです。
採光目的で設置されるはめ殺し窓(FIX窓)についてはこちらの記事もご参照ください。
関連記事⇒「はめ殺し窓とは? FIX窓とも呼ばれるその正体と特徴 メリット・デメリットも紹介」
採光と快適性の関係
明るさは快適な家の条件の1つですが、それだけでは住みやすい家になるとは限りません。採光のために必要な窓によって、以下のような問題が生じることもあります。採光と快適性をバランスよく考えながら家づくりを進めましょう。
・室温
大きな窓を設けると、夏場は暑く、冬場は寒くなりやすいです。庇やブラインドなどによる日射遮蔽計画、快適な温熱環境を維持する断熱・気密設計などをしっかり行うことが大切です。
・プライバシー
窓を設置する場合は、プライバシーの保護が快適性を左右します。人通りの多い道路に面した窓は、高い位置に設置するなど、不快な視線を感じないように工夫しましょう。
直射日光と間接光
採光には、以下の2つがあります。それぞれの特徴を踏まえて効果的に活用すると、居心地のよい空間を実現できるでしょう。
・直射日光
太陽から直接届く光は、明るさや暖かさを確保するのに適しています。レースカーテンやブラインドなどで採り込む光の強さをコントロールし、まぶしさや過度な暑さをやわらげましょう。
・間接光
間接光は、壁や天井などの物体に当たり、反射して届く光のことを指します。光がやわらかく拡散され、安定した光環境を実現できますが、間接光だけでは十分な明るさを確保しにくいことや設計難易度の高さがデメリットです。
おすすめ記事
2025.06.23
採光を意識した間取りアイデア

次に、採光について意識した間取りアイデアをご紹介します。
中庭・光庭
建物の中央に中庭を設けることは、自然光を採り入れるのに効果的なアイデアです。周囲の建物との距離が近い都市部の住宅でも、プライバシーを確保しながら自然光を多くの居室に採り込めます。採光や通風を主目的として設置する“光庭”にも同様の効果が期待できるため、中庭ほどのスペースを確保できない場合におすすめです。
関連記事⇒「中庭のある住宅 メリット・デメリットとパティオやテラスとの違い」
吹き抜け・スキップフロア
吹き抜けやスキップフロアを採用すると、間仕切り壁の量が減るため自然光は家全体に広がりやすくなります。上下階の視線が抜けて開放的な雰囲気が得られるほか、家族が顔を合わせやすいためコミュニケーションが増える効果も期待できるでしょう。
関連記事⇒「スキップフロアのある平屋 30坪の開放的でおしゃれな間取りとは」
屋内の空間をつなぐ室内窓で、光や風を届ける
部屋と部屋、または部屋と廊下の間の壁に“室内窓”を設置して屋内空間をつなぎ、光と風を複数の居室に届けるアイデアもおすすめです。
おすすめ記事
2025.05.20
室内窓で隣の空間の光や風を採り込む

光や風を通して室内空間をゆるやかにつなぐことができる室内窓をご紹介します。
室内窓とは
室内窓とは、部屋と部屋、または部屋と廊下を隔てる間仕切り壁に取り付ける窓です。部屋数を増やすために間仕切り壁が多くなってしまう場合でも、室内窓を設置して空間をゆるやかにつなげば、採光や通風性が向上します。
室内窓の種類
室内窓には大きく分けて以下の2種類があります。
・開閉タイプ
開閉可能な室内窓です。風通しを確保できるほか、窓を介して家族がコミュニケーションを取りやすくなります。両開き・片開き・押し出し・滑り出し・回転窓など、様々な開閉方法があります。
・FIXタイプ
FIXタイプは、開閉できない“はめ殺し”ともいわれる形式の室内窓です。隣室の音や気配が気になりにくく、プライバシーを守りながら自然光を届けられるのがメリットです。スリットタイプの細長い窓や正方形の窓を複数並べることで、単調な壁にリズムを与えるとおしゃれな印象になります。
関連記事⇒「はめ殺し窓とは? FIX窓とも呼ばれるその正体と特徴 メリット・デメリットも紹介」
室内窓の役割
室内窓に期待できる役割は以下のとおりです。
・採光・風通しの確保
・隣室との一体感の演出
・インテリアのアクセント
室内窓は、機能性とデザイン性の両面で空間の魅力を高めます。室内窓を介したやわらかい光はぬくもりを届け、空間が連続することによる一体感は想像以上の開放感を生み出します。家づくりでどうしても間仕切り壁が多くなってしまう場合は、室内窓の設置を検討してみてください。
心地よい空間を演出する室内窓『イエリア 室内窓 マドモ』『イエリア ルームウインドウ』
DAIKENでは、シンプルでスタイリッシュなデザインが魅力の室内窓として、『ieria(イエリア) 室内窓 マドモ』と『ieria(イエリア) ルームウインドウ』をラインアップしています。

『イエリア 室内窓 マドモ 開き戸タイプ』

『イエリア 室内窓 マドモ 引戸タイプ』

『イエリア 室内窓 マドモ FIXタイプ・スタンダード』
『ieria(イエリア) 室内窓 マドモ』は、広い開口部から光をたっぷり採り入れ、風通しをよくする室内窓で、部屋に開放的な雰囲気を演出できます。開き戸タイプと引戸タイプ、FIXタイプ・スタンダードを取り揃えており、設置する場所に合わせて選択可能です。

『イエリア ルームウインドウ フラップタイプ』

『イエリア ルームウインドウ FIXタイプ』
『ieria(イエリア) ルームウインドウ』は、スタイリッシュな格子状のラインが空間を引き締めて、多様なインテリアを演出できる室内窓です。『ieria(イエリア) ルームウインドウ』を設置して空間につながりをつくると、開放感や家族の気配も感じられるインテリアになるでしょう。
隣接する空間から光を採り入れたり、風を通したり、壁面のアクセントとして楽しんだりと、様々なシチュエーションでお使いいただけます。
まとめ
採光は、明るく快適な空間をつくり、ほっとできる住まいを実現するために欠かせない要素です。一方で、採光のために大きな開口部を設置すると、温熱環境が悪化したり、外からの視線が気になったりする可能性があります。これらの留意点を踏まえながら、自然光がたっぷり差し込む明るい家づくりを実現してください。

-
監修者
志鎌のり子(しかまのりこ)
一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。
保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など
関連製品
-
光や風を取り込んで開放的な雰囲気に
-
スタイリッシュなラインが空間を引き立て、多様なインテリアを演出
おすすめ記事Recommends
-
2025.07.07
-
2025.08.20
-
2025.07.07


























