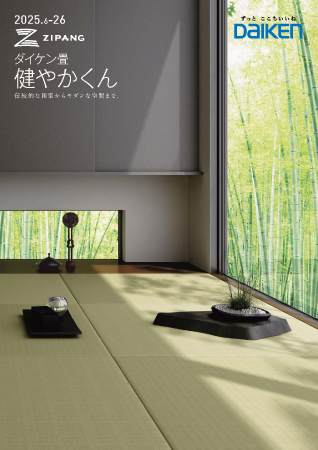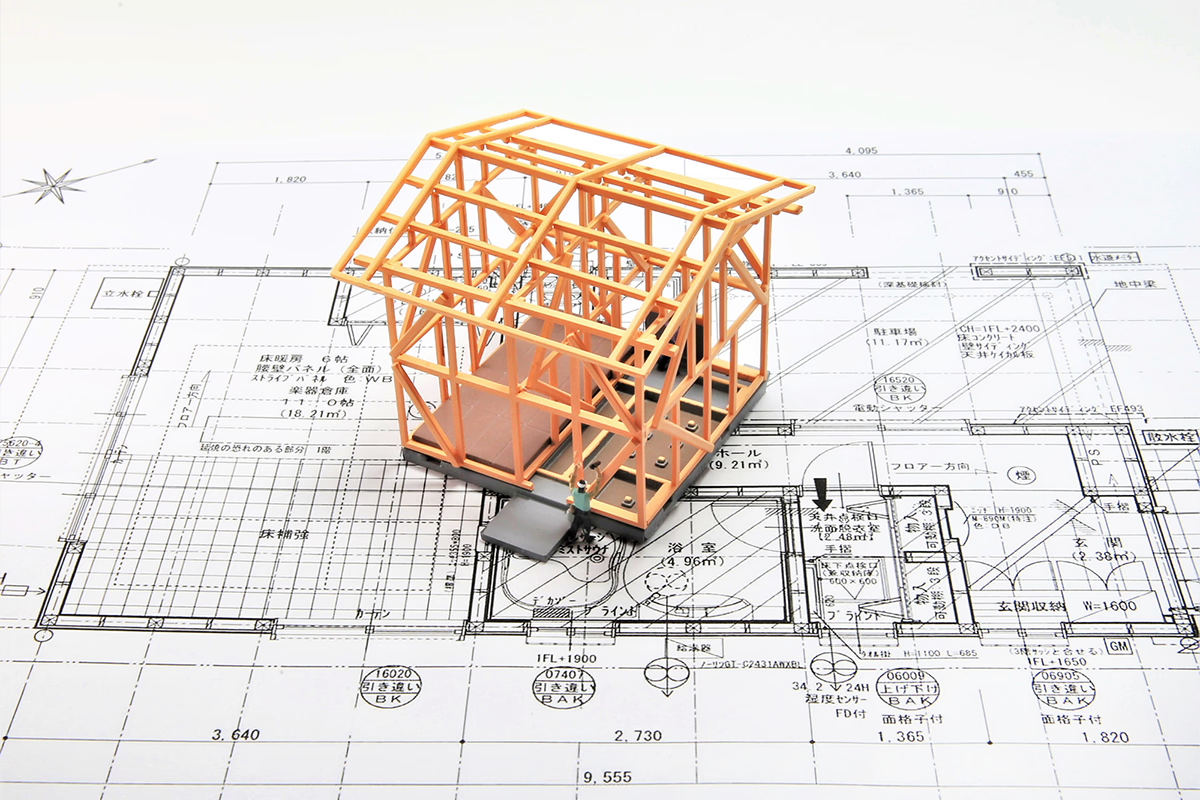住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。
家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
目次
“間(けん)”や“尺(しゃく)”や“寸(すん)”という単位を耳にしたことはありませんか。
いずれも長さの単位ですが、普段の生活であまり使われていない単位なのでイメージが湧きにくいかもしれません。
しかし、これらは家づくりにとって重要な単位です。今回は“尺貫法(しゃっかんほう)”について解説するとともに、現代の家づくりと尺貫法について考えます。
尺貫法とは 使われている長さの単位は?

(※)写真はイメージです。弊社製品ではありません。
“尺貫法”とは、長さの単位を“尺”、体積の単位を“升”、質量の単位を“貫”とする古来の計量法です。尺貫法の単位のうち、家づくりでよく使われるのは、尺(しゃく)、寸(すん)、間(けん)の3つですが、それぞれどれくらいの長さでしょうか。
尺(しゃく)
シャクガ科の幼虫である尺取り虫(しゃくとりむし)の動きのように、広げた親指と人差し指で長さを測ることは昔から行われてきました。広げた親指と人差し指の間の長さが約15cmで、これを2倍にした長さを“1尺”といい、1尺の長さは約30.3cmです。
寸(すん)
親指の幅が由来の“寸”は、尺貫法で最も短い長さの単位で、約3.03cmです。寸は1尺の10分の1の長さで、1尺=10寸となります。家づくりにおいては屋根の勾配を表す“3寸勾配”、高さが5尺7寸の襖(ふすま)を“五七(ごしち)”、5尺8寸の襖を“五八(ごはち)”というように呼び名としても使われています。3寸勾配とは縦3寸・横10寸の直角三角形と同じ傾斜角の勾配屋根のことで、傾斜角度は約16.7度です。
間(けん)
最も長い単位の“間”は、1尺の6倍、1間=6尺(約181.8cm)です。
1間は畳の長辺と同じ長さで、平均的な身長の成人がはみ出ずに寝転がれる長さです。通常、廊下の幅は半間=約91cm、押入れの幅の多くは1間です。
畳2枚分に当たる1間×1間は“1坪(つぼ)”で、この“坪”も家づくりでよく用いられる単位です。
関連記事⇒「1坪は何平米? 土地選びや家づくりの際に知っておきたい広さの単位」
参考:「測量用語」(一般社団法人 東京都測量設計業協会)
江戸間と関西間(京間)の違い
畳のサイズは地域によって異なることをご存じでしょうか。旅先の旅館で見る畳の大きさに、少し違和感を覚えたことはありませんか。
例えば、“江戸間(えどま)”は東京を中心として関東で広く使われている畳で、1畳のサイズは約1.55m²(1.76m×0.88m)です。一方、“京間(きょうま)”とも呼ばれる“関西間(かんさいま)”は京都を中心とした関西圏以西で使われている畳で、1畳のサイズは1.82m²(1.91m×0.955m)です。このような違いがある理由として、関東は部屋の広さを測る際に柱芯間の距離が基準(柱割り)だったのに対し、関西は畳の寸法が基準(畳割り)だったからといわれています。
おすすめ記事
2025.05.20
尺貫法の長さの単位一覧
正確に尺貫法をメートル法に直す必要があるなら、早見表を見ればよいでしょう。しかし、よく使う単位の長さを覚えておくと家づくりに便利です。
尺貫法 長さ一覧
| 1里(り) | 約3.93km |
|---|---|
| 1町(ちょう) | 約109m |
| 1間(けん) | 約181.8cm |
| 1尺(しゃく) | 約30.3cm |
| 1寸(すん) | 約3.03cm |
| 1分(ぶ) | 約3.03mm |
参考:「尺貫法」(大日本図書)
同じ“尺”の単位でも長さが違う?

(※)写真はイメージです。
ところが、同じ“尺”という単位を使っていても、違う長さを表していることがあります。
・曲尺(かねじゃく)
“曲尺”は建築の分野で使われている単位で、先述したように1尺は約30.3cmです。メートル法が導入されるまで日本国内で基準とされる公式の単位でした。なお、曲尺という言葉は建設現場で使われる直角型のものさしを指す言葉でもあります。
・鯨尺(くじらじゃく)
裁縫の分野で使われる尺が“鯨尺”です。鯨のひげでできたものさしを使っていたことから鯨尺と呼ばれており、現代でも鯨尺が刻まれた竹ものさしが販売されています。
鯨尺での1尺は尺貫法(曲尺)の1尺の1.25倍の長さで、メートル法に換算すると鯨尺1尺=約38cmになります。
身近に残る尺貫法

あまり使われなくなった尺貫法ですが、現代でも“尺”の付く言葉が残っています。その一部をご紹介します。
・尺玉
昔から尺貫法が用いられてきた花火づくりでは今もその名残があり、花火の大きさを1寸=1号で表しています。内径約30.3cmの筒で打ち上げる10号玉は直径10寸(1尺)の花火であり、これを“尺玉”と呼びます。
・二尺袖
二尺袖は、袖の長さが2尺の着物です。裁縫分野でいう尺は鯨尺での計算であり、袖の長さは約38cmを2倍にした約76cmとなります。一般的な振袖の長さは約110cmなので、二尺袖は振袖よりも袖が短く、一般的な着物よりは袖が長いという特徴のある着物です。二尺袖には“小振袖”という別名もあり、こちらの方が広く知られている呼び方かもしれません。
・尺鉢(植木鉢)
植木鉢のサイズにも、尺貫法の名残を感じられます。現代では、植木鉢のサイズを“号”で表しますが、1号=1寸であり、10号=1尺は約30.3cmです。
花火の尺玉が10号玉だったのと同じく、植木鉢の“尺鉢(しゃくはち)”も10号鉢を指します。
このように理解が深まれば、ガーデニングで植木鉢を用意する際にもサイズが想像しやすくなり、庭づくりがより一層楽しめます。
関連記事⇒「初心者が小さいお庭でガーデニングを楽しむための基礎知識」
家づくりに尺貫法が使われている理由
古くから使われてきた歴史のある尺貫法ですが、現在では廃止されています。それなのになぜ、今も家づくりの際に尺貫法が使われているのでしょうか。
尺貫法の由来と歴史
尺貫法は中国が起源といわれており、その後日本に渡り、大宝律令(701年)から日本の尺度として使われました。以降、1000年以上にわたり人々の暮らしの中で使われてきたのです。やがて度量衡法(1891年)の制定によりメートル法が日本で正式に認められ、計量単位として尺貫法とメートル法の2つが併用されることになりました。
第二次世界大戦の後、メートル法が広く使用されるようになったため、尺貫法は1959年に廃止され、土地や建物の取引以外では使われなくなりました。
国際単位系が統一された1966年以降、尺貫法の単位は内部計算など限られた場面のみで使用され、不動産取引や証明においてはメートル法を使用しています。
メートル法とは
メートル法とは「長さの単位をメートル、質量の単位をキログラム」とし、世界共通で使える統一された単位です。日本では1891年に、尺貫法とともに公認されました。
なぜ現在も尺貫法が使われるのか
それではなぜ、家づくりでは今でも尺貫法が使われているのでしょうか。
諸説ありますが、「私たちの体のサイズを元に生まれた尺貫法の単位は建築計画に便利で、家づくりに必要な各種建材や設備類の多くが今でも尺貫法をベースとしたサイズで構成されているから」という説が有力なようです。
住宅設計の正式な書類や図面に尺貫法の単位を使うことはできませんが、尺貫法は今なお私たちの暮らしに息づいているといってよいでしょう。
おすすめ記事
2025.07.07
尺モジュールとメーターモジュールとは

モジュールとは
“モジュール”とは、ひとまとまりの機能や部品、基本の単位を表す言葉で、住宅設計や建築においては基本となる寸法を指します。先述したように、尺貫法は廃止されていますが、効率良く長さや大きさを把握できる“尺モジュール”は今も利用されています。事前に知っておくと打ち合わせの内容を理解しやすいでしょう。
尺モジュールとメーターモジュールとは
・尺モジュール
3尺=約910mm(91cm)で、設計図では3尺×3尺を1マス(グリッド)としています。
この2マス(グリッド)並べた大きさが一般的な畳1枚に相当します。
関連記事⇒「6畳は何平米? 狭さを活かしたお部屋のレイアウトと快適なマイルームのつくり方」
・メーターモジュール
1,000mm(1m)を基本とする寸法で、設計図では1m×1mを1マス(グリッド)としています。
建材や建具など尺モジュールで展開されている製品は多く、どちらのモジュールを採用しているかによって建築費用に影響が生じます。このため、家を建てる際は、ハウスメーカーや工務店がどちらの基準を採用しているのか確認しておきましょう。
尺貫法とメートル法 家づくりにおける違いとメリット
尺や寸、間で表現されてもピンとこないからと、なじみのあるメートル法で家づくりをしたいと思われる方もいるのではないでしょうか。
メーターモジュールを基本寸法として家を建てる際は、それぞれの空間や設備が尺モジュールよりも約20%広く、大きくなります。廊下やトイレのような限られたスペースではゆとりを感じるでしょう。室内で車椅子を利用するなど、バリアフリーやユニバーサルデザインを考慮した間取りを実現しやすくなります。
また、尺モジュールで家を建てる際には、建設会社との意思疎通のしやすさ、建具や設備の選択肢が豊富な点やコスト面、コンパクトな土地で家づくりがしやすいといったメリットがあります。
尺モジュールとメーターモジュールの違いやメリット、ユニバーサルデザインについてはこちらの記事で解説していますのでぜひご覧ください。
関連記事⇒「モジュールとは 尺モジュールとメーターモジュールの違いとそれぞれのメリット」
関連記事⇒「キッチンのサイズ・寸法は尺モジュール? 使いやすい大きさや高さはどれぐらい?」
関連記事⇒「ユニバーサルデザインとは バリアフリーとの違いと住宅に取り入れるメリット」
建築業界では今も尺貫法が多く使われている一方で、メートル法を採用している会社も増えています。尺貫法とメートル法、それぞれの良さを把握しておくと家づくりがスムーズに進むかもしれません。
和紙の畳表が魅力! DAIKEN『ダイケン畳 健やかくん』
古くから使われてきた尺貫法のように、長く日本で親しまれてきたのが畳や和室です。より住みやすい家づくりのために、好きなときにゴロリと横になれる和室を設けてみるのはいかがでしょうか。

和紙の畳表が魅力のDAIKEN『ダイケン畳 健やかくん』は、畳の持つあたたかでやさしい風合いを大切にしながらも、カビの発生やダニの増殖を抑え、快適さを長くキープします(※1)。
撥水性があるので水分や汚れが染み込みにくくお手入れも簡単です。また、耐摩耗性にすぐれ、ペットの爪や玩具の傷も付きにくく美しさを保ちやすいという特長も持ち合わせています(※2)。

バリエーションも豊富で伝統的な和室からモダンな空間まで美しく演出してくれます。
人にも環境にもやさしい『ダイケン畳 健やかくん』を、家の雰囲気に合わせて取り入れてみてはいかがでしょうか。
(※1)機械すき和紙を使用しています。コウゾ、ミツマタ等を使用した手すき和紙ではありません。
(※2)表面に撥水(はっすい)加工していますが、しょう油やコーヒーなど液体をこぼした場合は乾いたタオルでただちに(2~3分の間に)拭き取ってください。長時間放置すると汚れが落ちにくくなります。汚れが付着した場合には、薄めた中性洗剤を布に含ませ固く絞ってから強くこすらずに拭き取ってください。
まとめ
家づくりでは、意見を自由に出し合えるプランニングが重要です。ハウスメーカーや工務店との打ち合わせでは、尺貫法の単位をベースにプランニングが進んでいく場合も少なくありません。尺貫法への理解を深めることは家づくりにおける基本的な寸法やサイズ感を把握することにもつながり、より快適な家づくりへの手助けになるかもしれません。
建設会社それぞれの特徴や違いについてもぜひご覧ください。
関連記事⇒「ハウスメーカーとは? 工務店とはどこが違うの? 選び方のコツとメリット」
関連記事⇒「設計事務所に注文住宅を依頼するメリットは? 設計施工分離発注と設計施工一括発注の違い」
関連記事⇒「工務店とは? ハウスメーカーや設計事務所との違いと特徴をチェック」

-
監修者
淀川 美和(よどがわ みわ)
株式会社アートアーク一級建築士事務所代表。一級建築士、インテリアコーディネーター、2児のママ建築家。「ママをきれいにする空間づくり」 をミッションの一つに掲げ、住宅・店舗・ホテル等の設計、内装コーディネート、メディア出演等を行う。自身も仕事と家事と育児のバランスをとりながら、忙しいママがいかに快適に家族と暮らせるかに焦点をあてつつ「お部屋のコンシェルジュ」として皆さまのお役に立てるよう奮闘中。
保有資格:一級建築士、インテリアコーディネーター、建築士会インスペクター、健康住宅アドバイザー、整理収納アドバイザー2級、アロマ検定1級

-
監修者
志鎌のり子(しかまのりこ)
一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。
保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など
公開日:2025.04.30 最終更新日:2025.09.19
関連製品
-
小粋でモダンな市松模様が魅力です
-
緻密でシンプルな美しい織り目が魅力です
おすすめ記事Recommends
-
2025.04.30
-
2025.05.20
-
2025.04.30