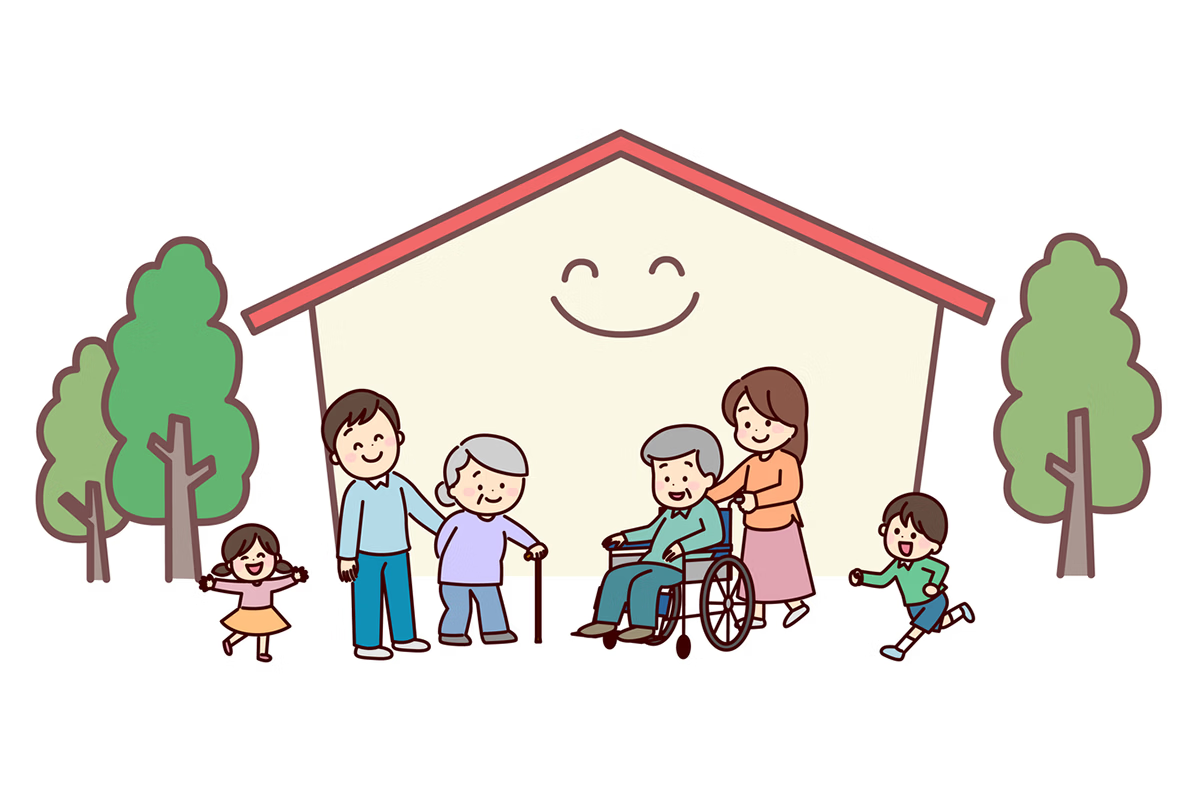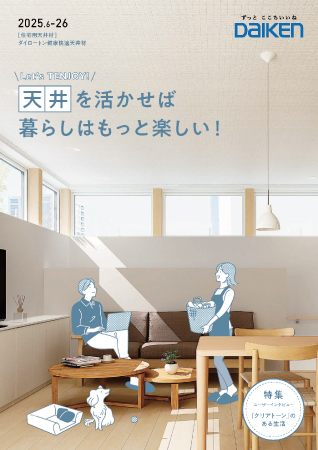住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。
家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
目次
2025年4月に建築基準法が改正されたことにより、省エネ基準適合の義務化と4号特例の縮小が実施されました。この改正で私たちの家づくりにはどのような影響が出るのでしょうか?
今回は、省エネ基準適合住宅の基準や基準適合義務化によって縮小された4号特例をわかりやすく解説します。そして、省エネ住宅の実現につながるDAIKENの天井材『クリアトーン12SⅡ』もあわせてご紹介します。
省エネ住宅の適合基準とは?
省エネ住宅とはどのような住宅で、適合基準とはどのように決められるのでしょうか。
そもそも省エネ住宅って何?
省エネ住宅とは、建物の断熱性や気密性を高めたり、省エネ設備を導入したりするなどの取り組みによって、冷暖房エネルギー消費を抑えた住宅です。具体的には「高断熱材を使用」「高性能な窓を採用」「効率的な換気設備を設置」などがあげられます。
このように断熱性能を高めた住宅なら夏は涼しく冬は暖かく過ごせるため、効率の良い省エネ設備によってさらにエコで快適な暮らしが実現します。光熱費の負担も軽くなり、二酸化炭素排出量も削減でき、経済的にも環境にもやさしい住宅なのです。
参考:「省エネルギー住宅とは」(経済産業省)
省エネ住宅の基準は何で決まる?
省エネ住宅にはいくつかの基準がありますが、国が定めているのは住宅の品質確保の促進等に関する法律による断熱性能を表す“外皮性能”と、住宅・建築物で使うエネルギー消費量を評価する“一次エネルギー消費量”を基にした省エネ基準です。
外皮性能は屋根や壁、窓を通して室内の熱がどれくらい出入りするのか、冷房期には室内にどれくらい日射が入るのかなどを数値化し、それをもとに地域ごとに等級分けしたものです。2022年3月までは等級4が最高等級でしたが、2022年4月以降に等級5~7が設定されました。
一次エネルギーの消費量は、設計時に予想されるエネルギー消費量を標準的な住宅のエネルギー消費量と比較して算出します。2013年に確立され、最高等級は6です。
”快適な住まい”ということでは、良好な住居環境や性能などの基準を満たした”長期優良住宅”もあります。長期優良住宅に認定されると、どのような良いことがあるのでしょうか。
関連記事⇒「長期優良住宅とは? メリット・デメリットと認定基準の条件を知っておこう」
2025年4月から適用される省エネ住宅の適合基準 ― 義務化で何が変わる?
これまで省エネ基準は努力義務として位置付けられていましたが、2025年4月からはすべての新築住宅・非住宅(事務所や商業施設など)で適合が義務付けられました。義務化への背景と義務化で何がどのように変わるのかをみていきましょう。
基準適合が義務化された背景
省エネ住宅の基準適合が義務化された背景には、国の地球温暖化対策とエネルギー資源の問題があります。日本では全エネルギー消費量の約3割を建築分野が占めており、この消費を削減することによってエネルギー問題と環境問題の両面で成果が出ることを期待されているのです。
今後、すべての新築住宅は省エネ基準を満たすことが義務となるので、環境負荷の低減に対する取り組みは一層加速していくでしょう。
参考:「建築物省エネ法のページ」(国土交通省)
義務化された基準の内容とは?
今回の法改正によって、すべての新築住宅・非住宅に義務化された省エネ適合義務の内容を確認しましょう。
具体的には、
・断熱性能:等級4以上
・一次エネルギー消費量:等級4以上
が義務化されました。
新築住宅を建てる際は、この断熱性能や一次エネルギー消費量の基準値をクリアしなければなりません。
基準に適合しているかどうかを判断するためには、建築確認申請時に適合性判定を受ける必要があります。ただし、計算なしで省エネ基準への適合を確認できる“仕様基準”を用いる場合、省エネ適合性判定の免除が可能で、手続きが簡略化できることから国土交通省でも利用を推奨しています。
この仕様基準は、国土交通省が設けている“仕様基準ガイドブック”のチェックリストに外皮性能と一次エネルギー消費量の値などを入力することで省エネ基準適否が判定できるもので、申請書類に添付します。
これまでの基準と、これからの基準
国土交通省では今後さらに最低ラインを引き上げる方針で、2030年以降に新築される住宅はよりレベルの高い“ZEH(ゼッチ)”水準の省エネ住宅の標準化を目標に、段階的な省エネ基準の引き上げが予定されています。太陽光発電など再生可能エネルギーの活用は徐々に普及しており、これからは一般住宅でもエネルギーの自給率向上を目指す方向にシフトしていくでしょう。
参考:「家選びの基準変わります」(国土交通省)
おすすめ記事
2025.08.20
省エネ基準適合の義務化にあわせ「4号特例」も変わる
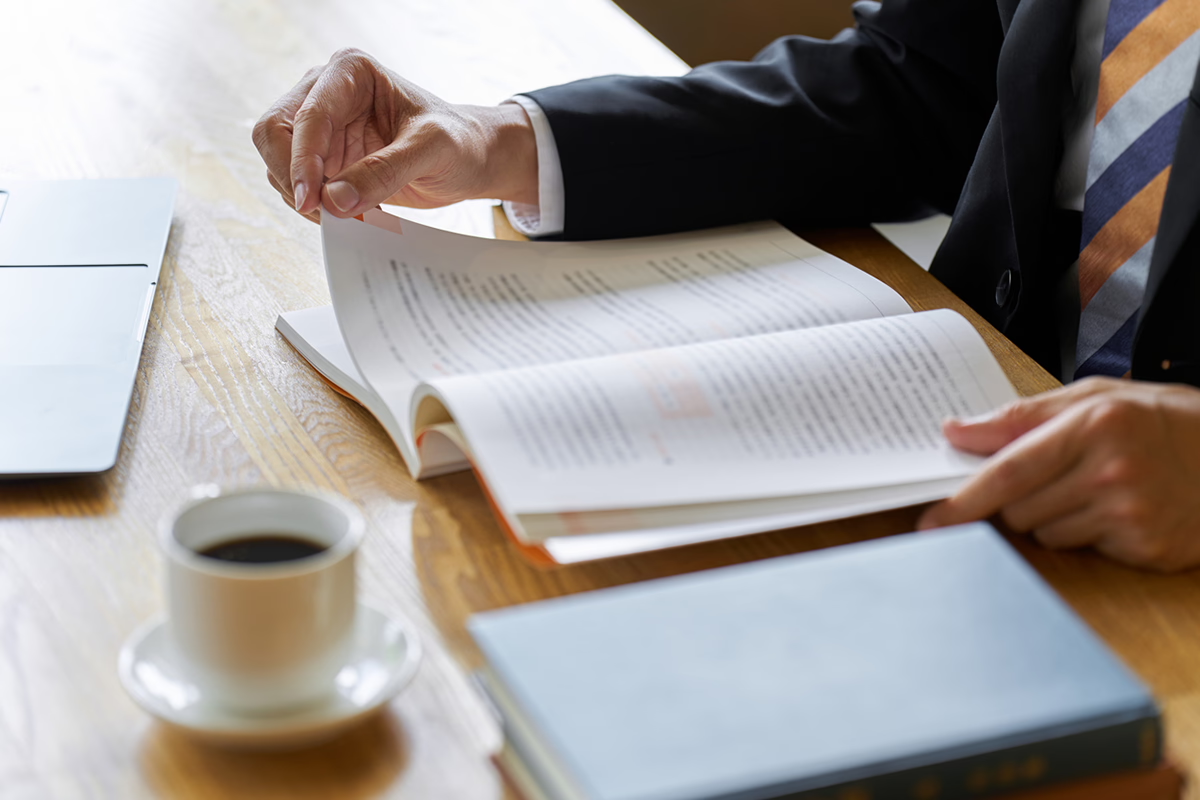
省エネ基準適合が実施される2025年4月からはこれまであった“4号特例”がなくなり、“4号特例の縮小”という形に変更されました。
あまりなじみのなかったこれまでの“4号特例”ですが、新築住宅と関連の深いワードなので押さえておきましょう。
4号特例とは?
4号特例は建築基準法第6条の4に基づき、一定の小規模建築物(4号建築物といいます)に対して確認申請時の構造計算や設備基準の適用を緩和(免除あるいは省略)する制度です。
対象は、木造2階建て以下の戸建て住宅や小規模な共同住宅などです。これまでは、これらの住宅を建てる場合、構造計算などの提出を不要にすることで設計者や施工者の負担を軽減し、経済成長に伴う住宅の建設ラッシュに対応してきました。
しかし、地震・台風など自然災害などによる被害が増加した現在も、これまでのように構造計算など建築確認の審査内容を一部省略したままだったのです。
2025年4月からの見直し内容
そこで省エネ基準適合義務化の流れに合わせ住宅の安全性を同時に確保するため、2025年4月から4号特例の対象範囲が見直され、適用要件が厳格化されることになりました。この変更によって建築主は確認申請の際に構造関係規定等図書の提出が必要になり、これまでよりも厳格なチェック体制が求められることになります。
また、これまで省エネ基準の適用が免除されていた小規模住宅も、今後はすべての新築住宅が省エネ基準を満たさなければなりません。これにより、省エネ基準の確保が期待されています。
参考:「4号特例が変わります」(国土交通省)
おすすめ記事
2025.04.30
家づくりへの影響は? メリットとデメリット
今回の建築基準法改正は、家づくりにどのような影響を及ぼすのでしょうか。省エネ基準適合住宅の義務化と4号特例の縮小によるメリット・デメリットを考えていきます。
省エネ基準適合住宅義務化の影響
省エネ基準適合住宅の義務化により、建築物の断熱性や気密性が上がり冷暖房効率が向上するため、光熱費の削減が期待できます。快適な室内環境が維持されるので、健康リスクの軽減にもつながるでしょう。
また、耐震性能や建物の寿命が向上し、長期的な資産価値の維持が可能です。省エネ性能が高い住宅は“フラット35S”などの低金利住宅ローンが利用しやすくなるため、金融面でのメリットもあります。
一方で、省エネ基準適合に伴う建材や設備の導入が必要となるため、初期建築費は増加する傾向にあります。特に、断熱材や高性能窓のコストは以前より高くなるでしょう。
そして、基準を満たすために必要な専門知識を持つ施工業者や設計者を選定する傾向も強くなると考えられます。知識や技術が不十分な業者に依頼すると基準をクリアできない可能性もあるので、業者の選定にはより慎重さが求められるでしょう。
4号特例縮小の影響
4号特例の縮小によって住宅の安全性や品質は担保されるとみられます。これまで小規模建築物に対して緩和されていた基準から省エネ性能や構造計算が適切に実施されるため、耐震性や断熱性など、住宅の品質や快適性が一段と向上するでしょう。
一方、確認申請の手続きが複雑化することで、工期が延びる可能性も生じます。特にこれまで特例で免除されていた部分が厳格化されたため、設計や施工の手間が増えて人件費やコストがかさむ可能性があります。コスト管理を適切に行える業者を選定しましょう。
高気密・高断熱性能によりエネルギー消費を極力抑える超省エネルギー住宅“パッシブハウス”をご存じですか。厳しい基準に裏付けされたパッシブハウスの快適性をご紹介します。
関連記事⇒「パッシブハウスとはどんな家? 特徴と費用の目安、建てる際の注意点をあわせてご紹介」
調湿性能で快適な住まいと暮らしをつくるDAIKENの天井材『クリアトーン12SⅡ』

DAIKENでは、省エネ住宅に寄与する様々なアイテムを取り揃えています。今回おすすめしたいのは、部屋の湿気や乾きすぎを防ぐ天井材、『クリアトーン12SⅡ』です。
調湿性能の天井材で快適性と省エネを叶える
『クリアトーン12SⅡ』は、湿度が高いときは空気中の湿気を吸収し、逆に湿度が低い時にはためこんだ湿気を放出する調湿性能のある天井材で、快適に暮らせる空間を演出します。
一般的に湿度が20%下がると、体感温度は約1℃下がるとされています。
エアコンの設定温度を1℃緩和できれば、冷房時で約13%、暖房時には約10%の電力量削減に、そして電力量の削減はCO2の排出量削減にもつながります。部屋の湿度調整は快適に過ごすためにも、省エネのためにも大切といえるでしょう。
参考:「家庭のエネルギー事情を知る」(環境省)
部屋干しにもおすすめ
調湿効果を持つ『クリアトーン12SⅡ』は、普段から洗濯物を部屋干ししているご家庭にもおすすめです。DAIKENの部屋干し実験では、『クリアトーン12SⅡ』を施工した部屋は一般的なクロス仕上げの部屋と比べて時間が短縮されることが確認されました。
さらには不快なニオイを抑える消臭性能と、生活音の響きをやわらげる吸音性能もあわせ持っています。洗濯物を部屋干しすることが多いご家庭や、階下やご近所への音漏れが気になるご家庭におすすめです。
まとめ
省エネ基準適合が義務化されたことにより、手続きが増えるなどのデメリットがあるとはいえ、住宅全体の省エネ性能や快適性がアップするのは大きな進歩であり、家づくりを検討する方にとっては好ましいことです。
天井材などの内装材にもこだわって、さらに暮らしやすい住環境を整えてはいかがでしょうか。

-
監修者
志鎌のり子(しかまのりこ)
一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。
保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など
関連製品
-
爽やかな空気をつくる天井材
おすすめ記事Recommends
-
2025.08.20
-
2025.05.20
-
2025.07.07