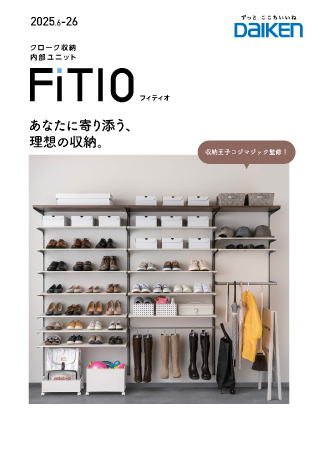住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。
家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
目次
新築の我が家への引っ越しは、人生の新たなスタートとして、多くの方にとって心に残る節目となるのではないでしょうか。公的な手続きや荷造り、引っ越し先の隣人への手土産を考えるなど、準備段階から何かと慌ただしくなりがちです。
今回は、引っ越しの作業や手続きを時系列で整理してスムーズに引っ越しするポイントを解説し、あわせて新生活を快適に始めるDAIKENの玄関収納をご紹介します。
引っ越しが決まったらすぐにやること(1か月以上前)

やることの多い引っ越し作業では、やるべきことを漏れなく進めることが大切です。
引っ越しが決まったら、早めに計画を立てて準備しましょう。まず、1か月以上前に着手しておくべき項目を順に確認します。
① 賃貸物件の解約
賃貸住宅にお住まいの場合、現在の住まいの退去日を決めて管理会社に連絡します。多くの物件では退去の1か月前までに解約の連絡が必要です。ただし、物件によっては2か月以上前の連絡を求められるケースもあります。通知期限は賃貸借契約書に明記されていますので、必ず確認したうえで手続きをしてください。連絡が遅れると、余計な家賃が発生する可能性もあります。
② 引っ越し会社の選択
春の引っ越しシーズンや週末は引っ越し会社が混み合って予約が取りにくいため、早めの会社選定が必要です。複数の会社から見積もりを取り、サービス内容や料金を比較しましょう。
③ 駐車場の解約・契約
自動車を所有している場合は、現在の駐車場の解約手続きと、新居の駐車場を忘れずに確保します。
④ 電気・ガス・水道の停止と契約手続き
ライフラインの停止と開始の連絡は、早めに済ませておきましょう。電気・ガスの供給会社と自治体の水道局に連絡し、旧居での停止日と新居での開始日を調整します。ガスの閉栓・開栓については、原則として当日の立ち会いが必須です。立ち会い者は契約者本人のほか代理人でも問題ありませんが、作業にはおおむね20~40分ほど要するので予定を調整しておきましょう。
⑤ インターネット・固定電話・ケーブルテレビの手続き
インターネットや固定電話、ケーブルテレビの移転は、新たに回線工事が必要なケースもあるため、早めに申し込むことをおすすめします。リモートワークやオンライン授業など通信環境が不可欠な家庭では、引っ越し先でもスムーズにインターネットが利用できるよう手続きを進めましょう。
⑥ 子どもの転園・転校手続き
お子様がいるご家庭では、引っ越しによる保育園・幼稚園・学校の転園や転校手続きが必要になります。学校によっては事前に面談を求められるケースもあるため、できるだけ早く手続きを始めて、スムーズに引き継ぎを行いましょう。
引っ越し前にやること(2週間前~前日)
引っ越し直前になって慌てないために、2週間前から前日までの準備が転居成功のカギです。優先順位をつけて、効率的に作業を進めましょう。
① 新居で必要なものの購入・搬送の手続き
カーテンや照明器具、ゴミ箱など必要品の買い出しをします。これらの生活必需品は、引っ越し当日から使えるように準備しておきましょう。
冷蔵庫や洗濯機などの大型家電やソファなどの大型家具は、設置位置や搬入経路を事前に確認しておくと、引っ越し当日のトラブルを防げます。
② 荷造りとそのコツ
引っ越しの荷造りのコツは、一度にすべてを行わず少しずつ進めることです。シーズンオフの衣類やあまり使わないものからダンボール箱などに詰めていくと効率的です。新居で荷ほどきしやすいよう、ダンボールには部屋名や中身のほか、「ワレモノ注意」なども記載しておきましょう。
使用するダンボールサイズも、荷物の種類ごとに使い分けると梱包がしやすく、荷ほどきも効率的に進みます。引っ越し会社からダンボールが提供されたら、小さいサイズのダンボールには重いもの、大きめのダンボールには比較的軽いものを入れるなど、意識して荷造りするとよいでしょう。
③ 役所で行う手続き
引っ越し前に済ませておく、役所での主な手続きをご紹介します。お住まいの自治体によって手続き方法が異なるため、事前にご確認ください。
・転出届
居住地の市区町村から他の市区町村に引っ越しする場合は、まず現住所の役所で転出届を提出し、転出証明書を受け取ります。手続きは転居予定日の14日前から可能です。
同一市区町村内の住み替えなら転出証明書は不要で、住み始めた日から14日以内に転居届を出すだけで手続きが完了します。
・国民健康保険
国民健康保険に加入している場合は、転出時に保険の資格喪失の手続きを行います。転入先の役所で再加入の手続きをするため、保険証は忘れずに持参しましょう。
・児童手当
児童手当を受給しているご家庭は、転出・転入それぞれの自治体で手続きが必要です。現住所の役所に受給事由消滅届などの書類を提出し、新住所の役所で認定請求を行います。
④ 郵便局で転居届・転送サービスの申請
郵便の宛先を新住所に変えるためには、郵便局に転居届を出します。届け出から1年間は旧住所宛の郵便物を新居に転送してもらえるため、重要な書類の受け取り漏れを防止できます。
⑤ 不用品の整理と処分
不要になった家具や家電、衣類などを整理し、リサイクルショップへの持ち込みや自治体の粗大ゴミ回収、引っ越しゴミの回収会社などを利用して処分しましょう。ゴミの出し方は自治体ごとにルールが異なるため、事前に確認が必要です。
⑥ 掃除と原状回復
賃貸住宅の場合、契約時の内容に基づいて借り主が原状回復を行います。部屋全体の掃除から始め、キッチンや浴室などの水まわり、床や壁、窓やサッシの埃なども丁寧に掃除します。次に、破損や汚れがある箇所を確認し、軽微なものであれば可能な範囲で補修を行いましょう。
おすすめ記事
2025.07.07
引っ越し後にやること

新生活を本格的にスタートさせるには、いくつかの大切な手続きを済ませなければなりません。クレジットカードの住所変更などは後回しにしがちなので、忘れずに手続きをしましょう。
① 役所で行う手続き
引っ越し後に役所で行う主な手続きを項目ごとにご紹介します。お住まいの自治体により手続き方法が異なるため、詳細は転居先の役所にお問い合わせください。
・転入届
旧住所の役所で受け取った転出証明書を持って、新住所の自治体で転入届を提出します。期限は引っ越し当日から14日以内です。
・国民健康保険
国民健康保険に加入している場合、新住所の自治体で加入手続きを行います。保険証や転出証明書、本人確認書類などが必要になります。
・国民年金
国民年金の住所変更も必要です。保険者区分により次のように手続きが異なります。また、マイナンバーと基礎年金番号がひもづいている被保険者は、原則として住所変更の届出は不要です。
| 自営業、学生、無職(第1号被保険者) | 引っ越し先の市区町村役所の窓口で手続きをする |
| 会社員(第2号被保険者) 扶養家族(第3号被保険者) |
会社員の場合は、事業所に「被保険者住所変更届」を提出。この書類により扶養家族の分も手続きをしてもらえる |
・印鑑登録
印鑑登録の住所変更も必要です。同じ市区町村内の引っ越しであれば転居届を出すことで印鑑登録の住所も変更されます。違う市区町村への引っ越しの場合は、転入先の役所で新たに登録を行います。手続きに必要なのは、本人確認書類と実際に登録する印鑑です。
手続きは自治体ごとに制度が異なるので、事前に確認しておきましょう。
・児童手当
お子様がいるご家庭は、児童手当の認定請求書を新住所の役所に提出する必要があります。所得証明や口座情報などを求められる場合もあるため、事前に必要書類の確認をしておくと安心できるでしょう。手続きは引っ越しの翌日から15日以内に行います。
・マイナンバーカード
マイナンバーカードを持っている場合、住所変更の手続きが必要です。多くの場合、転入届と同時に申請できます。
② 警察署で行う手続き
運転免許証の住所変更は、警察署や運転免許センターで手続きができます。免許証のほか、住民票など新住所を確認できる書類が必要です。免許証は身分証として使う場面が多いため、早めに手続きを済ませることが大切です。また、車を所持している場合、引っ越し先の管轄警察署で車両の住所登録の変更や保管場所証明申請を行う必要があります。
③ 銀行口座やクレジットカードの住所変更
銀行口座やクレジットカードの登録住所も忘れずに変更しましょう。ネットバンキングを利用しているときには、オンラインで手続き可能なケースが多くなっています。保険や証券口座なども含めて、全体をチェックしておきましょう。
④ 飼い犬の登録
引っ越しから30日以内に、鑑札と注射済票を持って新住所の役所や保健所などで住所変更をします。
マイクロチップを装着している場合は、環境省のサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で変更手続きが可能です。
おすすめ記事
2025.06.23
-
カーポートとは? ガレージとの違いと値段、固定資産税についてもチェック!
戸建てのマイホームを計画する際、間取りやデザインと同様に重要なのが、駐車スペースをどのように設けるか...
近隣への挨拶と手土産(挨拶品)選びのコツ

近年、防犯やプライバシーの観点から、都心部の集合住宅などでは引っ越しの挨拶を控える傾向もみられます。しかし、引っ越しの挨拶はこの先顔を合わせる近隣住民との関係性を築く第一歩になります。できれば挨拶はしておくと安心です。
手土産は何にする? 近隣のどこまで挨拶する?
手土産には日持ちするお菓子、タオルや洗剤などの実用品が一般的です。500~1,000円程度のものを目安に、相手が気を遣わない価格帯にします。
一戸建ての場合は、自宅を中心に両隣と道路を挟んだ向かい3軒、裏のお宅までを目安に挨拶しておくとよいでしょう。
訪問時のマナー
訪問は引っ越し当日または翌日の、日中の明るい時間帯が望ましいとされています。何度か訪ねても留守の場合は、簡単な挨拶状かメモを添えて、挨拶の品をポストに入れておくと丁寧な印象になります。
新生活を快適にするDAIKENの『ieria(イエリア)玄関収納』

隣人を自宅に迎えたとき、靴や荷物が散乱しているとお互いに気まずい思いをする可能性があります。引っ越し後は、まず玄関を整理しましょう。
DAIKENの『ieria(イエリア)玄関収納』は、機能的でありながら心地良い玄関を実現しやすい収納ユニットです。
ユニット連結式で、幅や高さ、ウッド扉やミラー扉などの組み合わせを選べます。扉裏収納など各オプション、色柄も豊富なので、新しいお住まいにぴったりの玄関収納が選べます。
引っ越し前にやること・引っ越し後にやること チェック表
これまでご紹介した引越しの手続きを、時系列の一覧表にしました。引越しの際のチェック表としてご活用ください。
| 時期 | 項目 | ポイント |
|---|---|---|
| □1か月以上前 | □賃貸物件の解約 | 退去日の通知。連絡が遅れると家賃が発生する可能性あり |
| □引っ越し会社の選定 | 複数社の見積もり・サービス比較。繁忙期は早めの予約を | |
| □駐車場の解約・契約 | 現駐車場の解約と新居の駐車場確保を忘れずに | |
| □電気・ガス・水道の停止と契約 | 電気・ガスは供給会社、水道は自治体に「停止日と開始日」を連絡 | |
| □インターネット・固定電話・ケーブルテレビの手続き | 回線工事が必要な場合もあるため早めの手続きを | |
| □子どもの転園・転校手続き | 保育園・幼稚園・学校の転園・転校は早めに手続きを | |
| □2週間前~前日 | □新居で必要なものの準備 | カーテン・照明・ゴミ箱など生活必需品の購入。新居の搬入経路を確認 |
| □荷造り | シーズンオフのものから少しずつ梱包 | |
| □役所での手続き(転出届など) | 転出届、国民健康保険、児童手当の手続き | |
| □郵便局への転居届の申請 | 1年間の郵便物転送サービス。インターネットまたは窓口で手続きを | |
| □不用品の整理・処分 | 自治体の粗大ゴミ回収・リサイクルショップの活用 | |
| □掃除・原状回復 | 水まわりなどを重点的に清掃。破損箇所の補修 | |
| □引っ越し後 | □役所での手続き(転入届など) | 転入届、国民健康保険、国民年金、印鑑登録、児童手当、マイナンバーカードの手続き |
| □警察署で免許証の住所変更 | 警察署または運転免許センターで手続き | |
| □銀行・クレジットカード等の住所変更 | 保険・証券口座なども忘れずに |
まとめ
引っ越しは、単なる荷物の移動ではなく、やるべき作業がたくさんある大きなイベントともいえます。時系列に沿って優先順位を整理して、着実に進めることが大切です。
挨拶や手土産の準備も忘れずに行い、良好な近所付き合いの第一歩を踏み出しましょう。新居の玄関は、新しいご近所の方々との接点にもなります。DAIKENの玄関収納を取り入れて、見た目はもちろん機能性も兼ね備えた玄関を実現してみてください。

-
監修者
志鎌のり子(しかまのりこ)
一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。
保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など
関連製品
-
機能的で心地いい玄関を実現する玄関収納ユニット
おすすめ記事Recommends
-
2025.06.23
-
2025.06.23
-
2025.06.23