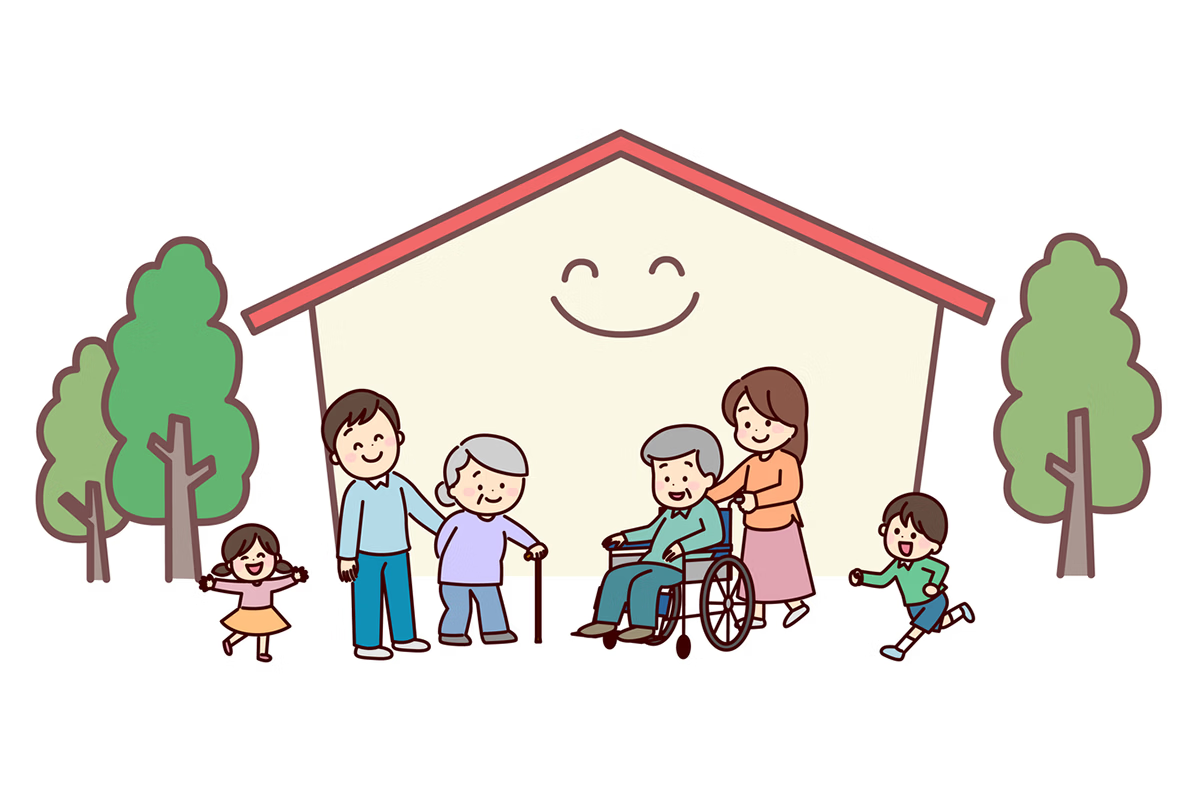住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。
家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
目次
家づくりをする際には“モジュール”と呼ばれる基準寸法を使用して間取りを設計していきます。モジュールには、“尺モジュール”や“メーターモジュール”などがあります。これらはいったいどのようなものなのでしょうか。
今回はモジュールの概要や種類による違い、メリットとデメリットなどをご紹介します。住まいの居住性や使いやすさに大きく関わるモジュールの基本を理解して、家づくりに役立てましょう。
家づくりにおけるモジュールとは?

モジュール(Module)とは、“部品” “要素” “単位”を表す言葉です。
ITや製造業の分野でのモジュールは「特定の機能を持つまとまり」を意味しますが、建築分野では「設計上の基本となる単位・寸法」を表します。
モジュールとは 建築の基本となる基準寸法
建築におけるモジュールには様々な種類があります。共通しているのは建築物の設計における“基準寸法”を指しているところです。
モジュールの概念は古代ギリシャから存在し、建築の基準寸法を“モデュルス(モドゥルス)”と呼んでいたことに由来しているといわれています。
空間スケールの設計に使われるモジュールで有名なのは、フランスの巨匠ル・コルビュジエが提唱した“モデュロール”です。人体の寸法や黄金比(古代ギリシャで発見された最も安定していて美しいとされる比率)を基に、快適な空間を設計するための考え方として使われていました。
一方、現代では「効率的に施工するために決められた工業製品の規格寸法」を一般的にモジュールと呼びます。複雑かつ高度になった現代建築で異なるメーカーの建材・建具・家具などを不自由なく組み合わせるための、いわば共通基準であるモジュールは、品質と適切な工期を守るために欠かせないものといえます。
モジュールが住宅に与える影響
モジュールは、住まいの使いやすさに大きく関係しています。例えば、部屋の大きさや廊下の幅、ドアのサイズなどはモジュールにより決定されます。結果としてモジュールは家具のレイアウトや人の動きやすさにも関わってくるのです。
もちろんモジュールの選定によって、空間構成や採用できる建具・家具のバリエーションも変わります。モジュールは住まいの住みやすさだけでなく、デザイン性やコストにも関連する重要な要素だといえるでしょう。
尺モジュールとメーターモジュールの違い

日本の家づくりで使われている代表的なモジュールは、“尺モジュール”と“メーターモジュール”の2つです。それぞれの特徴とメリット・デメリットをご紹介します。
尺モジュールの特徴とメリット・デメリット
尺モジュールは尺貫法に基づくもので、昔から日本で使われてきた基準寸法です。3尺(約910mm)を基本単位としており、設計図は3尺×3尺を1マス(1グリッド)として作製されます。
尺モジュールのメリット・デメリットは以下のとおりです。
【メリット】
・昔から使われているモジュールなので、採用できる建具や家具が多い
・多くの既製品を組み合わせられるため、施工効率が良い
・畳や襖(ふすま)といった和風建材との親和性が高い
【デメリット】
・メーターモジュールに比べると基準寸法が小さく窮屈に感じる可能性がある
・メーターモジュールで設計された海外製の建具は納まりにくいケースがある
一般的に家づくりでは、多くの既製品を組み合わせてコストと工期を抑えながら施工します。日本で古くから使われている尺モジュールを採用すれば、国内製の既製建材を使って効率的で柔軟な家づくりがしやすくなります。
関連記事⇒「尺貫法とは? 間、尺、寸の長さはどれぐらい? 家づくりで耳にする単位をマスター!」
関連記事⇒「キッチンのサイズ・寸法は尺モジュール? 使いやすい大きさや高さはどれぐらい?」
メーターモジュールの特徴とメリット・デメリット
メーターモジュールは、1,000mm(1m)を基準寸法とする国際的なモジュールで、設計図は1m×1mを1マス(1グリッド)としてつくられます。尺モジュール(約910mm)より2割ほど広いため、同じ間取りであればメーターモジュールでつくる部屋や通路は、尺モジュールでつくる場合より余裕があります。
メーターモジュールのメリット・デメリットは以下のとおりです。
【メリット】
・部屋や通路にゆとりが生まれ、開放感のある空間になる
・高齢者や車椅子利用者が暮らしやすい
・海外製建具やインポートの家具をレイアウトしやすい
【デメリット】
・国内製の建具や家具を採用しにくい場合がある
・改修や増築時のフレキシビリティが低くなる可能性がある
・コストが高くなりやすい
メーターモジュールで国内製の建材を使うと特注となる場合があり、コストが高くなりがちです。一方で、日本人の体格が昔に比べて大きくなっていることも考えると、広々とした空間をつくるのに向いているメーターモジュールは日本でもメリットが大きいといえます。
おすすめ記事
2025.09.19
尺モジュールとメーターモジュールはどちらを採用すべき?

モジュールの選定は、家族構成やライフスタイル、敷地条件などから総合的な判断を行うべきですが、今でも日本では尺モジュールが主流です。工務店などに自由設計の家づくりを依頼する際でも、尺モジュールを採用していれば何かと柔軟に対応してもらえるでしょう。
一方、広々とした空間やユニバーサルデザインに配慮した設計を重視する場合は、メーターモジュールの採用も検討する価値があります。それぞれの部屋が一回り大きくなるため、空間にゆとりが生まれます。また、車椅子利用者も余裕を持って動けるでしょう。1960年代からは一部の大手ハウスメーカーでもメーターモジュールを採用するケースが出てきました。
どちらのモジュールにも一長一短があります。まずは自分が依頼した住宅メーカーや工務店がどちらのモジュールを採用しているかを確認することが必要です。さらに家族構成やライフスタイル、予算などを考慮のうえ、条件を整理して設計者と相談し、必要であればモジュール変更や調整を検討しましょう。
おすすめ記事
2025.09.19
襖と洋風ドアを兼ねる室内ドア、DAIKEN『ieria(イエリア) 戸襖』

最近の家づくりでは洋風建築が多いものの、和室の良さも見直されており、和モダンなど和洋折衷のインテリアには根強い人気があります。こうした和室や畳の多くは尺モジュールで構成されています。だからといってメーターモジュールを採用すると和室が設置できなくなるわけではなく、対応してくれる建設会社もあります。ご自身の希望を叶えられる建設会社を探してみましょう。
自宅に洋室と和室を隣り合わせでつくりたい場合におすすめしたいのが、DAIKENの『ieria(イエリア) 戸襖』です。『ieria(イエリア) 戸襖』は、片面が襖、もう片面が洋風ドアで、洋室と和室を違和感なく仕切れる戸襖です。和洋折衷の家づくりにぴったりなのでぜひお役立てください。
まとめ
モジュールの選定は、住まいの快適性や使いやすさ、デザイン性、施工性、さらにはコストにまで影響を与えます。尺モジュールは採用できる建具や家具のバリエーションが豊富であり、メーターモジュールはゆとりある家づくりに適しています。家族構成やライフスタイルに合わせて最適なモジュールを選び、理想の家づくりへの第一歩を踏み出してください。

-
監修者
志鎌のり子(しかまのりこ)
一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。
保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など
関連製品
-
洋室と和室が隣り合う空間でも違和感なく仕切れる戸襖
おすすめ記事Recommends
-
2025.09.19
-
2025.08.20
-
2025.08.20