住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。
家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。
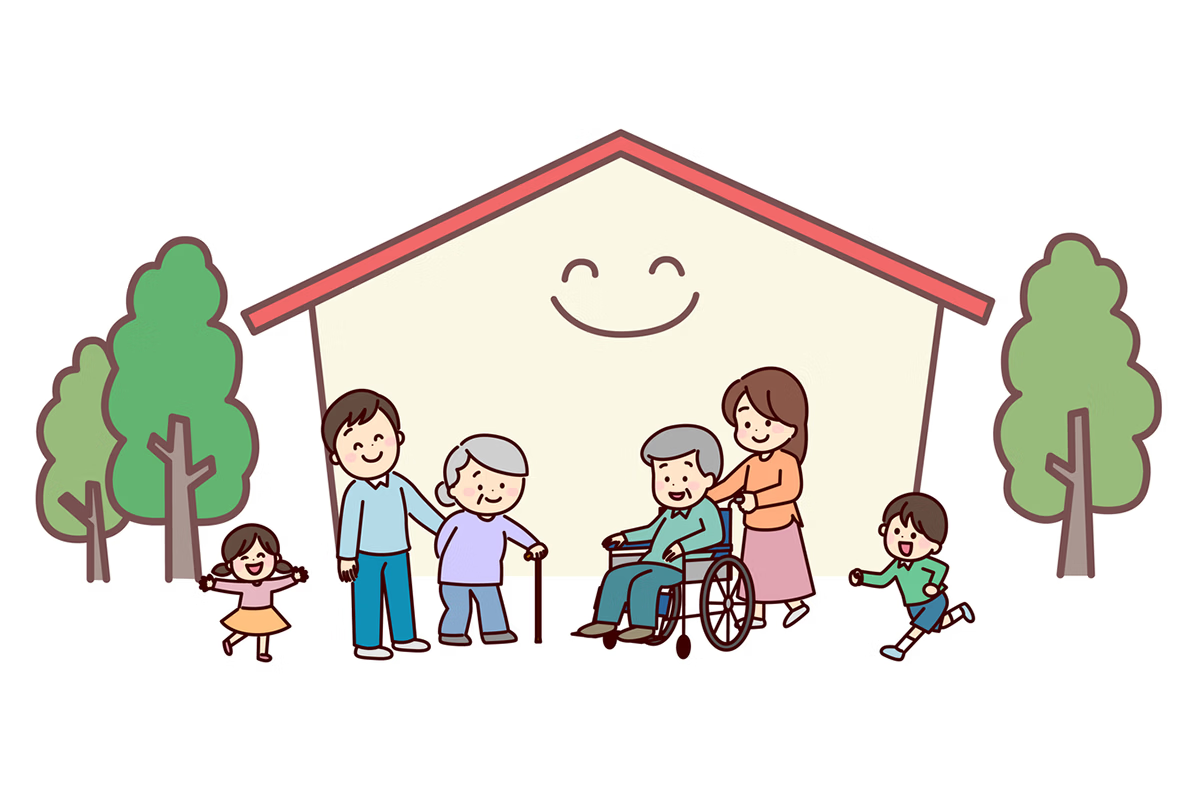
※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
目次
家をつくるなら、家族全員が心地良く安全に暮らせる住まいを目指して、できれば将来的な暮らしの変化にも対応できるようにしたいところです。そのためには、将来を見据えた間取りや設備を検討する必要があります。
そこで参考になるのが、ユニバーサルデザインという設計思想です。
今回はユニバーサルデザインの基本的な考え方や、バリアフリーとの違い、住宅に取り入れるメリットなどをご紹介します。家族みんなにやさしい家をつくりたいと考えている方はぜひ参考になさってください。
ユニバーサルデザインとは
ユニバーサル(universal)とは、“すべてに共通の” “普遍的な” “一般的な”といった意味です。建築設計におけるユニバーサルデザインとは、どのようなものを指すのでしょうか。
誰もが使いやすい建物を実現する設計思想

ユニバーサルデザインは、アメリカのノースカロライナ州立大学ユニバーサルデザインセンターのロナルド・メイス氏が初めて提唱した設計思想とされています。「できるだけ多くの人が利用可能であるように製品、建物、空間をデザインすること」と定義され、それまで主流だったバリアフリーとは異なる新しい考え方を示しました。
国立研究開発法人 建築研究所のホームページに掲載されている資料では、彼が提唱したユニバーサルデザインの7原則が以下のように翻訳されています。
【ユニバーサルデザイン7原則】
1.誰にでも公平に利用できること
2.使う上で自由度が高いこと
3.使い方が簡単ですぐわかること
4.必要な情報がすぐに理解できること
5.うっかりミスや危険につながらないデザインであること
6.無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に使用できること
7.アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること
出典:「ユニバーサルデザイン7原則」(国立研究開発法人 建築研究所)
ユニバーサルデザインが身近に取り入れられている例として、きざみ状の突起をつけて、手で触っただけで区別ができるシャンプー・リンスのボトルなどが有名です。トイレの操作ボタンも視覚的にわかりやすく、点字がついているなど誰にでも使いやすいように配慮されているものが多くあります。
建築設計においても、“誰でも”使いやすい建築や空間を目指すことがポイントになります。

(※)写真はイメージです。
ユニバーサルデザインとバリアフリーの違い
ユニバーサルデザインは、しばしばバリアフリーと混同されがちです。この2つはどう違うのでしょうか。それぞれの言葉を一言で説明すると以下のようになります。
| ユニバーサルデザイン | “誰もが”使いやすいデザイン |
| バリアフリー | “高齢者・障がい者が”社会生活をしていくうえでの障壁を排除すること |
バリアフリーは、高齢者・障がい者などが直面する“障壁(バリア)”を取り除くことが目的で、対象者は特定の人に限られます。一方、ユニバーサルデザインは性別・年齢・障害の有無などにかかわらず、“すべての人への配慮”を基本としています。ですから、バリアフリーは、ユニバーサルデザインの一部と捉えることも可能です。
おすすめ記事
2025.06.23
住宅にユニバーサルデザインを取り入れるメリット

ユニバーサルデザインは、公共施設、病院、学校など不特定多数の利用者が想定される建物で特に重視されますが、個人の家づくりにも取り入れることができます。個人住宅にユニバーサルデザインを取り入れるメリットについてご紹介します。
将来のライフスタイルに柔軟に対応できる
ライフステージが変わると、住まいへのニーズも変化します。“子どもが生まれる” “自宅で親の介護をする” “自分が高齢者になる”などの変化があると、自宅に求めるデザイン性や機能性を見る目が変わるかもしれません。
あらかじめユニバーサルデザインを取り入れた家づくりができていれば、こうした変化にも対応しやすくなります。
資産価値が高まる可能性もある
日本は高齢化が進んでおり、今後もこの傾向は続くと考えられています。そのため、高齢者が住みやすいユニバーサルデザイン住宅はこれからも高く評価されるでしょう。ユニバーサルデザインを取り入れた住まいは、物件の資産価値が上がる可能性もあります。
関連記事⇒「省エネ基準適合住宅とは? 2025年から義務化された省エネ基準と4号特例縮小を解説」
ユニバーサルデザインを取り入れることでバリアフリー関連の補助金を受けられる可能性がある
前述のとおり、バリアフリーはユニバーサルデザインの一部と捉えることが可能です。ユニバーサルデザインの一環として、高齢者・障がい者に配慮したバリアフリーのデザインや設備を取り入れれば、バリアフリー関連の補助金を受けられる可能性があります。
2025年時点では、省エネや子育て支援を目的とする「子育てグリーン住宅支援事業」なども活用できる場合があります。ユニバーサルデザインを取り入れる際は、こうした補助金についても調べてみましょう。
(※)補助金制度は予告なく変更・終了する場合があります。最新の情報は各自治体や関連省庁の公式サイトをご確認ください。
ユニバーサルデザイン住宅ってどのような家?

ユニバーサルデザインを取り入れた住宅がどのような仕様になっているのか、あまりピンとこない方もいるかもしれません。そこで家の中でどのような場所にユニバーサルデザインを採用できるかの例をご紹介します。
玄関・アプローチ
・段差の解消
・スロープ・段差解消機の設置
・引き戸の導入
・ベビーカーや車椅子で出入りがしやすい広さ・幅の確保
・施解錠しやすいドア
玄関やアプローチでは、安全かつ快適に移動できる仕様が重視されます。特に高低差の解消が重要で、スロープをうまく活用すると車椅子の方だけでなく、みんなが使いやすいアプローチになります。玄関には靴の履き替えの際に座れる椅子や、体を支えられる手すりがあるとさらに安心です。
関連記事⇒「玄関アプローチは家の顔 デザインと素材選びで門からの通り道をおしゃれな空間に!」
廊下・階段
・車椅子が通りやすいように90cm以上の幅を確保
・手すりの設置(途切れがないように連続して設置)
・フットライトの設置
・階段の1段ごとの高さを低めに設定する
・目で認識しやすい色の踏板
廊下は、90cm以上の幅を確保することで、車椅子利用者に配慮したつくりになります。また階段の1段当たりの高さを低めに設定し、上り下りの負担を軽減しましょう。
関連記事⇒「廊下で差をつける家づくり 適切な廊下幅は? 収納・照明で自分好みに演出しよう」
トイレ・浴室
・車椅子が転回(180度方向転換)できる広さ
・手すりの設置
・浴室暖房
・レバー水栓や自動水栓の導入
・ベンチカウンターの設置
・便器のふた自動開閉
・引き戸の導入
ユニバーサルデザインでは、トイレ・浴室などの狭い部屋は車椅子が転回しやすい広さを確保します。一般的な車椅子であれば、直径150cm以上の円を確保すれば、360度回転できるとされています。電動車椅子は160~180cm程度の円が必要な場合もありますが、機種や操作により異なるため、設計時に確認が必要です。
また浴室暖房は浴室と脱衣スペースの温度差を軽減して、体への負担をやわらげてくれます。浴室暖房乾燥機を搭載していれば天候に左右されず洗濯物を乾かせるため、より快適に暮らしやすくなるでしょう。
リビング・ダイニング
・段差のないつくり
・回遊性を高めて自由に動きやすい空間をつくる
・床暖房の導入
・音声操作に対応した家電の導入
・調光機能付き照明
リビングやダイニングは段差をなくして安全・快適性に配慮することで、家族みんなが安心して過ごせる場所になります。
回遊性のあるレイアウトを意識すると、高齢者や車椅子利用者を含め、みんながスムーズに移動できるようになり、使いやすさが向上します。
キッチン・洗面所
・座っていても使いやすいカウンターの高さ
・操作しやすい水栓
・十分な広さの確保
・十分な明るさが確保できる照明
キッチンや洗面所などの動作・操作が多い空間は、使いやすさを意識することが重要です。例えばキッチンや洗面台の高さが体に合っていないと、とても使いにくいものです。
車椅子に対応したユニバーサルキッチンでは適切な高さ設定のほか、シンク下をオープンにして足が入れられるスペースを確保するなど、車椅子利用者や座って調理する人への配慮がなされています。
関連記事⇒「洗面所をもっと便利に! 収納棚にタオルやパジャマ・下着を収納できる快適生活」
家全体に共通する項目
・コンセントの位置・高さ
・スイッチプレートの位置・高さ
コンセントやスイッチプレートの位置や高さについても、誰もが心地良く生活するためには重要なポイントです。大人も子どもも、車椅子の方も使いやすい位置に設置することを心がけましょう。
おすすめ記事
2025.05.20
ユニバーサルデザインにおすすめのDAIKEN『OMOIYARIひきドアW』

DAIKENではユニバーサルデザインを意識した住まいづくりに活用できる製品を多数展開しています。例えば『OMOIYARIひきドアW』は通常、引き戸として使えますが、介助・車椅子使用時には開き戸として開けば大開口ドアになるという、画期的な仕組みのドアです。

車椅子の幅は介助用で約560mm、自走式は約640mmあります。本製品は開き戸を全開放することで有効間口を1124 mmまで確保できるため、トイレの間口が狭くても、車椅子のまま乗り入れが可能です。
介助する人もされる人も、もちろん通常のトイレとして利用する人も、すべての人が快適に使えるトイレを実現します。
まとめ
ユニバーサルデザインは「できるだけ多くの人が利用可能であるように」というやさしい気持ちから生まれた設計思想です。住宅に取り入れれば、高齢者・子ども・障がい者を含め、家族みんなが安心・安全・快適に暮らせる住まいになるでしょう。
子どもが生まれたり、年を重ねたりといったライフステージの変化があっても、快適に末永く住み続けられるのがユニバーサルデザインを採用した住まいの大きな魅力です。ユニバーサルデザインを積極的に取り入れて、これからの時代に相応しい住まいを目指しましょう。

-
監修者
淀川 美和(よどがわ みわ)
株式会社アートアーク一級建築士事務所代表。一級建築士、インテリアコーディネーター、2児のママ建築家。「ママをきれいにする空間づくり」 をミッションの一つに掲げ、住宅・店舗・ホテル等の設計、内装コーディネート、メディア出演等を行う。自身も仕事と家事と育児のバランスをとりながら、忙しいママがいかに快適に家族と暮らせるかに焦点をあてつつ「お部屋のコンシェルジュ」として皆さまのお役に立てるよう奮闘中。
保有資格:一級建築士、インテリアコーディネーター、建築士会インスペクター、健康住宅アドバイザー、整理収納アドバイザー2級、アロマ検定1級
関連製品
-
使う人によって開閉状態を選べるフレキシブルなドア
おすすめ記事Recommends
-
2025.08.20
-
2025.05.20
-
2025.07.07

























