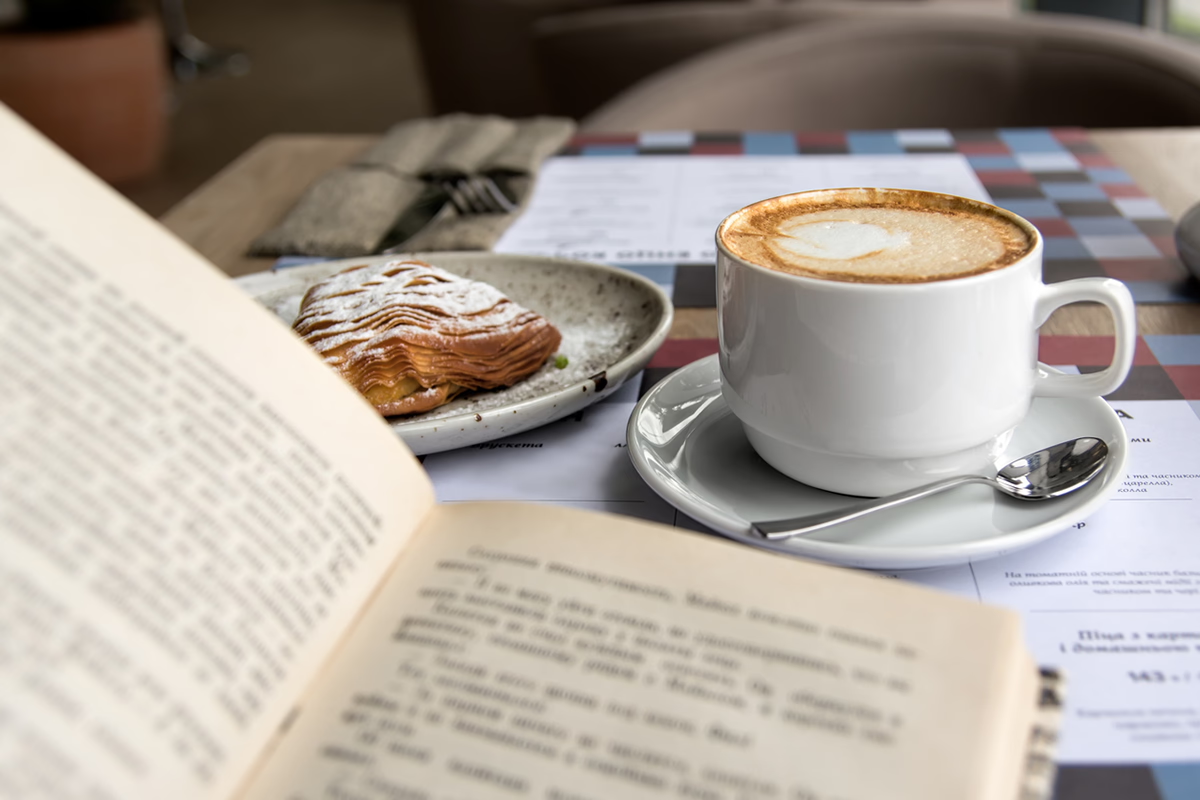住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。
家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
広い敷地を確保しにくい都市部で大きな家をつくりたいとき、選択肢の1つとしてあげられるのが3階建て住宅です。3階建ての家は、生活スペースを確保しながら1階部分にビルトインガレージを組み込むことも可能で、車をお持ちのご家庭にもおすすめです。
今回は、3階建て住宅のメリット・デメリットや計画時の留意点について解説します。利便性の高い都市部に家を建てたいと考えている方はぜひご覧ください。
3階建てのメリット

3階建ての大きなメリットは、十分な広さがない敷地でも高さを出して空間を広げることで、実現できるプランの選択肢が増える点です。
敷地を有効活用できる
駅や繁華街に近いなどの好立地は地価が高く、広い土地を手に入れるのが難しいかもしれません。しかし家を建てる際には、ゆとりのある土地が欲しくなるものです。
3階建て住宅で敷地を有効活用すると、広い土地が必要ではなくなるため、土地代を抑えることができます。3階建て住宅は、平屋や2階建て住宅に比べて坪単価が高くなる傾向がありますが、好立地においては建物代と土地代の合計が安くなるケースもあります。
ビルトインガレージを計画しやすい
独立した駐車スペースを用意するのが難しいコンパクトな敷地の場合は、建物の1階部分をビルトインガレージにするという選択肢があります。建物の1階を駐車場にする分、2階建てだと生活空間は手狭になってしまいますが、3階建てにすれば2・3階で十分な居住スペースを確保でき、日常生活に支障のない広さになるでしょう。車庫に関する悩みを解決しやすい点も3階建て住宅のメリットといえます。
メリハリのある生活をしやすい
3階建て住宅は、階ごとに用途を分けてメリハリのある生活を送りやすくするとよいでしょう。
具体的には、以下のような使い分けをイメージしてみましょう。
・3階:プライベートゾーン(寝室、子ども部屋、書斎)
・2階:パブリックゾーン(LDK、水回り)
・1階:玄関、ビルトインガレージ
家族の共有スペースは2階に、睡眠・勉強・仕事といった静けさが必要な場所は3階に、というように分けると、生活にメリハリが生まれます。
このように、目的に応じてエリアを分けることを“ゾーニング”といいます。ゾーニングについては以下の記事で詳しく解説していますので、家づくりの参考にしてください。
関連記事⇒「住宅におけるゾーニングとは? 機能的な動線や癒やしのある家に近づく間取りのポイント」
おすすめ記事
2025.08.20
3階建てのデメリット
次に、3階建て住宅のデメリットについてみていきましょう。計画段階からデメリットを踏まえ、3階建て住宅をどのようにつくっていくかを考えることが大切です。
建築コストの高さ
3階建て住宅で多くの方がデメリットと感じるのは建物代が高くなる点です。
3階建て住宅は平屋や2階建て住宅に比べると、柱や梁(はり)などの構造部材が多く必要となり、一般的に坪単価が高くなりがちです。また、設計の難易度が上がることから、設計料が高く設定されているケースも少なくありません。
しかし、家づくりは建物代と土地代をトータルで考えることが大切です。3階建てにして土地代を抑えられれば、全体的には安くなる場合もあるでしょう。
階段での移動
3階建て住宅のデメリットの1つに階段の上り下りがあります。ランドリールームや洗濯物を干す場所、浴室などを近くにまとめ、階段の上り下りを減らせる動線を考えるとよいでしょう。

3階建てを計画する際の留意点
3階建て住宅を計画する際は、平屋や2階建てと異なる留意点があります。3階建てならではの気をつける点にはどのようなものがあるのでしょうか。
地域の規制
3階建て住宅の計画を進める前に確認しておきたいのが、用途地域や建ぺい率・容積率など、地域の規制です。場合によっては、建物の高さが制限されていて3階建て住宅を建てられないケースがあります。購入した後で問題が発生しないよう、建築会社や不動産会社などの専門家に意見を聞き、該当する規制を購入前に確認しましょう。
快適な温熱環境を実現する計画
最上階は直射日光を受け、温度が上昇します。さらに、暖かい空気は上に移動する性質があるので夏は3階が蒸し暑くなりがちです。設計者に理想的な温熱環境を伝え、適切な仕様や設備を設定してもらいましょう。
・高断熱・高気密仕様
・高性能窓
・庇(ひさし)・ブラインド・植栽
・エアコン
・全熱交換器付き換気システム
空間のつながりと動線計画に配慮したプランニング
3階建て住宅は明確なゾーニングにより、メリハリのある生活を送りやすい点がメリットの1つですが、リビングなどのパブリックゾーンと、寝室や子ども部屋などのプライベートゾーンが階で分かれると、コミュニケーションの機会が減ってしまう場合があります。
パブリックゾーンを経由してプライベートゾーンにアクセスするプランニングや、吹き抜けで上下階をつないで一体感を演出するなどの工夫により、コミュニケーションが生まれやすい間取りを意識するとよいでしょう。
3階建て住宅では動線の効率化が必要です。浴室やトイレ、キッチンといったサービスゾーンの適切な動線計画で使いやすい家を目指すことがポイントです。
おすすめ記事
2025.06.23
様々なリクエストにお応えするDAIKENの階段製品ラインアップ

階段:『ieria(イエリア) ハモンド<ダルブラウン色>』、手摺部材:『スタンダードタイプ<ダルブラウン色>』
3階建て住宅における階段の選択はインテリアだけでなく、生活のしやすさに関わる大きなポイントです。
天然木のやさしさが魅力の階段部材『ieria(イエリア) ハモンド』は、踏板のノンスリップ溝を大きくしてあるので、より安全にお使いいただけます。エレガントな雰囲気を演出する装飾手摺部材『スタンダードタイプ<ダルブラウン色>』を合わせれば高級感を演出できます。
手触りが良く、住まう人の安全に配慮した笠木セットや手すりもご用意していますので、あわせてご活用ください。
まとめ
3階建て住宅は、土地の広さが限られていても、スペースの確保と利便性の面から選択肢の1つとなるプランです。ゾーニングを意識したプランニングを行い、実際に住んだときにどのような生活になるのかをイメージしながら計画を進めてみてください。

-
監修者
志鎌のり子(しかまのりこ)
一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。
保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など
関連製品
-
階段部材製品ラインアップ
おすすめ記事Recommends
-
2025.05.20
-
2025.05.20
-
2025.05.20