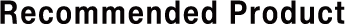ドアの防音性を高める方法は?設計時に考慮したいポイント

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
施設の設計において、空間の防音性を高めることは、快適性や情報保護などの観点から非常に重要な要素となります。防音性の低い空間は多くのリスクを抱えることになり、完成後に問題が生じるケースも少なくありません。
空間の防音性に関わる要素は多くありますが、その中でも「ドア」は設計段階で慎重に検討が必要な部分です。ドアは開口部のため隙間が生じやすく、音漏れの原因となるためです。
そこで本記事では、ドアの具体的な防音対策や、設計における防音の考え方について解説します。設計段階でしっかりと計画し、音問題の起こりにくい空間をつくりましょう。
ドアの防音性を高める重要性
ここではまず、ドアの防音性を高める重要性について掘り下げます。ドアから音が漏れる原因を理解することで、適切な対処ができるようになるでしょう。
●ドアの防音対策はなぜ重要?
ドアは壁や天井に比べて音が漏れやすく、適切な対策がなされていないとさまざまな問題を引き起こします。
具体的には、病院やクリニックでは患者の個人情報や診療内容が診察室外に漏れることでプライバシーが損なわれたり、オフィスでは会議室での会話が外部に聞こえることで、情報漏洩のリスクが高まったります。また、ホテルでは廊下の音や隣室の声が客室内に侵入することで、宿泊者のストレスとなり、満足度の低下につながる可能性もあります。
こうした問題を防ぐためには、設計段階からドアの遮音性能や気密性を十分に考慮することが求められます。
●ドアから音が漏れる原因
ドアは開閉機能を持つため枠や床との間に隙間が生じやすく、特にドアの下部や側面の隙間から音が漏れることが多いです。また、一般的なドアは壁よりも構造が薄いため、遮音性能が劣り、音が透過しやすくなっています。こうした理由から、ドアを通じて隣接する空間同士で音が伝わり、プライバシーや静音性に悪影響を及ぼします。
ドアの主な防音対策
続いて、ドアの主な防音対策について解説します。設計段階で防音対策を取り入れることで、空間全体の調和を図りつつ防音性を高められます。完成後に追加で対策をすると、その部分だけ浮いてしまう可能性があるため、設計段階での対処が重要です。
●ドアの隙間を埋める
ドアの基本的な防音対策の一つとして、隙間を埋めることが挙げられます。音はわずかな隙間からでも漏れるため、ドアの上下や側面の隙間をふさぐことで、効果的に音漏れを防げます。
具体的には、戸当たり部分に隙間テープや遮音テープ、気密パッキンを取り付けることで、音の出入口が小さくなり、防音性を高められます。ただし、隙間を埋めるとドアの開閉がしにくくなったり、空気の循環に影響を及ぼしたりする可能性があるため、操作性や換気計画とのバランスを考慮した上で、対策する必要があります。
●防音ドアを使用する
空間の防音性を確保する方法の一つが、防音用に設計された専用のドアを採用することです。防音ドアは一般的なドアに比べて高い気密性を備えており、音の透過を抑える特殊な構造や素材が用いられています。
例えばDAIKENの『防音ドア[SF(スチール・不燃)タイプ]』は、大型の気密パッキンやローラーハンドルを採用し、高い気密性を実現しています。またドア内部には特殊制震材やグラスウールを使用し、音の透過を軽減する構造になっています。不燃仕様のため防火性にも優れており、安全性と快適性を両立できるのが特徴です。特注対応によりバリアフリー化もできるため、医療施設や教育施設、スタジオなど幅広い施設に導入可能です。
設計段階でこうした防音ドアを取り入れることで、より高い防音性を実現できます。
ドアの防音対策を計画する際のポイント
ここでは、ドアの防音対策を計画する際に押さえたいポイントを解説します。ドア以外も含めた室内環境全体を考慮することで、バランスの良い音環境を目指しましょう。
●壁や床、天井の防音対策とセットで計画する
空間の防音性を高めるために、ドアは優先的に対策すべき部分です。音はドアや窓などの大きな開口部から漏れることが多いため、設計の初期段階で重要項目として扱うのが望ましいでしょう。
とはいえ、ドアの防音性だけ高くても、壁や床、天井などに隙間が空いていては、十分な防音対策にはなりません。壁を通して隣室の音が聞こえたり、天井や床を伝って上階の足音が響いたりと、音の侵入経路は多岐にわたります。
そのため、ドアを優先的に考えながらも、壁や床、天井など空間全体で防音性を高めることが効果的な防音対策につながります。
●遮音と吸音のバランスを考慮する
防音対策では、「遮音」と「吸音」のバランスを意識することが重要です。
遮音は隙間を埋めたり、音の透過を防いだりすることで音漏れを抑える手法です。しかし、遮音に偏りすぎると室内で音が反響しやすくなり、会話がしづらくなるなど快適性が損なわれるおそれがあります。そのため、音の反射を抑えて聞き取りやすさを向上させる「吸音」をバランス良く組み合わせることが、防音性と快適性の両立には欠かせません。
なお、防音対策のポイントは施設や用途によって異なります。施設・用途ごとの防音対策のポイントが気になる方は、下記の記事を併せてご確認ください。
⇒「オフィスで防音対策が必要な理由は?音問題の原因と対処方法」
⇒「ホテルでの防音対策|対処すべき音の種類と設計時のポイント」
⇒「病院において「防音」はなぜ重要?設計時に取り入れたい対策」
⇒「会議室の防音対策|音漏れや反響の原因と設計時に取り入れたい対策」
ドアを中心に空間全体で防音性を高めよう
ドアは役割上、音漏れの原因になりやすく、設計段階での防音対策が求められます。ドアの防音性を高めるには、隙間の処理や防音ドアの採用が効果的です。また、ドアを中心に、壁・床・天井との一体的な対策も重要な視点です。音漏れを防ぐ遮音だけでなく、音の響きを抑える吸音とのバランスも重要で、かつ用途に応じた適切な設計が求められます。空間全体を見据えた防音設計により、快適で機能的な環境をつくりましょう。
DAIKENでは防音対策に役立つ資料をご用意していますので、気になる方はぜひご請求ください。
防音対策のお役立ち資料「2025-26サウンドデザイン」を資料請求する
また建築士や設計関係者向けの会員制情報サイト『D-TAIL』では、施設設計や建材選びに役立つさまざまな情報を掲載しています。会員登録の上、日々の業務にお役立てください。
おすすめ製品