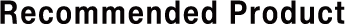インクルーシブとは ダイバーシティ&インクルージョンとの違いと実現を支える環境づくり

近年注目されている、「インクルーシブ」という言葉をご存じでしょうか。
教育業界では「インクルーシブ教育」、企業では「ダイバーシティ&インクルージョン」や「DEI」という言葉も登場しています。これらの言葉は、いずれも個々人が持つ多様な要素や属性の違いを互いに認め、共生していくという意味を持っています。
本記事では、インクルーシブやインクルーシブ社会、ダイバーシティ&インクルージョンの概念を解説します。また、インクルーシブな環境を作るにはどのような点に配慮すべきかについてもご紹介します。
実現すべきインクルーシブ社会とは
インクルーシブの意味は、「すべてを包括する、包みこむ」ことです。
障がいの有無や性別、性的嗜好、人種など、私たちには同じ人間であっても様々な違いがあります。このような違いを認め合い、すべての人がお互いの人権と尊厳を尊重し合いながら生きていく社会をインクルーシブ社会といいます。共生社会と呼ばれることもあります。
インクルーシブ社会では、自分の属性によって周りから排除されることがありません。どのような人も社会の構成員として、支え合いながら共に生き生きと暮らせる、それがインクルーシブ社会のあるべき姿なのです。
このような社会では、障がいのある方もただサポートされるだけの存在ではありません。例えば、足が不自由でも車椅子があれば散歩や買い物、スポーツもできます。環境が整っていれば、能力を十分発揮することができるのです。
しかし、もし街のあちこちに段差があったらどうでしょうか。車椅子を使っている人は移動が困難になり、学校や職場へ行くのが非常に難しくなります。また、「普通の人とは違うからこんなことはできないだろう」という周囲の気持ちが、障がいのある方を社会から排除してしまうこともあるでしょう。
障がいの原因が本人の心や体ではなく、社会にあるという捉え方を「障がいの社会モデル」といいます。インクルーシブ社会を実現するには、周りの人が障がいのある方の社会参加を阻むバリア(障壁)に気づき、それを取り除いていくことが重要です。
バリアを取り除くことを「バリアフリー」といいますが、バリアフリーは物理面だけでなく気持ちの面でも大切です。インクルーシブ社会を実現するためには差別をやめ、他人に寄り添い、「心のバリアフリー」を実行していく必要があります。
インクルーシブの意味とダイバーシティ&インクルージョン

インクルーシブという言葉は、様々な分野で使われています。
例えば、障がいのある方や外国籍の方なども含め、様々な背景を持つ人にもわかりやすいデザインが「インクルーシブデザイン」です。
学校などの教育現場では、インクルーシブ教育という言葉が使われています。これは障がいのある子も障がいのない子も、同じ環境の中で共に学び合う教育のことです。インクルーシブ教育の実践には、誰でも自分らしく学べるような合理的配慮や環境整備が必要となります。
インクルーシブと似た意味で「ダイバーシティ&インクルージョン」という言葉があります。
「ダイバーシティ」は「多様性」のことです。ある組織に多様な個性、背景を持つ人が受け入れられ、存在していることをダイバーシティと表現します。インクルーシブ教育と同様に、単純に多様性のある環境があればよいわけではありません。
そこで、ダイバーシティにインクルージョン(インクルーシブの名詞形)を加えた「ダイバーシティ&インクルージョン」や、そこにエクイティ(公平性)を加えたDEIという言葉が使われるようになりました。これにより、多様な人たちを受け入れ、それぞれが能力を発揮することのできる「お互いを尊重し、ともに活動する」という意味になります。様々な違いを持った人たちが、個性を発揮して組織の一員として活躍することを指した言葉です。
インクルーシブ教育やダイバーシティ&インクルージョンを実践することが、インクルーシブ社会の実現につながるのです。
下記記事にて「DEI」について詳しくまとめていますので、ぜひご参照ください。
⇒「DEIとは? 企業のオフィスでダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンを推進!」
インクルーシブ社会を実現するための施設環境づくり

インクルーシブとはすべての人々を取り残さず、その人権や尊厳に配慮する尊い理念です。しかし、いくら理念自体が崇高であっても、実現するための条件が整っていなければ実践はできません。誰もが属性に関わらず活躍できる場所づくりには、環境整備が不可欠で、日常的にインクルーシブを実践するインクルーシブ社会の実現のためには特定の人の「障がい」となる物理的な問題を取り除く具体的なアイディアが必要です。
ここでは参考として、オフィス、学校施設、共生型福祉施設の3施設の環境改善例をあげていきます。
●オフィス
日々ダイバーシティ化が進んでいる職場環境においてはインクルーシブな「空間」作りが効果的です。例えば、多言語対応が求められている場合は、聞き間違いによるトラブルを避けるためにも、声が聞き取りやすい空間づくりが求められます。
コミュニケーションを取りやすい環境づくりのため、音の反響を抑える吸音性能のある天井材や壁材の導入を検討するのもよいでしょう。
インクルーシブな職場環境を整備するための具体的なステップについては、以下の記事で解説しています。ぜひ、ご一読ください。
⇒「インクルーシブな職場を目指して 多様性を尊重した職場環境」
●学校施設
インクルーシブ教育を実現するには、学校施設における設備面でのサポートも必要です。
障がいのある方にとっても学びやすい環境であるために、例えば「車いすで教室の出入りがしやすいか」に焦点をあててみるのはどうでしょうか? 具体的な対策としては、段差をなくしてスロープを設置したり、少しの力で開け閉めがしやすい室内ドアを採用するといった方法が考えられます。
-
―インクルーシブ教育に関する記事―
・「インクルーシブ教育実現のために 学習環境に求められるバリアフリー化とは」
・「インクルーシブ保育とは? 多様性を知り、子どもの自発性を育てる教育」
●共生型福祉施設
東北大震災を契機として、高齢者のみならず子ども、障がい者、地域住民が一緒に利用する共生型福祉施設の設置が推進されるようになりました。開かれた高齢者施設は地域交流の役割を担うことが期待されます。様々な属性の人が集う施設ではインクルーシブ環境の整備が求められます。例えば、足元が不安定な子どもや高齢者が滑りにくい床建材選びなども重要になってくるでしょう。
こちらの記事では、高齢者施設でインクルージョンを実現するためのヒントを紹介していますので参考にしてください。
⇒「高齢者施設におけるインクルーシブデザイン ノーマライゼーションの違いとは?」
災害、非常時に備える「インクルーシブ防災」とは

インクルーシブな環境作りを目指すには、日常生活だけでなく災害や非常時に「すべての人が安全に避難し、避難生活を送れるかどうか」を様々な側面から検討することも大変重要になります。
このような、誰も取り残さない防災の考え方を「インクルーシブ防災」といいます。
非常時には避難経路ががれきなどで塞がったり、道に亀裂が入って歩くのが困難になる場合もあります。そのような中で、足腰が不自由な高齢者や車いすに乗った障がい者などはどうしても避難行動が遅れてしまいがちです。実際に東北大震災における岩手、宮城、福島の3県で、高齢者(60歳以上)死亡率は約65%以上と高い数値を記録しており、また障がい者の死亡率は一般的な死亡率の約2倍近くに達しています。
そのため、インクルーシブ防災の配慮として、避難所開設の時点で必要なスペースを確保していくことが大切です。例えば、通路に関しては車いすがスムーズに移動できるような幅を確保しておくなど、いざというときに高齢者や障がい者の逃げ遅れを防ぐことはもちろん、避難後の生活が困難にならないような配慮が求められます。
今後は、より様々な施設においてインクルーシブ社会を実現するための環境づくりが求められることになるでしょう。それぞれの施設において、すべての人々が共生できるよう、インクルーシブ防災やインクルーシブデザインにも配慮した設計・環境改善を心がけていくことが大切です。
-
―インクルーシブ防災に関連する記事―
・「インクルーシブな商業施設づくり 誰ひとり取り残さないインクルーシブ防災を目指して」
―インクルーシブ防災に関連する記事―
・「インクルーシブデザインの意味とは ユニバーサルデザインとの違いとピクトグラム活用」
公開日:2022.10.11 最終更新日:2024.02.05
おすすめ製品