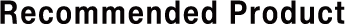建築基準法における内装制限とは?対象となる建築物や緩和の要件

建築設計を行う上で避けて通れないのが「内装制限」です。内装制限は、基準や緩和条件が非常に複雑で、設計や建材選びに困っているという建築士の方も多いのではないでしょうか。内装の仕様が建設コストに与える影響は大きいため、コストを抑えるためには基準だけでなく、緩和条件を正しく理解する必要があります。
本記事では、内装制限の概要や、2020年の法改正による緩和、2025年に予定されている法改正について解説します。
建築基準法における内装制限とは
内装制限とは、建物の内部で火災が発生した際に人々が安全に避難できるようにするための基準です。内装材への延焼や有害なガスなどの発生を防ぎ、避難経路が妨げられないようにすることが意図されています。
内装制限については、建築基準法第35条の2「特殊建築物等の内装」や消防法などで基準が定められています。内装制限に違反すると、建築主や建築士が懲役もしくは罰金のペナルティーを受けることを留意しておきましょう。建築主が内装制限違反を知りながら設計を指示したときは建築主が、建築主から指示がないままに建築士が内装制限に違反する設計を行った場合は建築士がペナルティーを受けるのが一般的です。
参考:「建築基準法第三十五条の二」(e-gov 法令検索)
内装制限の対象となる建築物
ここでは、内装制限を受ける建築物について解説します。対象となるのは、大きく分けて「特殊建築物」「大規模建築物」「火気使用室」「無窓居室」の4種類です。それぞれについてみていきましょう。
●特殊建築物
特殊建築物として内装制限の対象になる建築物とその内容は、以下のとおりです。
建物用途 |
制限を受ける建物の規模 |
内装制限 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
耐火建築物など |
準耐火建築物など |
その他の建築物 |
居室 |
通路 |
||
①劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など |
客室の床面積の合計が400m²以上 |
客室の床面積の合計が100m²以上 |
客室の床面積の合計が100m²以上 |
※壁・天井:難燃以上 |
壁・天井:準不燃以上 |
|
②病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、協同住宅、寄宿舎など |
当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300m²以上 |
当該用途に供する2階以上の部分の床面積の合計が300m²以上 |
当該用途に供する部分の床面積の合計が200m²以上 |
※壁・天井: |
壁・天井: |
|
③百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場など |
当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が1,000m²以上 |
当該用途に供する2階以上の部分の床面積の合計が500m²以上 |
当該用途に供する部分の床面積の合計が200m²以上 |
※壁・天井:難燃以上 |
壁・天井:準不燃以上 |
|
④自動車車庫、自動車修理工場など |
規模不問 |
規模不問 |
規模不問 |
壁・天井:準不燃以上 |
壁・天井:準不燃以上 |
|
①②③の用途に供する特殊建築物に設ける地階、地下工作物内の居室 |
規模不問 |
規模不問 |
規模不問 |
壁・天井:準不燃以上 |
壁・天井:準不燃以上 |
|
※①②③の「居室」については、下記の条件があります。
・壁:床面上1.2m以下を除く
・天井:3階以上の居室は準不燃以上
その他にも、対象となる部分、対象とならない部分が細かく定められています。設計を行う際は、最新の法令集などで必ず確認するようにしましょう。
●大規模建築物
大規模建築物として内装制限の対象になる建築物とその内容は、以下のとおりです。
【対象となる建築物】
・3階以上かつ延べ面積が500m²を越える建築物
・2階建てで延べ面積が1,000m²を越える建築物
・1階建てで延べ面積が3,000m²を越える建築物
【内装制限】
・居室の壁:難燃以上(床面上1.2m以下を除く)
・居室の天井:難燃以上(3階以上の居室は準不燃以上)
・通路の壁:準不燃以上
・通路の天井:準不燃以上
●火気使用室
火気使用室として内装制限の対象になる居室とその内容は、以下のとおりです。
【対象となる居室】
・住宅(事務所、店舗兼用を含む):
かまど、こんろなどの火気を使用する調理室、浴室など(耐火建築物および最上階を除く)
・住宅以外:
かまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関などの火を使用する設備などを設けた調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室など
【内装制限】
・居室の壁:準不燃以上
・居室の天井:準不燃以上
●無窓居室(むそうきょしつ)
無窓居室として内装制限の対象になる居室とその内容は、以下のとおりです。
【対象となる居室】
・下記のすべてに当てはまる居室(天井の高さが6mを越えるものを除く)
①床面積が50m²を越える
②開口部の開放できる部分(天井または天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る)の面積が居室の床面積の1/50未満
・温湿度調整を必要とする作業を行う作業室などで、下記のいずれかに当てはまる居室
①採光に有効な開口部の面積が、居室の床面積の1/7に満たない住宅の居室
②採光に有効な開口部の面積が、居室の床面積の1/5~1/10までの間において政令が定める割合に満たない病院・診療所・寄宿舎・下宿などの居室
【内装制限】
・居室の壁:準不燃以上
・居室の天井:準不燃以上
参考:
「建築基準法制度概要集」(国土交通省)
「建築基準法第三十五条の二」(e-gov 法令検索)
「建築基準法第三十五条の三」(e-gov 法令検索)
「建築基準法施行令第二十八条」(e-gov 法令検索)
「建築基準法施行令第百二十八条の四」(e-gov 法令検索)
「内装制限について」(一般社団法人日本壁装協会)
内装制限の範囲に使用する「防火材料」とは
内装制限が適用される部分には、指定の防火材料を使用する必要があります。ここでは防火材料の概要や種類について解説します。
●防火材料とは
防火材料とは、「不燃」「準不燃」「難燃」の性能に区分して国土交通大臣が定めた、もしくは認定した材料です。
建築基準法第108条の2で定められている防火材料の主な要件は、以下のとおりです。
・燃焼しないものであること
・防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること
・避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること(外部の仕上げに用いるものは除く)
参考:「建築基準法第百八条の二」(e-gov 法令検索)
●防火材料の種類
防火材料は、上述した基準の要件を満たす時間に応じて「不燃」「準不燃」「難燃」という3つの区分に分けられます。
●不燃材料
不燃材料は、加熱開始後20分間、要件を満たす材料です。具体的にはコンクリート・瓦・陶磁器質タイル・繊維強化セメント板・ガラス・石・石膏ボード(厚さ12mm以上、ボード用原紙の厚さが0.6mm以下)・ロックウールなどが挙げられます。
DAIKENでは、熱・水・汚れに強い不燃壁材や上質なデザインが魅力の不燃天井材を揃えた『グラビオ』シリーズ、軽量・防耐火・高耐久・省施工などの性能を備えた「ダイライト軒天井材」を用意しています。
参考:「建設省告示第1400号 不燃材料を定める件」(国土交通省)
●準不燃材料
準不燃材料は、加熱開始後10分間、要件を満たす材料です。具体的には、石膏ボード(厚さが9mm以上、ボード用原紙の厚さが0.6mm以下)・木毛セメント板(厚さ15mm以上)・硬質木片パネル(厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上)・木片セメント板(厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上)・パルプセメント板(厚さ6mm以上)などが挙げられます。
DAIKENでは、カラフルな色使いが特徴の準不燃天井材『パステルトーン』が人気の商品です。
参考:「建設省告示第1401号 準不燃材料を定める件」(国土交通省)
●難燃材料
難燃材料は、加熱開始後5分間、要件を満たす材料です。具体的には、石膏ボード(厚さ7mm以上、ボード用原紙の厚さが0.5mm以下)・難燃合板(厚さ5.5mm以上)などが挙げられます。
参考:
「建設省告示第1401号 難燃材料を定める件」(国土交通省)
「建築基準法制度概要集」(国土交通省)
内装制限の緩和要件
2020年の法改正にて内装制限が一部緩和されました。非常に複雑なため、ここでは一部の内容を簡単に紹介します。
●2020年の改正による緩和の要件とは
2020年の法改正による内装制限の緩和で、一定の条件を満たせば内装制限が適用される部分についても防火材料を使用しなくてもよい可能性があります。
以下に示すのは、緩和を適用できるケースの一例です。
【緩和を適用できる例】
以下のすべてを満たす場合に、内装制限の緩和を受けられます。
・一定規模以上の特殊建築物もしくは大規模建築物である(「内装制限の対象となる建築物」を参照)
・特殊建築物のうち、劇場・映画館・演芸場、観覧場・公会堂・集会場等、および、病院・診療所・児童福祉施設等に当てはまらない
・居室部分がそれ以外の部分と間仕切り壁もしくは防火設備で区画されている
・床面積が100m²以内、天井の高さが3m以上の区画された居室である
・避難経路を含まない居室である
ここでは一例を紹介していますが、実際の条件や内容は非常に複雑です。実務で緩和を取り入れる場合は、最新の法令集などで確認するようにしましょう。
参考:
「国土交通省告示第251号」(国土交通省)
「東京都建築安全条例の見直しの考え方(案)」(東京都都市整備局)
●2025年の改正建築基準法における変更点
2025年には、「大規模建築物における防火規定変更」が盛り込まれる建築基準法の改正が予定されています。内装制限に関する主な要点は、以下のとおりです。
・3000m²超の大規模建築物の木造化の促進
【現行】
3000m²超の大規模建築物を木造とする場合、壁や柱等を耐火構造(※)とするか、3000m²毎に耐火構造体で区画する。
※耐火構造:壁や床などが一定の耐火性能(通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊および延焼を防止するために必要な性能)を備えた構造。
【改正後】
構造部材の木材をそのまま見せる「あらわし」による設計が可能な新たな構造方法を導入する。ただし、火災時に周囲に大規模な危害が及ぶことを防止できるのが条件である。
・階数に応じて要求される耐火性能基準の合理化
【現行】
耐火構造の要求性能は、階数に応じて規定されているが、階数5の建築物と階数14の建築物の最下層に関して同水準の耐火性能を要求するなど、きめ細かな基準にはなっていない。
【改正後】
木造による耐火設計ニーズの高い中層建築物に適用する耐火性能基準を合理化する。階数によっては現状の規制よりも緩和される。
・大規模建築物における部分的な木造化の促進
【現行】
耐火性能が要求される大規模建築物は、壁や柱などの全ての構造部材に耐火構造を求められる。
【改正後】
耐火性能が要求される大規模建築物においても、壁・床で防火上区画された範囲内で部分的な木造化を可能とする。
・防火規定上の別棟扱いの導入
【現行】
耐火性能が要求される大規模建築物は、低層部分にも高層部分と同様の耐火性能が求められる。
【改正後】
延焼を遮断する高い耐火性能の壁を設置するなどの措置を取ることで、高層部と低層部を防火規定上の別棟として扱い、低層部分の木造化を可能とする。
・防火壁の設置範囲の合理化
【現行】
木造部分と一体で耐火構造や準耐火構造(※)の部分を計画する場合、耐火・準耐火構造部分にも1,000m²ごとに防火壁の設置が求められる。
※準耐火構造:壁や床などが一定の耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために必要な性能)を備えた構造。
【改正後】
他の部分と防火壁で区画された1000m²超の耐火・準耐火構造部分には、防火壁の設置を求めない。
参考:「改正建築基準法について」(国土交通省)
内装制限を遵守した設計を
内装制限の基準は非常に複雑で、建物の用途・規模、部屋の特性や緩和条件、法改正における変更など、多くの内容を確認しなければいけません。また、内装制限の理解を誤り、法適合のための仕様変更が生じると、イニシャルコストの増額、調達スケジュールの調整といった問題が発生します。スムーズにプロジェクトを進めるためにも、必要に応じて建築主事に確認しながら設計を進めるようにしましょう。
DAIKENでは内装制限に適合する壁・天井などの建材をカタログにまとめています。お気軽にご請求ください。
「不燃建材カタログ 2024-25」を資料請求する
また、施設設計・建材選びに役立つプロ向け情報サイト『D-TAIL』では、設計やプレゼンテーションに役立つ情報を提供しています。建材選びの課題解決にお役立てください。
●本記事に関連する商品
・不燃壁材、不燃造作材
・不燃天井材(施設向け)
・ダイライト軒天井材
・パステルトーン
おすすめ製品