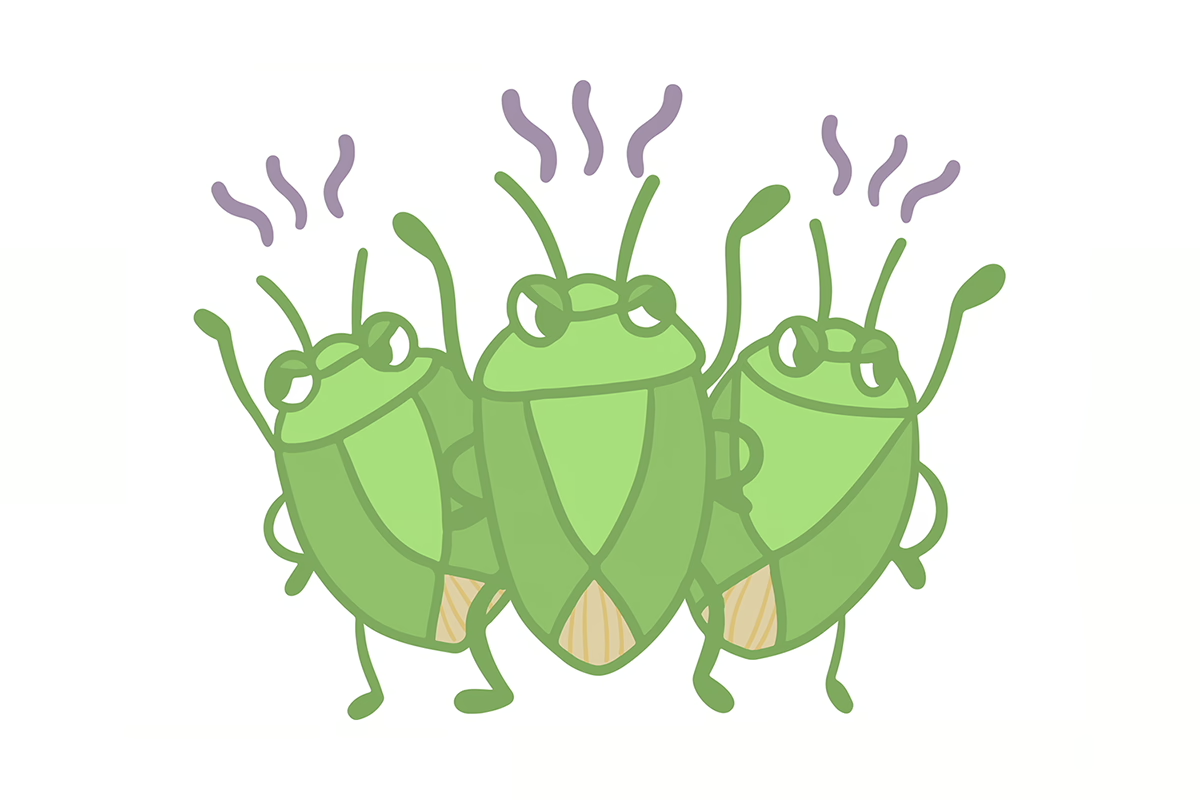住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。
家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
目次
秋の夜空に浮かぶ満月は静けさと美しさを感じさせ、心を癒してくれるものです。
特に十五夜に昇る“中秋の名月”のお月見は古くから親しまれてきた季節のイベントです。今回は自宅でお月見を楽しみたいという方に向け、中秋の名月の意味や由来、家族で楽しむための環境づくりについて解説します。
十五夜のお月見“中秋の名月”とはいつのこと?
「十五夜のお月見はいつなの?」とすぐ知りたい方のために、さっそくですが、2025年から5年間の中秋の名月にあたる日付をご紹介しましょう。
十五夜(中秋の名月)の日付一覧
2025年10月6日(月)
2026年9月25日(金)
2027年9月15日(水)
2028年10月3日(火)
2029年9月22日(土)
上記の中秋の名月の日付を見て、「どうして毎年日付が違うの?」と疑問に思う方もいることでしょう。
その理由は、中秋の名月が“旧暦”で決められているからです。
旧暦(太陰太陽暦)とは
旧暦は、1872(明治5)年まで日本で使われていた暦です。月の満ち欠けと太陽の動きをもとにつくられたもので、太陰太陽暦ともいわれています。1か月は29~30日になります。
新暦(グレゴリオ暦・太陽暦)とは
新暦はグレゴリオ暦ともいわれる、現在私たちが使用している暦です。太陽の動きをもとにつくられたもので、太陽暦ともいわれています。日本では1873(明治6)年から採用されました。
日付がずれる理由 旧暦では1年に13か月の月もあった!?
新暦は1年が365日で、地球の公転周期と暦のズレを調整するため、4年に1度366日となる閏(うるう)年があります。
一方、旧暦は1年が354日しかなく、地球の公転周期と比べて1年で約11日のズレが生じます。その調整のために2~3年に1度閏月が入り、1年が13か月になる年がありました。
十五夜は、この旧暦を基準としているため現在の新暦とはズレがあり、毎年日付が変わるというわけです。
おすすめ記事
2025.06.23
そもそも中秋の名月って何?
“中秋の名月”という言葉はよく耳にするものの、それがいつで、なぜそのように呼ばれるのかはよく知らないという方は多いかもしれません。中秋の名月とお月見イベントの由来について解説します。
中秋の名月(十五夜)の由来

旧暦の秋は7~9月を指します。その期間のちょうど真ん中にあたるということで、8月15日を“中秋”と呼んでいました。また新月から満月になるのに約15日かかるので、月の満ち欠けを基準とする旧暦を使っていた時代には、毎月15日の夜、つまり十五夜はほぼ満月でした。
年に12回やってくる十五夜のうち、月がもっとも美しく見えるとされたのは8月の十五夜であったことから、8月15日の月には“中秋の名月”と特別な名が付けられ、尊ばれるようになったのです。
中秋の名月は、新暦では9月~10月にやってきます。現在の中秋の名月は必ずしも満月ではありませんが、澄んだ夜空に浮かぶ月の風情を楽しみましょう。
ちなみに現在では、“お月見” “十五夜” “中秋の名月”はすべて同義語として使用されることが多いようです。そのため、“十五夜”といった場合は“中秋の名月”のことを指していることがほとんどです。
日本で愛される十五夜のお月見

十五夜にお月見をする習慣は、平安時代に中国から日本の貴族社会に伝わったとされています。当時は月を眺めながら、お酒を飲んだり楽器を演奏したりして宴を楽しんでいたそうです。
江戸時代に入ると、庶民にも十五夜の風習が伝わります。ただ、庶民にとっては「宴を楽しむ」というよりは「感謝の気持ちを共有する」という意味合いが強かったようです。特に中秋の名月は稲の収穫時期に近かったため、収穫祭や初穂祭として位置付けられました。また、江戸時代以前は里芋をお供えしていたため、十五夜は“芋名月”ともいわれていました。
人々は月を見上げ、月にお芋をお供えしながら豊作や家族の健康を祈ったのでしょう。
十三夜って何?
十五夜は有名ですが、そのほかに“十三夜”という日本独自の風習があることはご存じでしょうか。
十五夜が収穫前に豊作を祈る風習であることに対し、その約1か月後にあたる旧暦9月13日の十三夜は収穫後に豊作を感謝する風習です。十三夜は月見団子に加えてその時期に収穫される豆や栗をお供えすることから、 “豆名月”や “栗名月”ともいわれています。
十三夜は十五夜に次いで月が美しく見える日とされ、十三夜を“後の月(のちのつき)”、十五夜と十三夜を合わせて“二夜の月(ふたよのつき)”と呼び、どちらか片方だけ見るのは“片月見(かたつきみ)”もしくは“片見月(かたみづき)”といって縁起が悪いとされていたこともあるようです。ただ、現在においてそのようなことを気にする必要はありませんので、十五夜と同様に、十三夜もお月見を楽しんでみてはいかがでしょうか。
十三夜の日付一覧
2025年11月2日(日)
2026年10月23日(金)
2027年10月12日(火)
2028年10月30日(月)
2029年10月20日(土)
お月見に必要なもの

現代でも秋の美しい月は私たちの心を癒してくれます。ただ月を眺めるだけでなく、古くからの風習にちなんだ飾り付けやお供え物を準備すれば、よりお月見の風情を楽しめそうです。では、お月見に欠かせないものにはどのような意味があるのでしょうか。
月
月を見る風習は縄文時代からあったとされます。日本神話では月の神様、夜の神様として登場する月読命(つくよみのみこと)が農耕の神様としても崇められていたことから、収穫前に豊作を祈願してお供えをするようになったといわれています。
現在の日本の秋は、大陸から移動してくる高気圧の影響で大気中の水蒸気や塵の量が少なくなる傾向にあります。そのため、空気が澄んでいることも多く、夜空に浮かぶ月はより一層美しく見えます。
お月見の際、天気次第で月が見えないこともありますが、昔の人は雲に隠れて見えない月を“無月”、雨で見えない月を“雨月”と呼びました。見えない月を愛でるのも風流です。
月見団子
お供え物として江戸時代から親しまれているのが、月に見立てた丸い月見団子です。気持ちを月まで届けたいという思いから、十五夜に際して15個の団子を積み上げる風習もあります。お団子のほか、旬の野菜・果物などがお供えされることもあります。
なお、江戸時代以前は里芋をお供えしていたこともあり、月見団子は里芋を模したものともいわれています。
また古くからの風習というわけではありませんが、お月見に際して月見そばを楽しむご家庭もあるようです。
ススキ
ススキは、月の神様が降りてくる依り代(よりしろ)になるともいわれており、お米が豊作であるようにという祈りのこもったお供えです。できれば稲穂を使いたいところですが、十五夜の時期は稲刈り前のため、稲穂の代わりに形がよく似たススキを使うようになりました。
今でもススキは秋を代表する植物として親しまれています。月見団子と並べることで、よりお月見の雰囲気が高まり、風情ある空間を演出できるでしょう。
お月見を家族で楽しむ季節イベントに!

家族で一緒に楽しむイベントが少ないと感じている方は、ぜひこの機会にお月見を毎年恒例の季節イベントとして取り入れてみてはいかがでしょうか。
家族で自然を観察する時間として
前述のとおり、江戸時代から庶民の間でも楽しまれてきたお月見は、家族や仲間に感謝する気持ちが込められています。お月見の由来を知ることが、家族や友人、自然への感謝を再認識するきっかけになるかもしれません。また、お子様が月の満ち欠けや星空について学ぶよい機会にもなりそうです。
お団子づくり
市販のお団子を用意するのもよいですが、家族で一緒に月見団子を手づくりするのも楽しい時間になるでしょう。月見団子は、だんご粉や上新粉、白玉粉などを使えば簡単につくることができます。イベントとして楽しめ、家族が一緒に伝統に触れる良い機会として充実した時間を過ごせるでしょう。
お月見をイベントとして家族で楽しむ
ススキを生けたり、折り紙でうさぎや月を作って飾り付けたりするのも、お子様にとって楽しい時間になります。お月見を満喫できる雰囲気も高まり、思い出に残るイベントになることでしょう。
おすすめ記事
2025.07.07
お月見を楽しむ環境づくり

(※)写真はイメージです。弊社製品ではございません。
お月見はどこで行うのがよいでしょうか。お月見を楽しむには、月をゆっくり眺められるベランダやバルコニー、屋上などが人気です。特に、東から南の方角が開けた場所を選ぶと月を長く楽しめます。
屋内と屋外をつなぐ縁側は、月を眺めるのにぴったりの空間です。
縁側には種類があり、建物の外側にあるものを“濡れ縁(外縁)”、建物の内側にあるものを“内縁”、内縁の中でも建物に対して平行に板を張る形式は“くれ縁”と呼びます。また、広めの縁側を“広縁”、狭い縁側を“狭縁”といいます。
内縁であれば天候に関係なくお月見が楽しめますので、家族との思い出づくりの場に縁側がほしいと考えている方にもおすすめです。
縁側は、リビングとはまた一味違った家族団らんの時間を過ごせる場です。
なお、9月や10月はまだまだ虫の多い季節です。内縁なら問題ありませんが、濡れ縁でお月見をする場合は、虫よけスプレーや蚊取り線香の準備もお忘れなく。
関連記事⇒「縁側の魅力とは メリット・注意点を踏まえて美しい空間をつくろう」
虫は光によって来ることが多いので、対策を忘れずに。
関連記事⇒「カメムシが大量発生! 自宅に寄ってくる原因と寄せ付けないための対策 駆除方法もチェック!」
家族の思い出づくりに縁側を! DAIKEN『タフアートえんこうエコ』

お月見や庭鑑賞をする際に雰囲気を盛り上げてくれる縁側ですが、DAIKENでは内縁として使用できる建材も展開しています。
『タフアートえんこうエコ』は、傷や凹み傷が付きにくい和風床材で、色のばらつきはほとんどない安定した張り上がりが特長です。桧板目柄では木目柄のレイアウトをバランスよく配置し、シート化粧でありながら、自然な張り上がりを表現しています。
和風・和モダンな家づくりでは、空間演出のベース素材として活用できます。なお屋外での使用は想定されていないため、縁側として使う際は屋内空間で使用してください。家族団らんのスペースにしたい場合は広縁にするのがおすすめです。
まとめ
中秋の名月に楽しむお月見は、自然の美しさを感じながら家族や仲間とのつながりを深める伝統的な風習です。家族で月見団子やススキなどを用意して絶好のロケーションで楽しむお月見は、家族にとってきっとかけがえのない思い出になることでしょう。
家づくりにおいて縁側を設置すれば、お月見をはじめとした季節のイベントを楽しみやすくなります。季節ごとに趣の異なる自然を身近に感じながら暮らしたいという方は、縁側を取り入れた暮らしについて検討してみてはいかがでしょうか。

-
監修者
志鎌のり子(しかまのりこ)
一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。
保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など
関連製品
-
傷や凹みが付きにくい和風床材
おすすめ記事Recommends
-
2025.08.20
-
2025.05.20
-
2025.07.07