住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。
家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
家や土地を探す際、〇坪、〇畳、〇m²といった単位を目にすることがあると思います。これらは建築業界や不動産業界でよく使われている広さの単位です。不動産広告や契約図面、住宅ローンの計算書など、一般の方が扱う資料にも使われていますし、フローリングや天井材などの販売単位として、「1ケース1坪入り」と表記されている商品もあります。しかし、坪、畳などの単位では広さがイメージできないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、建築・不動産で扱う広さの単位を換算する方法や、土地選び・家づくりにおける面積の目安について解説します。理想の家に必要な土地や、家の広さを知りたいという方は、ぜひ参考にしてください。
1坪の大きさはどれぐらい? 建築・不動産で扱う広さの単位
さっそく建築・不動産で扱う広さの単位をみていきましょう。
坪、平米(m²)、畳(地域で大きさが異なる)の違い
日本の建築で昔から使われてきた坪、畳という広さの単位は、尺貫法と呼ばれる単位系をもとにしています。尺貫法は長さに尺、質量(重さ)に貫、体積に升という単位を使い、昔は買い物など、日常生活の中でも使われていました。現代では主に建築や不動産の分野で使用されています。
尺貫法について詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事をご参照ください。
関連記事⇒「尺貫法とは? 間、尺、寸の長さはどれぐらい? 家づくりで耳にする単位をマスター!」
坪・畳の換算方法
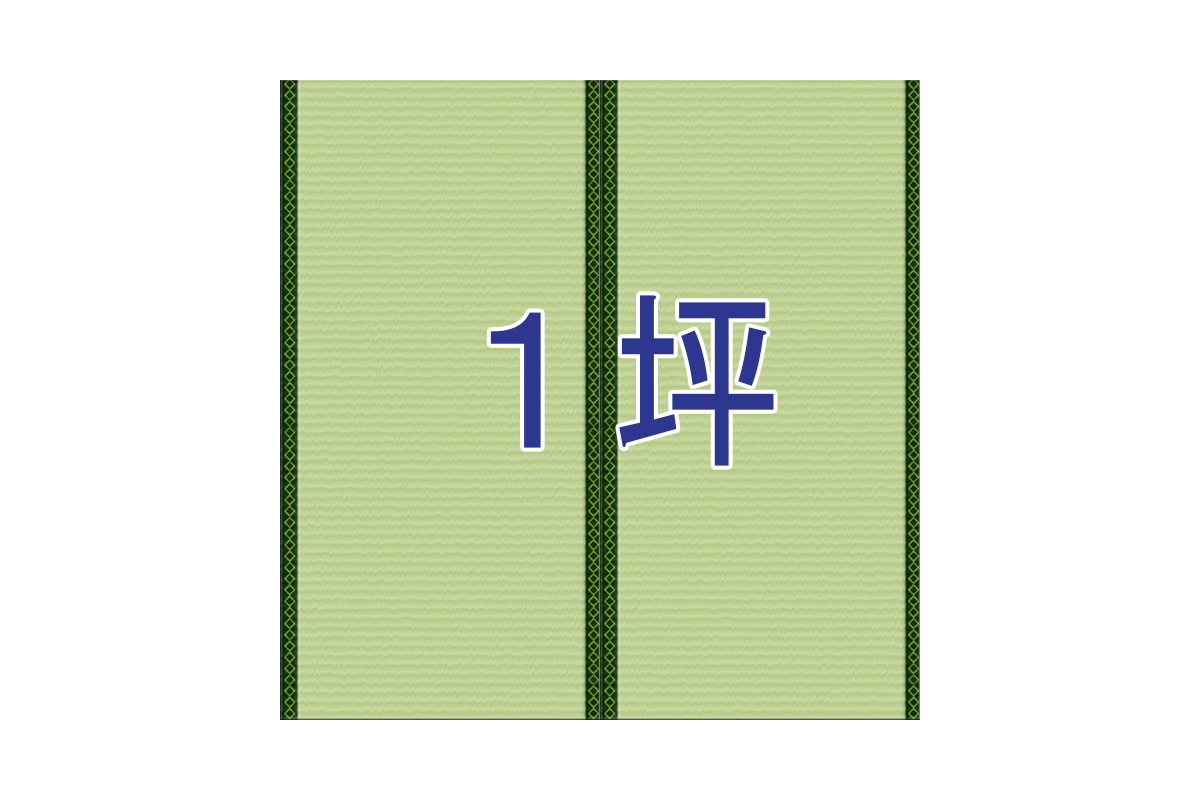
一般的には、1畳=約180cm(6尺)×約90cm(3尺)です。また、1坪は畳を2枚並べた広さ、180cm×180cm(約3.3m²)を指します。1畳は平均的な日本人がごろりと横になれる広さであり、体感に即した家を建てる際の基本にちょうど良かったのです。
ところが、1891年になると「度量衡法」が制定され、「メートル法」が正式に認められました。その後の1959年には尺貫法が廃止され、1966年にメートル法に統一されるという歴史を辿り、現在は建築・不動産以外で用いることがほとんどありません。そのため、尺貫法は多くの人にとってなじみのない単位となってしまいました。
しかし、今でも土地の価格や家の建築費用はたいてい坪単価で表記されます。面積が40坪(約132m²)で4,000万円の注文住宅なら、1坪あたりの単価は100万円(1m²あたり約30万円)ということになります。また、フローリングや天井材なども「1ケース1坪入り」といった売られ方をされることがあります。1坪=180cm×90cmの畳2枚分とイメージできれば、どれぐらいの量が入っているか想像できますね。
実をいうとこの尺貫法は、地域によって基準値が異なるという特徴があります。
同じ1畳でも、
江戸間(関東)→176cm×88cm(約1.55m²)
京間(関西)→191cm×95.5cm(約1.82m²)
と、かなりサイズが異なるため、「1坪」の広さも当然変わります。これは関西では畳に合わせて柱を建てていたのに対し、関東(江戸)では柱や壁の中心から中心を「1間」として畳を作ったため、柱の太さの分だけ畳が小さくなったという建築方法の違いによる説や、江戸幕府が年貢をたくさん取り立てるために1間の長さを縮めたという説など、同じ単位でも地域によってサイズが異なる理由には諸説あるようです。
ともあれ、家を建てる場合は1畳、1坪の正確な広さがとても重要です。齟齬が生じないようにメートル法でも確認するようにしましょう。
おすすめ記事
2025.08.20
土地選びにおける面積のポイント

家づくりや土地選びで尺貫法のほかにも知っておきたいのが建ぺい率と容積率(ようせきりつ)です。どちらも普段ほとんど耳にしない言葉ですが、土地選びや家を建てる場合には重要かつ必須の項目として知られています。
建ぺい率
建ぺい率というのは敷地面積に対する建物の建築面積(外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。わかりやすくいうと建物を真上から見たときの面積)の割合です。地域によっては建ぺい率の最大値が法律で定められていることがあり、例えば建ぺい率が50%なら土地の広さの半分まで家を建てるために使うことができます。建ぺい率の目的は、火災の際に延焼を防ぐため、敷地に空間を確保することです。
容積率
積率は敷地面積に対する建物の延べ床面積(建物の各階の床面積の合計値)の割合です。建ぺい率と違って各階の床面積を合計します。高い建物が乱立して人口が過密化するのを防ぐ目的があります。
例えば、普通の住宅地で建ぺい率が50%の場合、土地の半分しか使えないなら5階建て、10階建てにしてしまおう…と考える人が増えると、高い建物が増えて周辺の日当たりや風通しが悪くなり、電力や水道が追い付かなくなるという問題が起きかねません。容積率はその土地の用途によって決められており、容積率を超過すると建築許可がおりません。
土地が理想の家に十分な広さかということを正確に計算するには専門的な知識が必要です。土地選びの際は工務店や建築会社に相談し、建ぺい率と容積率も確認しておきましょう。
おすすめ記事
2025.08.20
家づくりにおける面積の目安

適切な家の広さは人によって様々ですが、国土交通省が「住生活基本計画(全国計画)」の中で居住面積の目安を示しているので参考にできるかもしれません。広さはm²で表記されているため、「坪」に換算する際は3で割る(あるいは0.3を掛ける)と、ざっくりと算出できます。
なお、ここでご紹介する居住面積水準は以下のように定義されています。
・最低居住面積水準…健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠の住宅の面積に関する水準
・一般型誘導居住面積水準…豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準(都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建て住宅を想定)
・都市居住型誘導居住面積水準…「一般型誘導居住面積水準」と同様(都市の中心及びその周辺における共同住宅を想定)
1人暮らし
1人暮らしの場合は以下の面積が目安です。
・最低居住面積水準:25m²
・一般型誘導居住面積水準:55m²
・都市居住型誘導居住面積水準:40m²
地域によっては条例でマンションなどのワンルームの最低面積を25m²以上にすることが定められています。趣味やリモートワークを充実させて多様なライフスタイルを実現したいなら、余裕のある居住面積が確保できる40m²を目安にするとよいかもしれません。
2人暮らし
2人暮らしの場合は以下の面積が目安です。
・最低居住面積水準:30m²
・一般型誘導居住面積水準:75m²
・都市居住型誘導居住面積水準:55m²
近年はDINKs(共働きで子どもを持たない選択をした夫婦)や、シニア世帯に向けた2LDKタイプのマンションが注目を集めています。それぞれの空間をつくってゆったりとした生活を送るのにおすすめの間取りですが、広さとしては50m²程度が目安になるでしょう。
ファミリー
ファミリーの場合は以下の面積が目安です(世帯人数は、3歳未満:0.25人、3歳以上6歳未満:0.5人、6歳以上10歳未満:0.75人として算定)。
・最低居住面積水準:10m²×世帯人数+10m²(例:4人家族なら50m²[※10歳未満の子どもがいない場合])
・一般型誘導居住面積水準:25m²×世帯人数+25m²(例:4人家族なら125m²[※10歳未満の子どもがいない場合])
・都市居住型誘導居住面積水準:20m²×世帯人数+15m²(例:4人家族なら95m²[※10歳未満の子どもがいない場合])
ファミリーの場合は人数だけでなく、子どもの成長によっても適切な広さが変わります。引っ越しを考えないのであれば広めの家を用意しておきたいところですが、出産や子どもの成長過程に合わせて住み替えを検討するのもよいかもしれません。
半畳サイズの『ここち和座』で憩いの場を

DAIKENではどんな家づくりにもマッチする床材を数多くラインアップしていますが、中でもおすすめしたいのが高機能の畳です。『ダイケン畳 健やかくん』は、和紙(※)の畳表を使用したインテリア畳で、カビの発生やダニの増殖を防ぐ抗菌性にすぐれています。変色しにくい、お手入れが簡単、傷が付きにくいなど、様々な機能も持っています。
(※)機械すき和紙を使用しています。コウゾ、ミツマタ等を使用した手すき和紙ではありません。
同じ畳表を使用している『ここち和座』も魅力的な製品です。敷き込みタイプの『ここち和座』はフローリングと同じ厚さで、施工時に下地の落とし込みが不要なためリーズナブルに和モダンな空間がつくれます。
一方、置き敷きタイプの『ここち和座』は、半畳サイズの畳風床材を組み合わせることで、くつろぎの空間を提供する製品です。ラグのようにフローリングの上に置くだけで、個性的なインテリアが簡単に演出できます。不要な時にはしまっておけますし、引っ越し時に持って行くこともできます。
豊富なバリエーションの中から自由に組み合わせて、和のテイストを取り入れた家づくりにぜひご活用ください。
まとめ
「坪」「畳」といった表現にはなじみがないかもしれませんが、家づくりや家探しの際は慣れておくと空間の広さをイメージしやすくなります。まずは「1坪=畳2枚分=約3.3m²」を覚えておくと、不動産広告などの表記を理解しやすくなるでしょう。ご自分のライフスタイルにぴったりの家には、どれぐらいの広さが必要なのか考えるきっかけにしてください。

-
監修者
淀川 美和(よどがわ みわ)
株式会社アートアーク一級建築士事務所代表。一級建築士、インテリアコーディネーター、2児のママ建築家。「ママをきれいにする空間づくり」 をミッションの一つに掲げ、住宅・店舗・ホテル等の設計、内装コーディネート、メディア出演等を行う。自身も仕事と家事と育児のバランスをとりながら、忙しいママがいかに快適に家族と暮らせるかに焦点をあてつつ「お部屋のコンシェルジュ」として皆さまのお役に立てるよう奮闘中。
保有資格:一級建築士、インテリアコーディネーター、建築士会インスペクター、健康住宅アドバイザー、整理収納アドバイザー2級、アロマ検定1級
関連製品
-
簡単にくつろぎスペースをつくる置き畳
おすすめ記事Recommends
-
2025.09.19
-
2025.08.20
-
2025.09.19
























