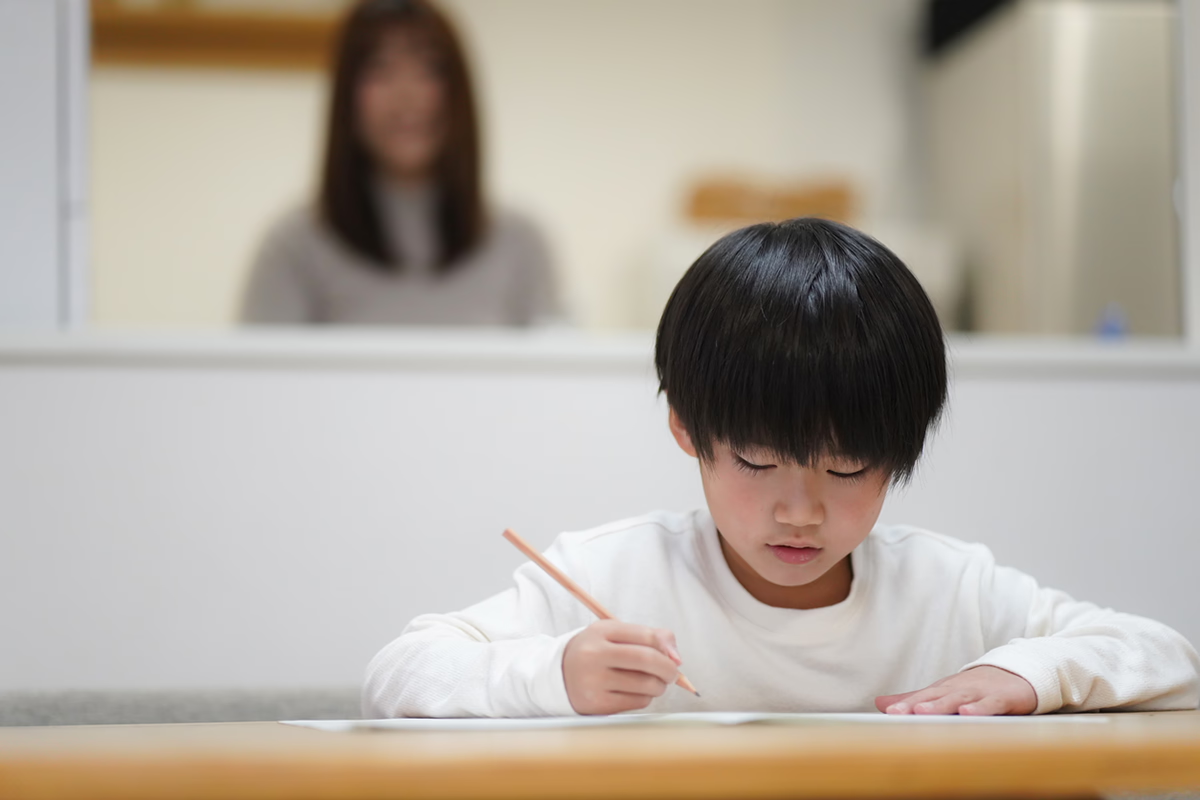住まいと暮らしのライフスタイルマガジン『HomeLife』。
家での暮らしをより楽しく、豊かにするための様々な情報を発信します。

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
目次
子ども部屋は、子どもの成長に伴いモノが増減したり、種類が変化する空間なので、収納や片付けに悩むこともあるでしょう。収納を工夫するとモノの変化に柔軟に対応でき、片付けやすくなります。
今回は、実用性とインテリア性を重視した子ども部屋収納のアイデアや、子どもの成長段階に応じた収納スペースの家具レイアウトなどを取り上げます。
あわせて、様々なライフステージに合うDAIKENのシステム収納もご紹介します。
子ども部屋に収納が必要な理由
子ども部屋は、単に寝たり遊んだり、勉強したりする場所というだけでなく、子どもの成長を支える大切な空間といえます。中でも子ども部屋の収納スペースは、子どもの生活習慣や自立に関わる要素の1つといえます。
片付けが習慣化しやすくなる
自分の部屋に適切な収納スペースがあって部屋がいつも片付いていれば、自然と生活リズムも整い、スムーズに行動できます。また、散らかっている部屋がどうしたら片付いた状態になるのか考えるようになると、段取りや物事を取捨選択する力が身に付いていくでしょう。片付ける習慣や、整理整頓された空間を快適だと思う気持ちは大人になっても役立ちます。
整理整頓の見直しは安全性につながる
おもちゃや学用品、小物、雑貨が床に散らかったままになっていると、見た目が雑然としているばかりでなく、転倒やケガ、年齢によっては誤飲などの原因にもなりかねません。
収納が機能してきちんと片付いた部屋は、安心して過ごせる空間となるでしょう。
使いやすい収納が自立を助ける
子どもが自分で片付けをする行為は、自立心を育てる第一歩です。手の届く高さの棚やラック、出し入れしやすい引き出しがあると、大人の手を借りずに自分の持ち物を自分で管理する習慣を身に付けやすくなります。適切な収納は、自己管理能力の向上につながります。
片付いた空間での勉強ははかどる
周りにモノが散乱していると気になってしまい、落ち着かないこともあるでしょう。国内外の大学で、「机の上が雑然としていると勉強に集中できない」「整理整頓が学力に影響を及ぼす」といった報告がされているようです。
部屋や学習机の上が片付くと視界に入る情報が少なくなり、その分、目の前の勉強に集中できる環境が整います。
収納上手な子ども部屋づくり!おしゃれにスッキリ隠すには?

子ども部屋は散らかりやすい空間だけに、収納には工夫が必要です。使いやすいうえ、きちんと片付いた印象を与えられる収納について考えてみましょう。
クローゼット収納で整った部屋に
収納の定番であるクローゼットには、洋服やバッグ、オフシーズンの寝具、季節用品などをまとめて収めましょう。扉を閉めてしまえば中のモノを隠せるので、部屋全体が整った印象になります。
子どもが開け閉めしやすい折れ戸や引き戸タイプの扉を選ぶと、さらに使い勝手も良くなるでしょう。
オープン収納で使いやすく
オープン収納は、遊び道具や本、学用品など、使用頻度の高いモノを出し入れするのに適しています。バスケットやボックスを使うと見た目がスッキリし、色やデザインによってはおしゃれなインテリアになります。子ども自身が楽しみながら片付けや管理をできるようにしましょう。
使い分けが片付け習慣のカギに
「よく使うモノは見える位置に、たまに使うモノは隠す場所に」といった収納の使い分けルールを一緒に考えましょう。例えばオフシーズンの衣類や思い出の品はクローゼットに、日常的に使う学用品やおもちゃはオープン収納に分けるのもよいでしょう。小さいお子様の場合、最初は大人が一緒に片付けをすることで、片付けの習慣が身に付きやすくなります。
おすすめ記事
2025.06.23
勉強環境を整える収納机

最近、自室のほかにもリビングなどで勉強するお子様も多いようです。どのような場所で勉強するにしても、あると便利なのが専用の勉強机です。“収納机” “収納付きデスク”などと呼ばれる机は、その名のとおり収納を兼ね備えた机で、普段使いのモノを手の届く範囲に収納できる点が魅力です。ここでは収納付きデスクを使用するメリットについて説明します。
必要なモノをまとめて収納
収納机は、学習に必要な道具を1か所に集約できる点がメリットです。ノートや鉛筆などの文房具や教科書をセットで机の引き出しや棚にまとめておけば、必要な道具を必要なときにすぐ取り出せるので、気が散らずに集中して勉強できます。
収納の“見える化”でモチベーションが上がる
机周りに必要な用具が揃っていると、学習に対するモチベーションが上がります。しかし、引き出しの中がごちゃごちゃしていては逆効果です。ラベリングや仕切りを活用して引き出しや棚の中を整理し、「何がどこにあるか」が一目でわかるようにしましょう。
子ども自身が片付けやすくなり、自分だけの学習スペースとしての愛着が生まれることも期待できます。
おすすめ記事
2025.07.07
子どもの成長段階別・子ども部屋のレイアウト

子どもの成長段階によって、部屋の使い方や必要な収納は変化します。成長に応じた工夫を取り入れて、子どもの自立心や学習意欲を育てる空間にしましょう。
未就学児、小学生、中学生・高校生それぞれに適した部屋づくりと収納のポイントをご紹介します。
未就学児
未就学児の部屋は、大人の目が届きやすく安全性を確保できるレイアウトを優先しましょう。例えば、リビングやダイニングの近くに子ども部屋を配置したり、扉を開けたままで様子を確認できるようにするなど、生活の中で大人が自然に見守れる環境にすると安心です。
収納家具は、角が丸い形状、指を挟まない構造、化学物質不使用など安全面への配慮がされているかを考慮します。加えて、子どもの身長に合った高さで、手が届きやすいかどうかも確認すると安心です。
この年頃は、大人と一緒に遊び一緒に片付ける、というケースも多いのではないでしょうか。片付けの際は、おもちゃ、ゲーム、絵本など、大まかなカテゴリーに分けます。入れるだけのボックス収納にすると、分類と片付けが楽になり、習慣化しやすくなります。
関連記事⇒「子どものリビング学習 机は? 収納は? おすすめの間取りとレイアウト」
小学生
小学生になると、ランドセルやリュック、学用品などの持ち物が増えるので、収納に工夫が必要になります。
就学と同時に学習机を購入するご家庭もあるでしょう。そのタイミングで、子どもが自分で片付けを習慣化できるよう大人がサポートします。
まずは、それぞれの置き場所を決めます。学用品は教科ごとに分ける、衣類は季節や用途別のハンガー収納にするなど、わかりやすい仕組みをつくりましょう。
学習机とベッドの配置、学用品の収納場所など、毎日の動線を考えたレイアウトも重要です。例えば、玄関近くや部屋の入口付近にかばん類や上着の収納場所をつくり、机の隣に本棚を配置すると、準備や片付けがスムーズになります。
中学生・高校生
中学生・高校生になると、これまでの“片付けやすさ”や“管理のしやすさ”に加え、“収納量”や“使いやすさ”をプラスした収納が重要です。
部活動や趣味で使う道具、参考書や資料などアイテムの種類も量も増えるので、新しく大きめの収納家具を購入する必要が生まれるかもしれません。壁面も含めて、空間全体を有効に使う方法を検討してみましょう。
受験勉強などで学習に一層集中する時期でもあり、勉強するときは余計なモノが視界に入らないようにすると勉強しやすい環境が整います。学習に関係ないモノは机から離れた場所に収納するとよいでしょう。テレビは机の後ろに設置するのもおすすめです。
好きなカラーやインテリアスタイルへのこだわりが出てくる年頃でもあるので、居心地が良く愛着を持てる空間になるよう、希望を尊重することが大切です。
『MiSEL(ミセル)』で叶える、片付けやすくおしゃれな子ども部屋

勉強道具はもちろん、身の回りのモノがスッキリと片付けられる収納があると、子ども部屋はより快適になるでしょう。DAIKENでは、子どもの成長に合わせて使い方を変えられる収納『MiSEL(ミセル)』を展開しています。
子どもの荷物は小学校の6年間で大きく増加するといわれています。『MiSEL(ミセル)』の収納机は、ゆとりをもった収納量と整理整頓しやすさが特長です。ランドセルなどのかばん類をはじめ、教科書やノート、ファイルなど、小学生の荷物がきれいに収まります。
また『MiSEL(ミセル)』は、ユニットの組み合わせにより、高さや横幅を自由に調整できます。幼少期にはおもちゃや絵本の収納、さらに成長するにつれ学用品や衣類の収納にするなど、成長やライフスタイルの変化に応じて収納スペースを再構成できます。
豊富なカラーバリエーションとシンプルなデザインは思春期以降も使いやすいでしょう。片付けやすく、おしゃれな子ども部屋収納の実現に役立つアイテムです。
まとめ
子ども部屋の収納は、部屋をきれいに保つためだけでなく、子どもの成長や自立を支えるうえでも重要な役割を果たします。年齢に応じたレイアウトや収納を取り入れれば、成長に合わせた使いやすい空間になるでしょう。
“見せる収納”と“隠す収納”のバランスを意識し、収納のルールを子どもと一緒に考えると、片付けやすさと取り出しやすさの両立につながります。
成長に合わせてアレンジできる収納製品なども上手に取り入れながら、長く快適に使える子ども部屋づくりを目指しましょう。
関連製品
-
実用性を備えた魅力あるユニット
おすすめ記事Recommends
-
2025.08.20
-
2025.08.20
-
2025.08.20