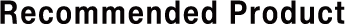地域活性化に繋がる国産木材活用のすすめ 構造材に固執しない木材活用
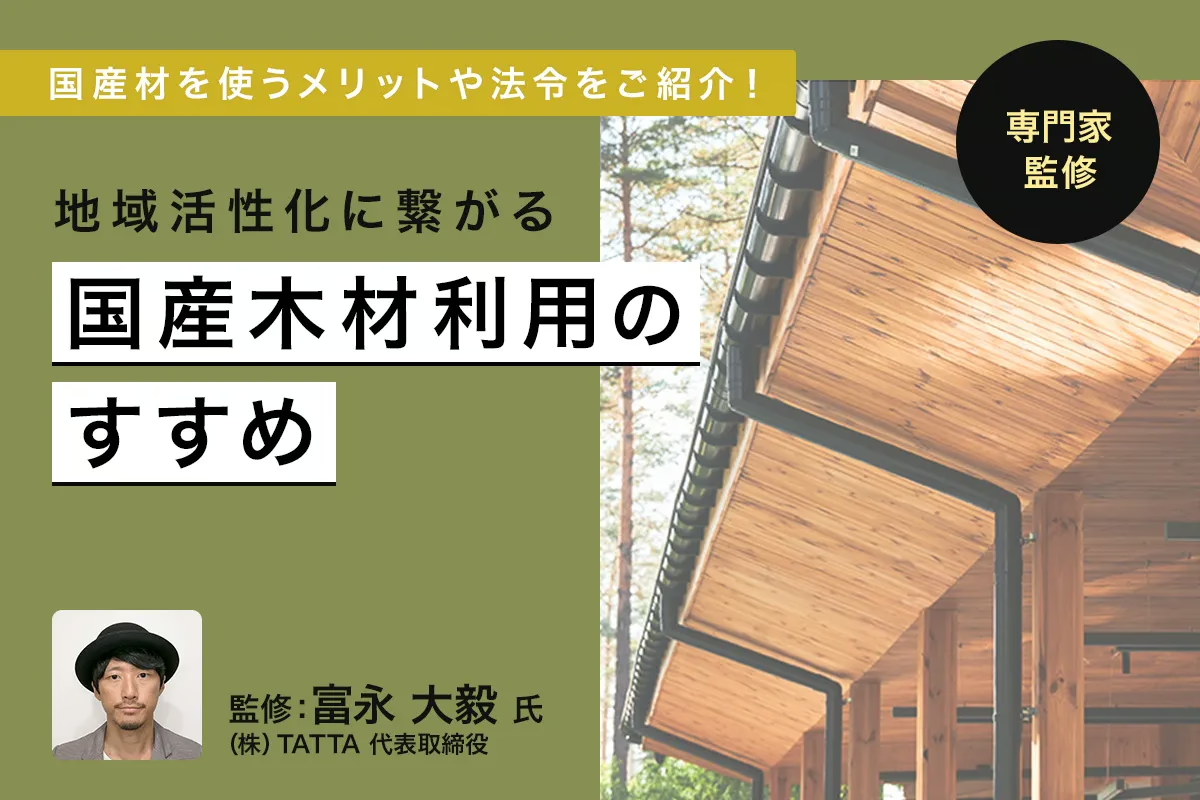
目次
近年、地球環境に対する意識が高まる中で、建築業界でも持続可能性を重視した取り組みが増えています。中でも特に注目すべきテーマの一つが「国産木材の活用」です。日本の国土の約67%が森林という中、高度経済成長期に植林されたスギなどが伐期を迎え、2000年に20%を割っていた木材自給率も40%近くまで上がってきています。地域ごとの特性を生かしつつ、持続可能な社会にも大きく貢献する木材。さらに林業の方まで視野を広げると、どういう木の使い方が森林の持続可能につながるのか、また違った視座が見えてきます。本記事では、木材利用の活用事例や知っておくべき法令などをご紹介します。
監修者
-

-
株式会社TATTA
代表取締役
富永 大毅 氏
建築家、一級建築士、建築学修士
2001年東京都立大学工学部建築学科卒業後、ミュンヘン工科大留学を経て、2005年東京工業大学理工学研究科建築学専攻修了。
2005年千葉学建築計画事務所、2008年隈研吾建築都市設計事務所を経て2012年富永大毅建築都市計画事務所を設立。
2019年株式会社TATTA代表取締役。
2016年より林業と建築のよりよい関係構築を目指すべく、製材所に通いダイレクトに現場に製材を納品する設計スタイルが始まる。
2017年~首都大学東京 非常勤講師、2018年~日本大学 非常勤講師、2022年~明治大学 兼任講師など多くの大学で建築教育にも携わる。
「GOOD DESIGN AWARD 2021」「住まいの環境デザイン・アワード2019ベターリビングブルー&グリーン賞」、「ウッドデザイン賞2017」「AICA施工例コンテスト2017最優秀賞」「第20回木材活用コンクール第三部門賞」など受賞多数。
国産木材活用のメリットと設計者が心得ておくこと

国産木材と設計者の接点を考えた時、多くは、木材メーカー、プレカット工場、CLTや集成材を扱うのであれば各々の工場が関係してくるかと思います。それを踏まえて、現在伐期を迎えている日本の森林状況を鑑みると、私たちには二つの道があります。
ひとつは木材の量を扱うことです。CLTや集成材に使う材は、材の善し悪しに関わらず、山を丸ごと伐採する皆伐された材が使われます。こうした材には高値は付きませんが、時間がかかるにしろ皆伐された森も放っておけば広葉樹を中心に森は回復していきますので、人口の減っていく日本社会を考えると、人工林を減らしていくのも大事な方策のひとつです。
もうひとつは、木材の質を扱うことです。無垢の製材を使い、安価な構造材だけでなく値が付きやすい造作材を活用し、原木の価格を上げることができれば、再造林までコストが回り、森林環境税に頼らずとも林業=森の保全が続き、国土の7割近い森林を経済資源として活用していくことができます。
いずれにせよ、ひと昔前にあった森林伐採=悪という感覚とは真逆で、現代の日本では木材を大量に使うべき状況にあります。
そのため、実際の施工現場の近くにどういう工場・製材所があるかを把握しておくことが、輸送コストをかけすぎない地域産材の使用につながります。設計者が、現場近隣の製材体制をきちんと把握し、地域産材を積極的に利用することで、地元の林業や経済の活性化を期待することができます。
地域産材を利用する際には、最も近い山の材料を採用すると、その材料がどの山と地続きで、どのような里山圏を形成しているのかを伝えることができます。今後、より小さな経済圏が社会で重視されていく中で地域産材を利用することは、建物の利用者にブランドや会社の理念を伝える方法としても有効です。森林の状況は地方自治体によって大きく異なるのも、国産木材活用の面白いところです。
-
―国産木材活用に関する記事―
・杉・栃などの地域産材を内装材に! 地元に愛される施設を目指して
・地方創生を考えた公共施設づくり 市民センターに地元の木材を活用!
国産木材活用のデメリットと設計者が心得ておくこと

国産木材を使用する際の最大のデメリットに、長らくコストが高くなるのではないかという懸念がありました。しかし、近年はウッドショックなどの海外情勢により輸入材の価格が大幅に上昇。これを受けて、国産木材と輸入材の価格差が縮小し、むしろ国産木材は利用しやすい状況になってきています。
ウッドショックに関する記事については、下記でご紹介していますので、こちらもご確認ください。
⇒ウッドショックで見直される日本の木 国産材・地域産材を活用した地産地消の施設づくり
また、ここでも量と質の問題があります。
量の問題は、時間の面にも関わってくるのですが、国産木材は地域によって、林家が山に入れない雨期には流通量が少なくなるなど、流通量が安定しない傾向にあり、乾燥方法によっては納期がかかるという問題があります。ただ、国による国産木材活用推進の取り組みなどにより木材自給率も増加傾向にあり、今後は流通量が徐々に増えていくことが予想されます。
設計者としては、事前に製材所のストックと乾燥機の状況を見極めて納期から発注のタイミングを逆算し、場合によっては事前の材料調達が必要となってきます。面倒に思えるかもしれませんが、なんでも翌日には届くAmazonと比較して、地元の小さな本屋で本を買うと、在庫がなくて取り寄せに時間がかかるイメージと一緒です。地域経済を回すには少し時間と手間がかかるのです。
もうひとつは質の問題です。外材と比較すると湿度の高い環境で育った国産木材は、乾燥や製材技術がしっかりしていないと材の質が安定しないことがあります。これに対してはJAS(日本農林規格)構造材の活用があります。JASの認定を受けている製材所は限られますが、公共事業をはじめ、JAS材使用の義務化が進みつつあります。またJAS構造材利用の補助金もここ数年充実していますので調べておくとよいでしょう。
※参考:全国木材検査・研究協会「製材等JAS認証工場名簿」
構造材だけじゃない、国産木材活用に関する国や自治体の取り組み

木材利用の方法の1つに、構造材にも、仕上げ・造作・家具材にもなることが挙げられます。
構造材として利用する場合、燃えやすく安定しないというデメリットからは、なかなか逃れるのが難しいという事実があります。
このデメリットを無理に解決しようとすると、下記のようなケースが考えられます。
・他の構造形式よりもコストがかかってしまう
・不燃処理できる工場が限られるため、地域産材の利用を諦めてしまう
・やり方を間違えると、手触りや香りどころか、石膏ボードを巻く必要がでて、木の魅力がほとんど残らない
木材利用を考えるとき、無理に構造材にこだわらずに、仕上げや造作材のように人の手に触れやすいところに木材をどう使えるかが設計者としての腕の見せ所でもあります。以降、構造材と仕上げ・造作・家具材の両者に分けて、国産木材活用に関する取り組みをみていきます。
●構造材系
・「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」改め
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」
国産木材活用に関する国の取り組みとしては、2010年に制定され通称「木材利用促進法」があります。この法律により、公共建築物の木造率は増加したものの、非住宅分野や中高層建築物の木造率は低位にとどまっていました。
そこで、木材の利用を公共建築物から建築物一般に拡大するために、2021年に法律の一部を改正した「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施工されました。
この法律は木材全体の需要を拡大し、森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与することを目的としたものです。国が整備する公共建築物においては、原則全ての建築物の木造化を推進することを目標としています。
※参考:林野庁「都市(まち)の木造化推進法」
・JAS構造材実証支援事業
実質的に3F建て以上の木造には必要となるJAS構造材。今後、建築基準法の4号特例見直しが進めば、さらなる需要が生まれそうですが、認定製材所が少ないことから、なかなか広がってない実情があります。そこで、構造材にJAS構造材を活用する低層の戸建ての居住専用住宅及び事業用併用住宅を除く建築物(施主が国以外)の実証的取り組みに対し、構造材の調達費用の一部を助成するという事業です。かなり人気が高いようで2023年度は二次募集も締め切ってしまっていますが、今後も注視していきたい取り組みの一つです。
※参考:全国木材組合連合会「JAS構造材実証支援事業」
・木の学校づくり先導事業
また、建築基準法の耐火基準が改定されたことで、大規模木造校舎が建てやすくなったことを受け、文部科学省は「木の学校づくり先導事業」を2015年より展開しています。
木の学校づくり先導事業に関する記事については、下記記事でご紹介していますので、こちらもご確認ください。
⇒文部科学省が促進する地元の杉やヒノキを活用した木の学校づくり そのメリットとは?
●仕上げ・造作・家具材系
・木づかい運動
林野庁では木材を利用することの意義を広め、木材利用を拡大していくための国民運動として、2005年から「木づかい運動」をはじめています。身の回りのものを木に変えたり、生活に木を取り入れることを意味する「ウッド・チェンジ」を合言葉に、全国各地で木材利用促進運動が展開されています。他にも、木材や木製品との触れ合いを通じて木材への親しみや木の文化への理解を深めて、木材の良さや利用の意義を学んでもらう「木育」などの取り組みも行われています。
-
―木づかい運動や木育に関する記事―
・木育を保育園・幼稚園からはじめよう! 地産地消の木のおもちゃで五感を磨き、SDGsにも貢献
・「木育」が地球環境を救う? 子どもが木のぬくもりを身近に感じられる学習環境
・外構部の木質化対策支援事業
クリーンウッド法に基づいて合法伐採された材を使用することを条件に、街並みに寄与しやすく法的な制限のかかりにくい塀やデッキの製作に対して補助金がつく取り組みです。
※参考:全国木材協同組合連合会「外構部の木質化対策支援事業」
構造材だけじゃない、国産木材活用に関する東京都の取り組み

木材利用に対する補助的な取り組みは自治体ごとに様々あり、都市部でも国産木材の活用が進んでいます。その一例として、東京都の各種取り組みをご紹介します。これらの取り組みでは地域活性化、建築物の木造化推進といった視点から多摩産材を中心とした国産木材の活用を推進しています。
●構造材系
・中・大規模建築物の木造木質化設計支援事業
設計に補助金が出る、珍しい取り組みです。東京都内の中・大規模の民間施設を対象に、建築施設の主要構造部に一定以上の国産木材を使用する際にかかる経費を補助します。
●仕上げ・造作・家具材系
・にぎわい施設で目立つ多摩産材推進事業
だれでも利用できる、人が多く集まる都内の施設(駅舎、商業施設など)を対象に、多摩産材を内外装や什器に使用した際の経費を補助する取り組みです。
・木の街並み創出事業
多摩産材の普及と需要拡大を目的に、東京都内における商業施設やオフィスビルなどの民間施設の外壁・外構材への国産木材(多摩産材3割以上)を利用した際の経費を補助する取り組みです。
・多摩産材活用木材利用ポイント事業
多摩産材の利用拡大と地域経済の活性化を図るため、多摩産材の利用量に応じて東京の特産物等と交換できるポイントを交付する事業です。東京の農林水産物、伝統工芸品、国産木材製品など、様々な特産物とポイントを交換することが可能です。
木材を上手に活用するため知っておくべき法令・条例

木材の利用は基本的には耐火との戦いです。上手に活用するためには、法令と条例の知識が必要です。2019年の建築基準法改正で、木造建築に係る制限が合理化されていますので、最新版をチェックしましょう。耐火建築物になるのを避け、防火壁などによる1000m²ごとの区画を上手に使いながら設計する必要があります。その際に知っておくべき主要な法令・条例についても構造材系とそれ以外に分けて確認しておきましょう。
●構造材系
・燃えしろ設計に係る告示
建設省告示1901号1902号。準耐火建築物で木材を表しにするためには、基本燃えしろ設計となります。30分、45分、1時間と分けて、集成材だけでなくJAS構造材の場合も使えます。
・施行令136条の2の技術的緩和
防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準で、面積制限などにより、燃えしろ設計を使うことなく、木の架構が表しやくなります。木材の利用を拡大するための重要な要素となっています。
・準耐火構造の構造方法を定める告示
規模に関わらず木造で木に無理をさせずに主要構造部を表しにするためには、最低でも準耐火構造に留める必要がありますが、この告示をよく知っておく必要があります。耐火性能を確保しながらも、美しい木造建築を実現するための基準となります。
※参考:林野庁「準耐火構造の構造方法を定める件」
●仕上げ・造作・家具材系
・内装制限
規模や用途で木材の内装使用は制限されている場合があり、この面積限度を押さえておくことがまず必要になります。また、100m²以内で区画されている内装や、床、家具に関してはこの制限がかからないため、木材を活用することが容易になります。不燃処理材になってしまうとメーカーが限定されるため地域産材の利用が難しくなります。
まとめ
現代は木材をいくらでも多用していい時代であり、同時に豊富な森林資源とそれを活かすための技術や価値観を、どうしたら次の時代につなげられるかが問われている時代です。
国産木材活用の軸となるのは規模を問わず、製材に関わる工場・製材所です。
設計者には、
・現場に近い製材所とその特徴を捉えること
・構造材に固執せず、木材それぞれのもつ特質を活かす使いどころを考えること
・木材の量を使うなど、魅力的にみせる表しの方法を考えること
・建築を訪れる人々に、地元の山への思いを少しでも持ってもらうこと
といったことが求められています。
おすすめ製品