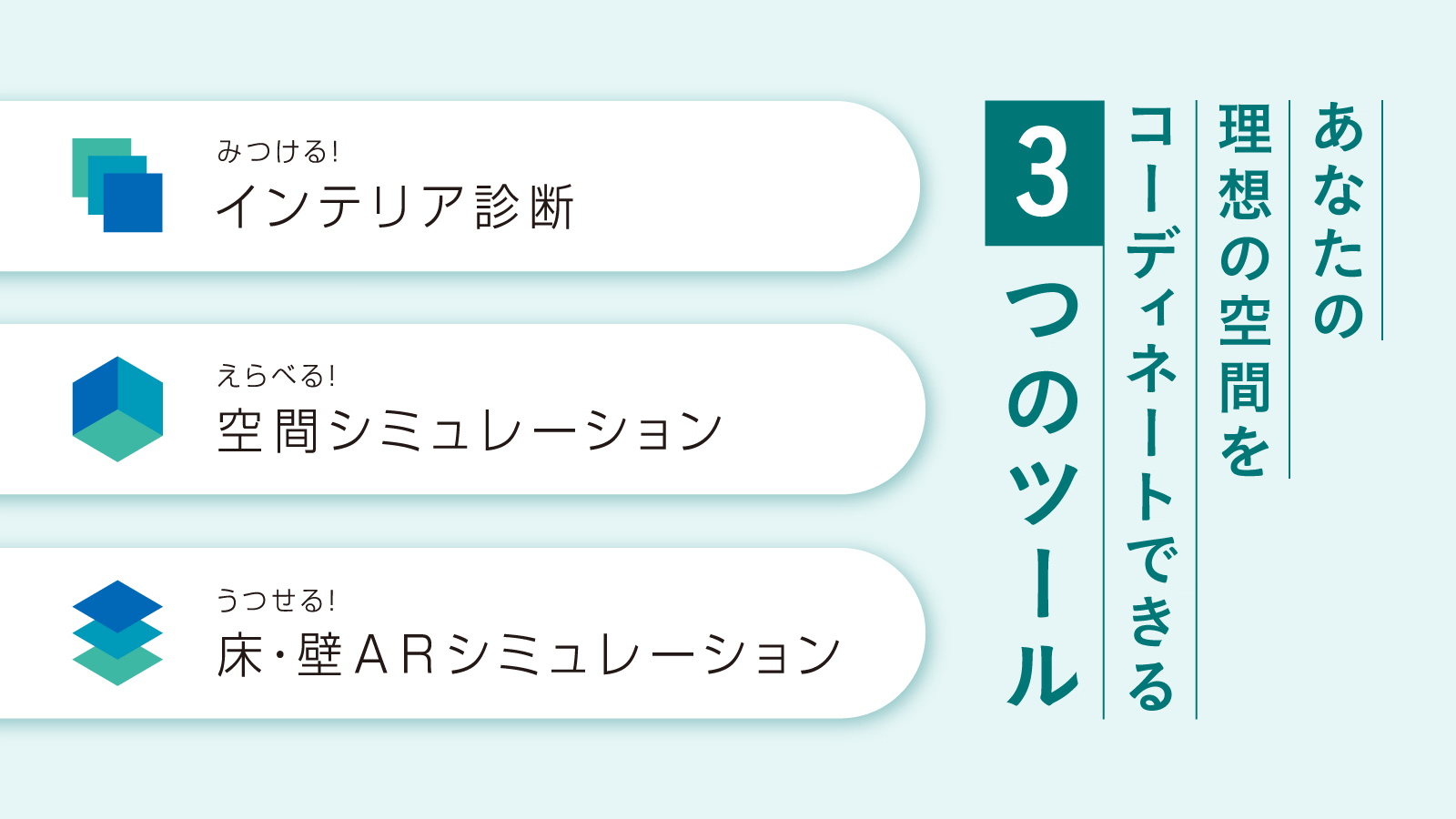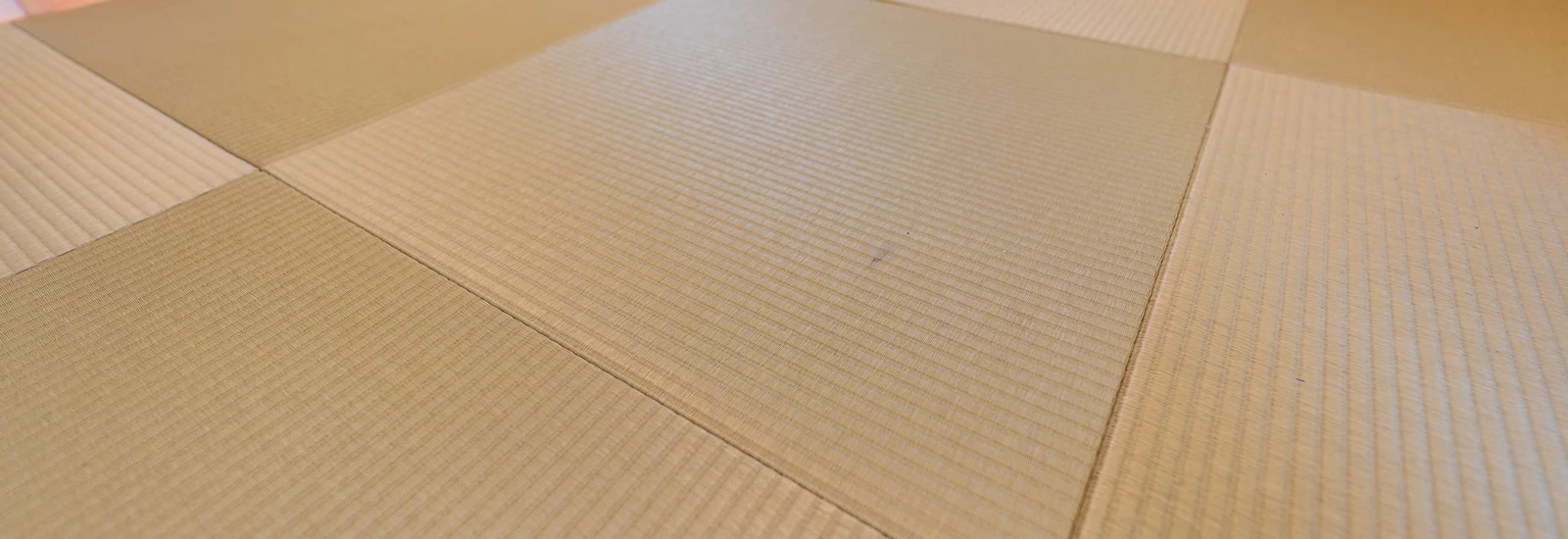
琉球畳とは? 置き畳、ユニット畳との違いと、畳表の材料となる七島藺、イ草、和紙畳の違い
※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
“琉球畳”という畳をご存知でしょうか? 名前は聞いたことがあっても、実際にはどのような畳なのか知らない方も多いと思います。
本記事では、知っているようで知らない琉球畳について、その特徴や普通の畳との違いなどをご紹介します。
関連記事⇒「床の見切り材はどのくらい重要? インテリアやフローリングの色柄に合わせてコーディネート」
関連記事⇒「居室とはどのような部屋のこと? 間取り図にあるDENとは? 畳を使ったおしゃれかつモダンな和室リフォーム」
琉球畳とは 縁がない正方形の畳の正体
昨今は、周りに縁がない正方形の畳を、“琉球畳”と呼ぶことが多いのですが、これは正確な呼び方ではありません。それでは、琉球畳について詳しく見ていきましょう。
●琉球畳とは
琉球畳とは、七島藺(しちとうい)という植物を使った畳表で作られた畳のことをいいます。
この七島藺がかつて、沖縄(琉球)で栽培されていたことから、琉球畳と呼ばれるようになりました。
畳の形状が長方形でも正方形でも、七島藺で作られていれば、本来はすべて琉球畳です。しかし、現在は七島藺で作られていなくても、縁なしで正方形の畳を琉球畳と呼ぶケースが多く見られます。
●琉球畳の特徴と普通の畳との違い

琉球畳と普通の畳の最も異なる点は材料です。普通の畳は素材にイ草を使っていますが、琉球畳の素材には七島藺が使われています。
七島藺を畳表にするための工程は、普通の畳に使われるイ草と比べて大変な手間がかかりますが、琉球畳は普通の畳より耐久性に優れていて、縁をつける必要がありません。
その丈夫さから、1964年に行われた東京五輪の柔道会場でもこの琉球畳が使用されたそうです。
現代では普通の畳との違う点として、「縁がないこと」「畳の形状が正方形であること」が一般的な琉球畳の特徴として知られています。
● 七島藺(七島イ)とは

七島藺は、琉球畳の表面に使う材料となるカヤツリグサ科の植物で、元は琉球王国やトカラ列島で栽培されていました。そして、トカラ列島には7つの有人島があることにちなんで、七島藺と呼ばれるようになります。現在は大分県の国東地方だけで生産されている貴重な植物です。断面が三角形である七島藺を使って畳表に仕上げるにはかなりの手間がかかりますが、非常に丈夫な点が特徴です。
● 琉球畳の歴史
琉球畳の歴史は江戸時代にまでさかのぼります。
1609年以降に現在の鹿児島県である薩摩藩が琉球王国を支配下に入れたことで、琉球王国に畳が取り入れられたといわれています。つまり、琉球畳の歴史はおよそ400年あまりと、平安時代から存在すると伝わっているイ草の畳に比べるとまだ浅いのがわかります。
置き畳、ユニット畳と琉球畳の違いは?

置き畳とは、主にフローリングの上に置いて使える畳のことで、半畳分である正方形のものが主流です。洋室の一部に畳のスペースが欲しい時など、家が完成した後でも工事なしで手軽に取り入れることができます。
●ユニット畳
ユニット畳とは、名称が違うだけで置き畳と同じものと考えて差し支えありません。ほかにもシステム畳やリビング畳と呼ばれることもあります。
●置き畳と琉球畳の違い
縁がない正方形の畳のことを総じて琉球畳と呼んでしまっているケースが多くありますが、本来の意味は少し異なります。七島藺を使用していれば形状によらずすべて琉球畳となるのです。
また、置き畳と琉球畳には厚みの違いもあります。琉球畳は通常の畳と同様に60mm程度が多いのに対して、置き畳は厚みが薄いものが多く、15mm程度のものが主流です。
置き畳を使ったおしゃれな和モダン空間づくりに興味がある方は、ぜひ下記の記事もご参照ください。
関連記事⇒「置き畳でフローリングをおしゃれに彩る! お手軽和モダンな部屋づくり」
フローリングに敷くだけで畳スペースがつくれる方法は、下記の記事をご参照ください。
関連記事⇒「畳をフローリングに敷いて寝転がる快感! 気軽に楽しめる“置き畳”の魅力と畳の部屋の使い方」
琉球畳のメリット・デメリット

それでは、琉球畳のメリットとデメリットについてご紹介しましょう。
●琉球畳のメリット
・イ草畳に比べて耐久性が高い
・縁がなくスタイリッシュな見た目
・洋室との相性も良い
●琉球畳のデメリット
・普通の畳より高価なうえにサイズが小さい
・裏返しをして使用することができない
・縁がないため角が傷みやすい
七島藺を使用した本来の琉球畳はほとんどの工程を手作業で行っているため、希少性が高く納品までに時間がかかる場合があります。それでも本物にこだわりたい、という方にはおすすめです。
別の素材の畳でも機能性やデザイン性が良いものがあれば検討したい、という方は次にご紹介するDAIKENのインテリア畳『ここち和座』もおすすめです。
畳をフローリングマットに替えたいと考えている方は、下記の記事でメリット・デメリットをご参照ください。
関連記事⇒「畳の上に敷くフローリングマットでカビ・ダニを防ぐには 畳をフローリングに替えて和室を快適でおしゃれに!」
和室からのリフォームについては、ぜひ下記の記事もご参照ください。
関連記事⇒「和室をおしゃれにリフォーム! ドアの扱いと、洋室・和室・和モダンのメリット・デメリット」
高機能でデザイン性にも優れたインテリア畳『ここち和座』

●耐久性や撥水性に優れ、傷つきにくい
インテリア畳『ここち和座』は、和紙※に樹脂コーティングなどの特殊加工を施した高機能な畳表を使用しており、メンテナンスも簡単です。
・撥水性に優れている
・ひっかき傷やすり傷がつきにくい
・耐光性が高く紫外線による変色が起こりにくい
・カビの発生やダニの増殖が少ない
●扱いやすい厚さ 敷き込みタイプはフローリングと同じ12mm!
『ここち和座』にはフローリングの上に置いて使える置き敷きタイプと、床の下地の上に施工する敷き込みタイプの2種類があり、それぞれに厚みが異なります。置き敷きタイプの厚さは13〜14mm。敷き込みタイプは一般的なフローリングと同じ12mmのため、通常の畳の場合と違い 床下地を下げることなく簡単に施工できます。
●カラーバリエーションが豊富!
『ここち和座』はデザイン性が高く、豊富な柄やカラーバリエーションがあるため、生活の様々なシーンにあわせて選べます。ここでは新たにラインアップされた『ここち和座 穂波』の置き敷きタイプと敷き込みタイプをご紹介します。
・『ここち和座 置き敷きタイプ 穂波』

『ここち和座 置き敷きタイプ 穂波』は、自然な風合いと柔らかな質感が特長です。カラーは3種類から選べます。
・『ここち和座 敷き込みタイプ 穂波』

『ここち和座 敷き込みタイプ 穂波』は、フローリングとシームレスに融合するデザインが魅力です。フローリングとのコーディネートがしやすく、インテリア選択の幅が広がります。
小上がりで畳を使いたい方は、ぜひ下記の記事もご参照ください。
関連記事⇒「リビング収納にもなる”小上がり” 和紙の畳おもてが魅せる快適生活」
まとめ
琉球畳や置き畳・ユニット畳は、伝統的な和の趣とモダンでおしゃれなデザインを両立させた床材です。
特に『ここち和座』のようなインテリア畳は、従来の畳の良さを残しながら、現代の生活にも合わせやすい機能性とデザイン性を備えています。これらを活用して、ライフスタイルに合わせた魅力ある和空間づくりにぜひトライしてみてください。
(※)機械すき和紙を使用しています。コウゾ、ミツマタ等を使用した手すき和紙ではありません。
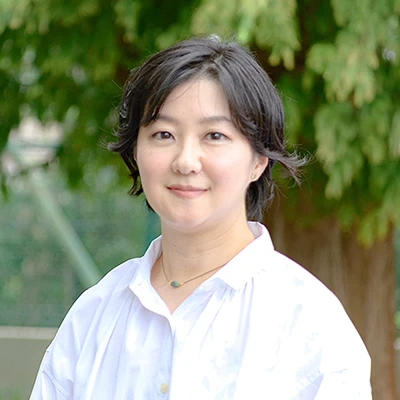
-
監修者
淀川 美和(よどがわ みわ)
株式会社アートアーク一級建築士事務所代表。一級建築士、インテリアコーディネーター、2児のママ建築家。「ママをきれいにする空間づくり」 をミッションの一つに掲げ、住宅・店舗・ホテル等の設計、内装コーディネート、メディア出演等を行う。自身も仕事と家事と育児のバランスをとりながら、忙しいママがいかに快適に家族と暮らせるかに焦点をあてつつ「お部屋のコンシェルジュ」として皆さまのお役に立てるよう奮闘中。
保有資格:一級建築士、インテリアコーディネーター、建築士会インスペクター、健康住宅アドバイザー、整理収納アドバイザー2級、アロマ検定1級