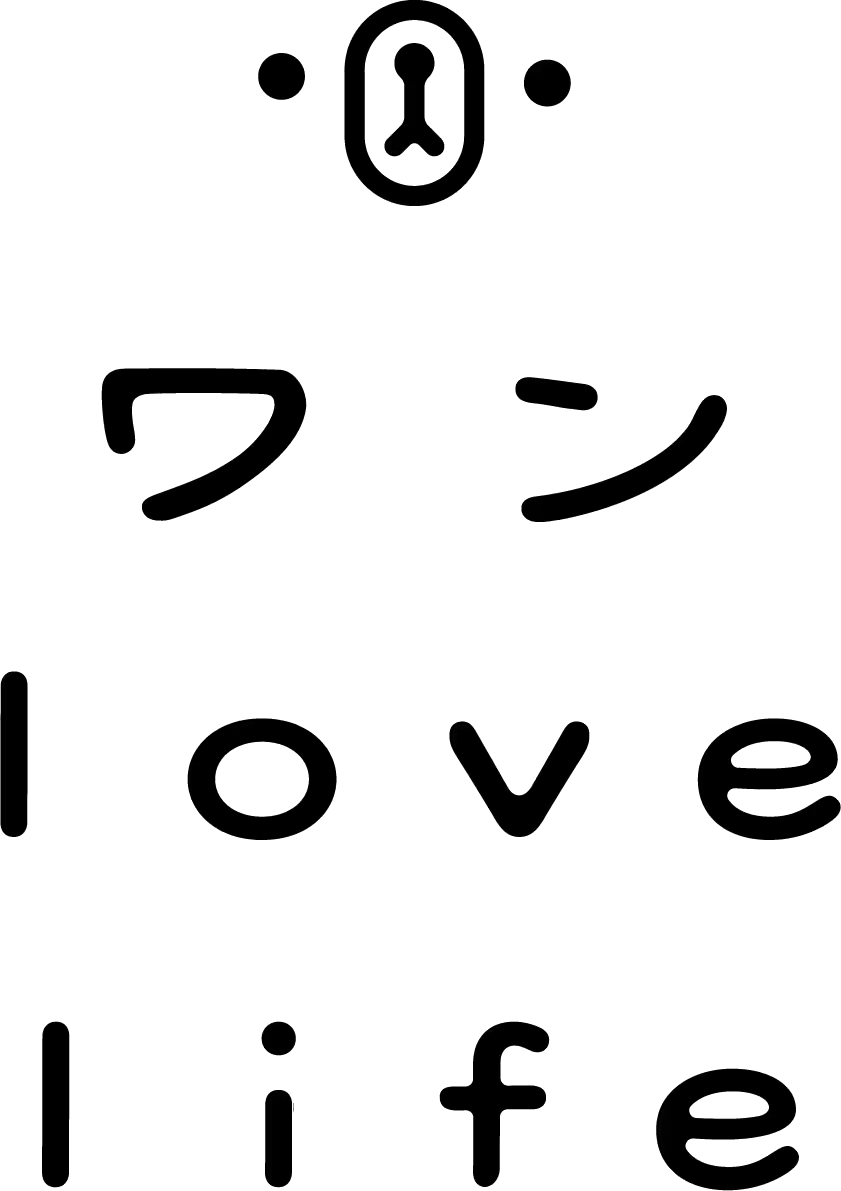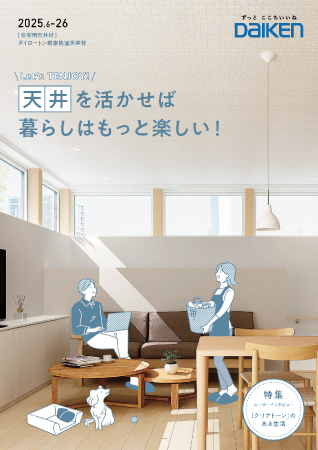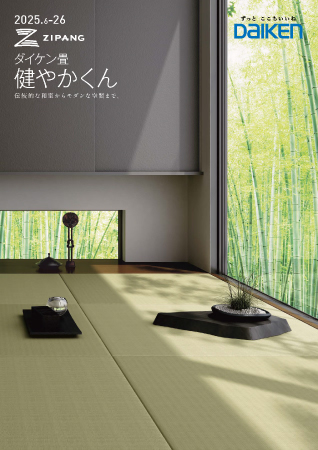犬の爪切りは、大切なお手入れです。しかし、犬の爪の切り方や「愛犬が爪切りを嫌がる」、「どこまで切ってよいかわからない」といった悩みを抱えている方も多いでしょう。
今回は、犬の爪切りが必要な理由と安全な爪切りの方法、そして爪切りが苦手な場合の対策を解説します。また、犬の爪などによる引っかき傷に強いDAIKENの建材もご紹介します。
犬の爪切りは必要?
犬は歩いたり走ったりするときに自然と爪が削れますが、室内犬の場合は通常の散歩程度では適切な長さまで削れません。爪が伸びすぎると、地面に足をしっかり付けられなくなるため、立ち上がりにくくなったり、歩行中にバランスを崩して転ぶことがあります。加えて、伸びた爪が引っかかって折れたり、肉球に刺さってケガにつながるおそれもあります。
犬の爪の中を通っている血管や神経は爪と一緒に伸びていくため、爪を伸ばしすぎると伸びた爪とともに血管や神経も切ることになってしまい、犬に苦痛を与えることになります。犬に負担をかけないためにも、定期的な爪切りは欠かせません。
また、犬の足裏よりも少し上の位置にある“狼爪(ろうそう)”は、地面に触れないため自然に削れることがありません。伸び過ぎると何かに引っかけてしまったり、巻き爪になって傷付けたりすることがあるため、狼爪も定期的に切る必要があります。
犬の爪切りはどこまで切る? 頻度はどのくらい?

犬の爪切りは「血管や神経の手前」まで切ります。白い爪なら血管が透けて見えるので、その手前まで切るのが目安になります。黒い爪は血管の位置がわかりにくいため注意が必要です。スマートフォンのライトなどで爪を照らし、血管の位置を確認して切ります。わからない場合は、一気に切らず、先端から少しずつ切るのがポイントです。
犬の爪切りの頻度は、爪の伸びる速度やライフスタイルによって異なります。例えば、室内で過ごす時間が多い犬は、月に2回程度の爪切りが必要です。一方、散歩に行く機会が多い犬であれば、爪が適度に削れるため、月に1回ほどで十分でしょう。また、犬が歩いているときに“カシャカシャ”と音がしたら爪を切るタイミングです。
■散歩についてはこちらでも詳しく解説しています
・犬の散歩は毎日行くべき? 理想のお散歩とお散歩バッグの中身とは
犬の爪切りのやり方

犬の爪切りをする際、慣れないうちはうまくできるか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。飼い主の不安は犬にも伝わってしまうため、手順どおりに落ち着いて切りましょう。
●犬の爪切りに必要な道具を準備する
まず、犬用の爪切りを用意します。爪切りには「ギロチンタイプ」「はさみタイプ」「ニッパータイプ」があります。ギロチンタイプは切れ味が良く、動物病院でよく使用されています。はさみタイプは、やわらかい爪や子犬向きです。ニッパータイプは、ギロチンタイプの爪切りで切れないときや、巻き爪を切るときに使われることがあります。
爪を切った後のお手入れに使うやすりや、誤って血管を傷つけてしまったときに備え、ティッシュやガーゼ、止血剤も用意しておくと安心です。
●愛犬を脇で抱え込む
まず、愛犬をテーブルの上に乗せて立たせ、爪切りを持っていない側の脇で愛犬を挟むように固定します。高いところにいると、犬は比較的おとなしくなる傾向があり、飼い主も作業しやすくなります。また、低いテーブルを使用する場合も、転落した際のケガを防ぐために、テーブルには滑り止めマットを敷いておきましょう。
●肉球を押して少しずつ爪を切る
肉球を軽く押すと、毛に埋もれている爪が出てくるので、先端を少しずつカットしていきます。後ろ足から先に切ると、犬は爪を切っているところが見えないため、怖がりにくいです。慣れないうちは、伸びている部分だけを切るところからはじめましょう。
白い爪の場合は、血管の手前で爪切りを終了します。黒い爪は、切った断面が湿っぽくなっていると神経や血管が近いサインなので、それ以上は切らないようにしましょう。切りすぎて出血してしまった場合は、速やかに止血剤を出血している箇所に付けましょう。もし、止血剤がない場合は、ティッシュやガーゼなどで傷口を押さえて止血します。出血が止まらないときは、早めに動物病院を受診しましょう。
●爪をやすりで整えて仕上げる
最後に、爪をやすりで丸くなめらかに整えます。やすりで整えておくと、犬が体を掻く際に爪で皮膚を傷つけたり、クッションなどに引っかかりにくくなります。愛犬と一緒に遊んでいるときに、犬の爪に引っかかって飼い主が痛い思いをすることがなくなるでしょう。爪のやすりは人間用のものでも代用できます。
愛犬が爪切りを嫌がるときの対策
もともと足先に触られるのが苦手な犬や、過去に深爪で痛い思いをした犬など、爪切りが苦手な場合もあります。愛犬が爪切りを嫌がる場合、どのように対処すればよいでしょうか。
●無理をせず、嫌がる前に中断する
大切なポイントは、無理をしないことです。犬が嫌がる前に中断しましょう。無理やり続けてしまうと、爪切りが嫌いになり、飼い主との信頼関係に影響が出る可能性もあります。また、叱らないことも大切です。1度に全部の爪を切ろうとせず、「1本でも切れたらOK」というくらいの気持ちではじめてみましょう。
さらに、できるだけ子犬の頃から爪切りに慣れさせていくことも大切です。
●おやつを活用する
爪切りが苦手な場合は、おやつを使いながら褒めて、少しずつ切ってみましょう。協力してくれる人がいれば「1人はおやつ係、もう1人は爪切り係」など、役割分担をするとスムーズに行えます。1人で行う場合は、おもちゃなどにペースト状のおやつやウェットフードを塗っておき、犬が舐めている間に切るという方法もあります。
爪切りが終わった後は、途中で中断した場合でもしっかり褒めてあげましょう。“爪切り=いいことがある”と覚えさせることがコツです。
●プロの手を借りることも検討する
いろいろ試してもうまくできない場合は、プロの手を借りることも検討しましょう。犬の爪切りは動物病院やトリミングサロンでも行われています。費用は一般的に500円から1,000円程度です。動物病院なら、爪切りだけでなく愛犬の健康状態もチェックしてもらえます。定期的な健康チェックも兼ねて爪切りに行くのもよいかもしれません。
■トリミングについてはこちらでも詳しく解説しています
・犬のトリミングとは? はじめる時期や料金の目安、サロンの選び方は?
DAIKENのペットにやさしいフローリング材・おすすめ建材
DAIKENでは、ペットにやさしい建材を多数取り扱っています。その中から、愛犬との快適な暮らしをサポートするフローリング材やおすすめの建材をご紹介します。
●愛犬の足腰にやさしい床材『ワンラブフロアⅤ』

『ワンラブフロアⅤ』は、滑りにくい表面仕上げが施されており、小型犬の歩きやすさに配慮したペット用床材です。(※1)
「ワックス掛けが不要」「よだれやおしっこなどの汚れが落としやすい」「傷が付きにくい」など、様々な機能を持っています。床暖房やホットカーペットにも対応しているため、ペットも人間も快適に過ごせます。
●簡単リフォームで愛犬の歩行に配慮『イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄(ペット対応)』

『イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄(ペット対応)』は、小型犬の足の滑りに配慮し、既存の床材から張るだけで簡単にリフォームができる床材です。(※1)
小型犬の歩行だけでなく、ペットの引っかき傷やよだれ、おしっこ、吐き戻しにも配慮し、お手入れも簡単です。
また、豊かな木目の表情が魅力な、様々な柄や色のバリエーションも揃えています。
●愛犬が歩きやすく階下への音を軽減する『ワンラブオトユカ45Ⅳ(147幅タイプ)』

『ワンラブオトユカ45Ⅳ(147幅タイプ)』も、小型犬の歩きやすさと歩行時の沈み込み感に配慮されたペット向けのマンション用の防音床材です。(※1)
抗菌仕様ですり傷が付きにくく、汚れがとれやすい、ワックス掛けも不要といった特長があります。さらに、ホットカーペットや床暖房にも対応しています。
(※1)本製品は小型犬の肉球の滑り抵抗を考慮しておりますが、全てのペット(犬・猫)の歩行に最適とは限りませんのでご注意ください。
●抗菌仕様でやさしい使い心地の和紙畳『ダイケン畳 健やかくん』

『ダイケン畳 健やかくん』は、カビの発生やダニの増殖を抑える性能を持った和紙畳です。(※2)
畳敷きの部屋で犬を飼っていると、爪やおもちゃによる傷が気になりますが、『ダイケン畳 健やかくん』は、ささくれや傷が付きにくく、美しさをキープできます。様々なカラーや柄が用意されており、インテリア性を重視する方にもおすすめです。
●傷や汚れに強く簡単に取り入れられる和紙畳『ここち和座』

『ここち和座』は、手軽に取り入れやすい畳です。(※2)
『ダイケン畳 健やかくん』と同じく、ペット(小型犬など)の爪やおもちゃによる傷が付きにくく、カビの発生やダニの増殖を抑え、撥水性があるため汚れが染み込みにくいのが特長です。
さらに、フローリングの上に置くだけの「置き敷きタイプ」と、フローリングと組み合わせられる「敷き込みタイプ」の2種類を展開しています。
(※2)機械すき和紙を使用しています。コウゾ、ミツマタ等を使用した手すき和紙ではありません。
●消臭・調湿・吸音性能付きの天井材『クリアトーン12SⅡ』

DAIKENの『クリアトーン12SⅡ』は、室内の湿気を吸収・放出する調湿天井材です。
調湿性能により、室内を心地よい湿度に保ち、爽やかな空気をつくります。さらに吸音性能や消臭性能もあわせ持ち、気になるペットのニオイや犬の吠え声、生活音の響きを抑えます。

犬の爪が伸びすぎると、歩きにくくなるだけでなく、ケガをするおそれもあります。伸び具合をこまめにチェックして、定期的に爪切りをしましょう。
どうしてもうまくできない場合は、動物病院やトリミングサロンなど、プロの手を借りるのも1つの方法です。爪切りという習慣に慣れてもらい、愛犬をケガから守ることが大切です。
■あわせて読みたい
・愛犬家のために! 室内やアウトドアで犬と遊ぶためのおすすめ情報
・しわしわの顔や垂れ耳がかわいい! パグの気になる体重や性格、寿命
・小型犬の種類と寿命。ミックス犬やいつまでも小さい犬が抱える悩みとは
-

-
執筆者
伊藤悦子 (いとう えつこ)
麻布大学獣医学部環境畜産学科(現・動物応用科学科)卒業
ペット栄養学会・動物医療発明研究会
動物が大好きで、セキセイインコや文鳥、モルモットのほか、犬5頭や猫7頭の飼育経験あり。ペットと飼い主様の幸せのために記事の執筆を行っている。保有資格:ペット栄養管理士 家畜人工授精師(牛)など
おすすめ記事
-
2025.03.25
-
2025.03.25
-
2025.04.18
-
2025.06.25