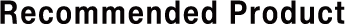オフィスの天井の種類│特徴やメリット・デメリット、天井高の影響

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
オフィスを計画するときの重要な検討要素のひとつが「天井」です。システム天井(後述)の登場によりバリエーションが広がり、デザイン性・施工性・コストといったさまざまな要望や条件に合わせて適切な天井を選べるようになりました。
そこでこの記事では、オフィスに用いられる天井の種類と特徴を紹介するとともに、オフィスに適した天井高について解説します。
オフィスの天井の種類と特徴
はじめに、オフィスの天井の種類とそれぞれの特徴について解説します。設計時の自由度の高さを求めるなら「在来天井」、施工性や将来に向けた柔軟性を意識するなら「システム天井」が適しています。
●在来天井(在来工法天井)
在来天井は、現場で組み上げた下地材に石膏ボードやロックウールなどの天井材を取り付ける在来工法による天井です。施工できる会社が多く、オフィス・病院・学校・官庁施設などで使われているポピュラーな天井といえます。
後述するシステム天井のように、モジュール(基本寸法)が決まっているわけではないので、設計の自由度の高さがメリットです。空調機器や照明などのレイアウトがシステム天井のモジュールにはまらない場合は、有力な選択肢になるでしょう。また、多くの天井材に対応できることから、デザインの幅が広がるということも設計者にとっては大きな魅力です。
一方で、施工した後は改造しにくいことがデメリットとして考えられます。空調機器や照明の移設にも大掛かりな工事が必要になる傾向があるので、将来的なレイアウト変更の可能性がある場合は留意しておきましょう。
●ライン天井(ライン型システム天井)

在来天井の施工の手間を低減するために登場したのが「システム天井」です。一定のモジュールで用意された下地材の枠組みに、空調機器や照明などをはめ込むようにセットすることで手軽に施工できます。なかでも、空調機器や照明などを直線上に配置するシステム天井を「ライン天井(ライン型システム天井)」と呼びます。
ライン天井のメリットは、システム天井のなかでも特に施工性が高いことです。後述のグリッド天井と比べてモジュールが大きく大判の板を使用できるため、短い期間で施工ができます。またライン天井の場合は、照明とデスクを平行に並べるオフィスレイアウトにすることで、デスクの照度を調整しやすくなり、働きやすいオフィスに近づけられます。
一方、モジュールが大きいという特徴から、細やかなデザインには向いていないことがデメリットのひとつとして挙げられるでしょう。ラインを見せるスタイリッシュな空間演出に適しています。
●グリッド天井(グリッド型システム天井)

「グリッド天井(グリッド型システム天井)」は、格子状に組まれた下地材に空調機器や照明などを組み込んでつくるシステム天井です。
モジュールが細かいため、設備機器のレイアウトが容易であり、将来的な移設・増設にも柔軟に対応できます。また、グリッドで区切られた天井材をそのまま点検口として使えるため、美しい見た目を損なうことなく天井裏のメンテナンス性を確保することが可能です。
多くのシステム天井に共通することですが、在来天井に比べると防音性(遮音性・吸音性)に劣ることがデメリットとして挙げられます。オフィスは集中して実務を行う場のため、音環境への配慮は必須になります。音環境にこだわるためにも、メーカーなどの専門家に相談しながら採用を検討するとよいでしょう。
システム天井の防音性を上げるためにも、天井材そのものに防音性に優れた製品を採用することをおすすめします。DAIKENの『ダイロートン』は吸音性のある天井材で、音の中でも特に耳障りな中・高音域を抑えてくれます。『ダイロートン』をシステム天井の天井材に使用することで、音が残響しにくくなるため、会話の聞き取りやすい快適なオフィス環境の実現につながります。
また、システム天井の吸音性の低さをカバーするための対策としては、吸音パネルの設置をおすすめします。DAIKENの『OFF TONE(オフトーン)』は、壁やパーテーション等に貼り付けることで吸音効果を期待できる製品です。豊富なカラーバリエーションを用意しているので、防音性能を高めつつ、おしゃれな空間を演出できます。
⇒吸音材で職場環境改善! WEB会議の質が向上する吸音の方法
●スケルトン天井

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
「スケルトン天井」とは、天井材を設置せずに設備機器やダクト、建物の躯体などを見せる天井です。もともとは音楽スタジオなどで多く使われていた天井ですが、デザイン性が人気を集め、美容院やカフェ、オフィスなどでも使用機会が広がっています。
スケルトン天井のメリットは、空間を広く見せられることです。天井材による上方向の閉塞感がなくなり、開放的な空間を演出できます。設備機器などが剥き出しの状態なので、メンテナンスをしやすいことも利点です。
一方でデメリットとして挙げられるのが、ホコリなどが気になる点です。設備機器や照明などにホコリが溜まると、通風や空調によりホコリが落ちてくることがあります。そのため、オフィスや飲食店といった清潔感が求められる部屋では、清掃を徹底する必要があります。
オフィスの天井高が与える影響
良好なオフィス環境をつくるうえで意識したいのが「天井高」です。働きやすい空間をつくるには、部屋の広さに応じた適切な天井高を設定することが大切です。ここでは、オフィスの天井高が仕事やオフィス環境へどのような影響を与えるのか説明します。
●仕事効率への影響
空間の広さは人の精神状態に大きな影響を与えるとされています。たとえば、部屋の広さ(横幅)に対して天井高が低すぎると圧迫感や閉塞感を与え、反対に天井高が高すぎると落ち着かなくなってしまうことがあります。不適切な天井の高さになることで、従業員がベストパフォーマンスを発揮できる精神状態から離れてしまう可能性が高くなるでしょう。
●オフィス環境への影響
天井高によるオフィス環境への影響も無視できないものです。わかりやすい例として、光環境について考えてみましょう。部屋が広いのに天井高が低い場合、窓際のデスクは自然光で明るくなりすぎ、部屋の奥(窓から離れた場所)は自然光が届かずに暗すぎるといった状況になります。デスクの照度にバラつきが生じるので、個別の照明などで対策する必要があります。
もうひとつの例として挙げられるのが温熱環境です。天井高が高いと暖かい空気が上部に留まりやすくなるので暖房効率が低下します。対策として、性能の高い空調機器やシーリングファンの導入が必要になります。一方で、天井高が低い場合には空気が循環しにくくなる傾向があるので、空調機器の吹出口を増やすといった工夫が必要です。
オフィスの天井の高さはどのくらいが良い?
最後に、オフィスに適した天井高について解説します。施主の要望やオフィスの使われ方に合わせて適切に設定しましょう。
通常のオフィスの天井高は「2.5~2.8m」に設定されるのが一般的です。一方で、超高層ビルのハイクラスなオフィスなどでは、フロア面積が大きいことや付加価値が求められることから、2.8mを超える天井高が設定されるケースが増えています。
さらに、近年リモートワークの推進が進んだことにより、オフィスに求められる機能や使われ方は多様化しています。オフィスの運用イメージを施主と共有し、フロア面積や働く従業員の数に合わせて適切に天井高を設定することが大切です。
また、天井高はオフィス建設のイニシャルコストや法への適合性にも影響を与えます。天井高を100mm上げるだけでも、オフィスフロアが30層あれば建物の高さが3mも高くなり、内外装、仮設費といったさまざまな面でコストが高くなります。場合によっては、建物の高さ規制に引っかかることも懸念されるので、慎重に検討しましょう。
オフィスの天井は適切な種類と高さ選びを

天井は、オフィス空間に大きな影響を与える要素です。システム天井の普及により、選択肢の幅が広がっているため、オフィスの用途やコスト、施工性などを考慮しながら意図した空間を演出できる製品を選びましょう。また、快適な空間をつくるには、天井高を意識することが大切です。部屋の広さに対する適切な天井高を設定し、働きやすい環境を目指してみてください。
DAIKENで取り扱っている『ダイロートン システム天井』は、省施工・省コストを実現するシステム天井です。吸音性に優れた天井材『ダイロートン』を使用しており、快適かつ集中して働けるオフィス環境づくりに役立ちます。ラインタイプとグリッドタイプの2種類を用意しているため、オフィスのデザインに合わせてお選びください。製品が気になる方は、下記のカタログをご確認ください。
「2024-25 ダイロートン システム天井」を資料請求する
また、施設設計・建材選びに役立つプロ向け情報サイト『D-TAIL』では、オフィスの設計に役立つ情報を提供しています。建材選びの課題解決にお役立てください。
おすすめ製品