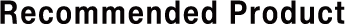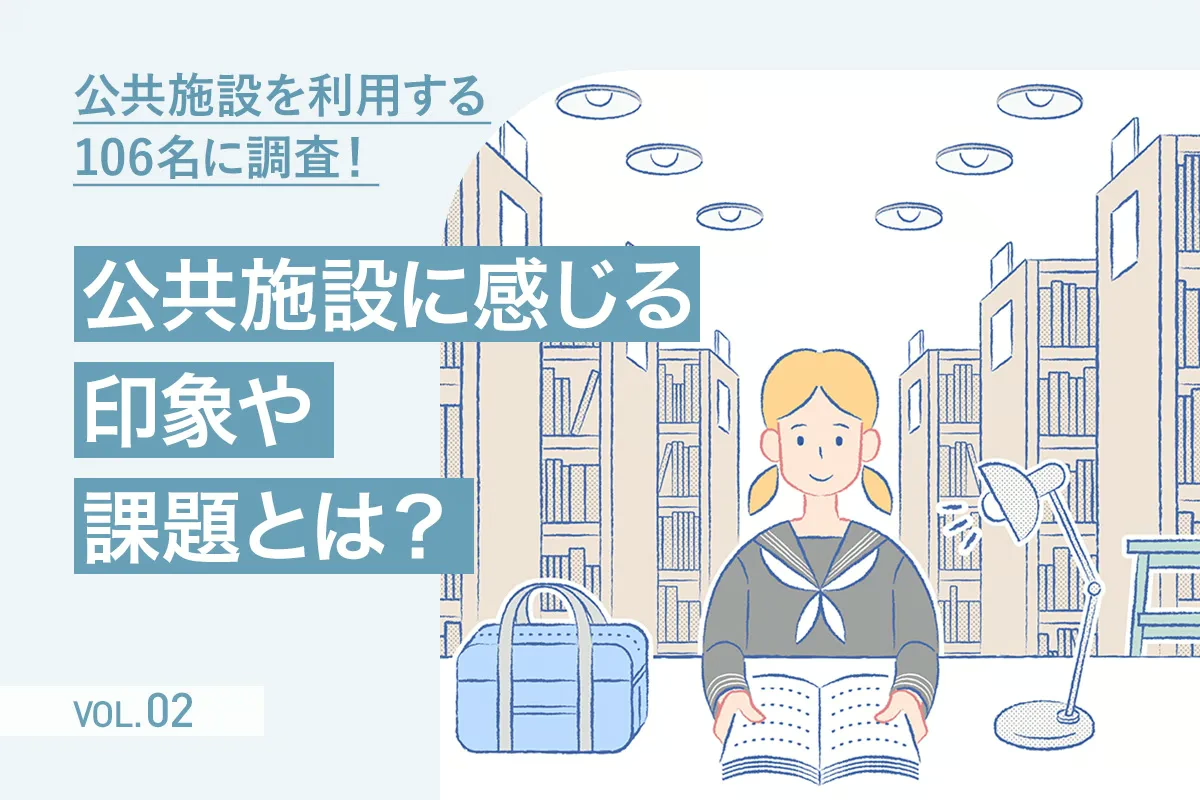美術館建築に求められることは?コンセプトの傾向や設計のポイント

美術館建築とは、芸術作品の展示、保存、鑑賞を目的とした施設を設計することを指します。美術館は単なる展示空間ではなく、機能性と美観を融合させることが求められる特別な空間です。来館者に快適な体験を提供しつつ、作品の保存環境にも配慮された設計にする必要があり、美術館建築には高度な建築技術や芸術的センスが詰まっています。
本記事では、美術館建築の考え方や必要な構成、設計のポイントまで幅広く解説します。
美術館建築の計画を立てる際の考え方と必要な構成
ここでは、美術館建築の計画を立てる際の考え方と必要な構成についてご紹介します。美術館特有のエリア構成について、大まかに把握しておきましょう。
●美術館の建築計画を立てる際の基本的な考え方
文化庁は美術館などの文化財公開施設に対して、下記の基準を示しています。
-
【文化財公開施設の基本的な考え方】
1.建築予定地の環境、建物の配置が文化財の保存・公開にふさわしいものであること。
2.建物は、耐火・耐震性能に配慮し、安全性を確保していること。
3.建物内の展示室、収蔵庫等の配置が展示、収蔵、管理等の面から機能的であり、かつ、十分な広さを確保していること。
4.展示室、収蔵庫等の設備が、適切な展示および保存環境を確保していること。
5.防火・防犯等の各設備が適切に配置されていること。
出典:「文化財公開施設の計画に関する指針」(文化庁)
この基準は、ギャラリーや保管される作品の安全性を確保して施設に対する信頼を高める目的で定められています。展示スペースや保管エリアの環境を適切に管理し、アート作品やコレクションを長期にわたり安全に保存できる設備設計が求められるのです。
●美術館のエリア構成
美術館のエリア構成は来館者が利用する「公開エリア」と、スタッフや業務目的の来訪者のみが利用する「非公開エリア」に分類されます。
公開エリアには、展示エリア・交流エリア・エントランスホール・受付・カフェ・ショップ・トイレ・授乳室などが含まれ、来館者が快適に過ごせるような空間が整備されています。
一方で非公開エリアには、調査研究エリア・収集保存エリア・空調機械室・搬出入口・トラックヤード・荷解場・運営事務所・警備員室・職員用トイレなどが設置され、主に業務運営や作品の管理・保存のためのスペースとなっています。
美術館建築のコンセプトに求められる傾向とは?
美術館建築に求められるものは、時代とともに変化しています。近年では作品展示に留まらず、交流し、学び、体験できる多機能な場としての役割が期待されているのです。
●地域文化との連携
近年では、美術館建築において地域文化との連携が重視されるようになっています。地域の歴史や文化を反映し、伝統工芸や自然景観を取り入れた建築デザインが注目を集めているのです。また、地域の文化交流の拠点としてワークショップ等が開催しやすい美術館設計が期待され、地域活性化への貢献度も高くなっています。
そして、地域の森林保全や林業の活性化に寄与する取り組みとして、地域産材を建材に活用する事例も見られます。地域産材を壁材や床材、造作材に使用することで、地域の資源を生かした持続可能な美術館建築が進められているのです。
-
▼地域産材を活用した美術館の例
鳥取県立美術館
DAIKENでは、突板の風合いと質感が魅力の不燃壁材『グラビオUS』や、土足対応WPCフローリングの『コミュニケーションタフ バイオリーフ DW』、空間に高級感を演出する不燃突板造作材『グラビオルーバーUS』などで地域産材を活用可能です。なお、地域やその年の気候などにより、適した木材が確保できない場合があります。対応可能な樹種や数量、納期等について、詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。
参考:「美術館・博物館の特徴的な取組に関する調査事業」(文化庁)
●環境と共生する建築
近年、環境への配慮が求められる中で、自然素材の利用や省エネルギー設計を取り入れたエコロジカルな建築への移行が環境省によって推進されています。そして美術館においても、環境と共生する建築設計が重要視されるようになっているのです。これにより持続可能な建築が広がり、美術館の敷地自体が環境保護のシンボルとなるケースもあります。また周囲の景観との調和を図り、地域の自然や都市環境と美しく一体化するような美術館のニーズも高いです。
参考:「建築物木材利用促進協定について」(環境省)
●体験型の空間設計
近年のミュージアムや現代美術館では、来館者が主体的に参加できる体験型の空間設計が求められています。例えば、アート作品と来館者がより深く融合するようなデジタル技術を活用した展示や企画が催されるようになってきています。
また多様な用途に対応できる広場やギャラリー、アトリウムなどの空間も設けられ、イベントに柔軟に対応できる設計も重要視されています。ガラスを用いた外観やファサードが庭園と調和し、敷地全体がアート作品の一部として体感できる美術館の構築も人気です。
美術館建築のポイント
ここでは、主な美術館建築のポイントをご紹介します。特殊な空間だからこそ、建材選び等の工夫が重要となります。
●防音性の高い建材を用いる
美術館建築において、防音性の高い建材を用いることは非常に重要です。特に現代の美術館やミュージアムでは、展示されている美術作品やアート作品に集中できる静寂な環境が求められます。そのため美術館を設計する際には、足音や話し声が響かないように防音性を高める工夫が必要になるのです。
例えば軽い足音を防ぐために、防音効果の高い床材を使用することが一般的です。また壁面や天井に吸音パネルを設置することで、音の反響を抑えます。これにより展示エリアやギャラリーでは静けさが保たれ、アート作品をじっくりと鑑賞できるのです。こうした防音対策は、内部空間の快適さを支える重要な要素となります。
美術館建築での具体的な防音対策としては、下記の製品がおすすめです。
・コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ DW4/FW4:ハイレベルな防音性能と土足対応を兼備した高性能フローリング。
・ダイロートン:音の響きを抑える施設向け天井材。バリエーション豊富で用途に合わせて選択可能。
・KIN TONE:正方形や円形の天井用吸音パネル。ビビットかつカラフルな色味で、遊び心のある楽しい空間に。
・OFF TONE:壁面に取り付けられる吸音パネル。豊富な色柄を揃えており空間のアクセントとしても。
●来館者に配慮した動線をつくる
美術館建築で展示鑑賞体験の質を高めるためには、来館者に配慮した動線設計が重要です。例えば、来館者がスムーズに展示を鑑賞できるようにするため、視覚的なガイドを設けることが効果的です。これにより、来館者は迷うことなく展示エリアやアート作品を楽しめます。さらにバリアフリーやユニバーサルデザインを採用することで、より多くの方が美術館を利用しやすくなります。
動線設計の工夫は、混雑の軽減にも寄与します。例えば広場やアトリウムなどのオープンスペースを活用して来館者の流れを分散させることで、展示エリアでの過密を防げます。
●展示を邪魔しないデザインを採用する
美術館の展示室内のデザインは、展示物を引き立てることが主眼となります。そのため、内装はシンプルなデザインや落ち着いた色調にすることが重要です。これにより視覚的な焦点が美術作品やアート作品に自然と向かい、作品の魅力を最大限に引き出せます。
また、展示物を主体とした照明計画も大切な要素です。適切な照明器具を選ぶことで、来館者に美術品の質感や色合いを忠実に伝えられるようになります。照明の設置位置や明るさ、演色性などを考慮し、展示物を引き立てるように設計しましょう。
例えば、展示物を引き立てる照明には、明るく均一に、光源や展示物がガラスに映り込まない演色性の高い照明が必要です。展示品によって推奨照度はJISで定められており、光源と視線の関係は反射角を考慮して決めるほか、一般社団法人照明学会が作成した「美術館・博物館の照明技術指針」をガイドラインとして設計されます。
美術館建築に適した「建材選び」が大切
近年の美術館は、学びや体験といった多目的な利用を想定した建築が求められるようになっています。その中で「建材選び」は非常に重要です。音環境にしっかり配慮することで、静寂な環境で美術作品やアート作品に集中できる空間を提供できます。具体的な施工事例を確認したい方は、下記の事例集をご覧ください。
美術館建築に役立つ事例集「2024 公共商業施設 施工事例集」を請求する
またプロの建築家向け情報サイト「D-TAIL」では、設計に役立つ様々なヒントを確認できます。興味のある方はぜひご登録ください。
おすすめ製品