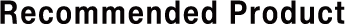カウプ指数・ローレル指数で子どもの肥満度をチェック コミュニケーション力を高める運動で肥満解消!

保育園や幼稚園・学校などの教育機関で子どもたちと関わっている方にとって、子どもの健康管理はとても大事です。子どもの健康といっても様々ですが、肥満傾向児の割合が増加している昨今、現場でのサポートはさらに重要視されています。ここでは、子どもの肥満度をチェックする方法や、肥満を解消する運動法・環境づくりについてご紹介します。
カウプ指数とローレル指数とは
保育や教育の場で子どもの発育は常に気になりますが、見た目だけでは分かりにくいものです。子どもの肥満度を測る方法として、身長や体重を使った計算式で算出できる「カウプ指数」と「ローレル指数」というものがあります。
子どもの発育が正常かどうかを調べるため、カウプ指数とローレル指数のさらに詳しい内容や、計算方法を見ていきましょう。
●カウプ指数とは
カウプ指数とは、生後3カ月から5歳までの乳幼児に用いられる体格指数です。計算式は下記の通りで、数値と年齢によって判定します。
カウプ指数=体重kg÷(身長mの2乗)×10
| カウプ指数 | 正常範囲 |
| 乳児 | 16~18未満 |
| 満1歳 | 15.5~17.5未満 |
| 1歳6ヶ月~満2歳 | 15~17未満 |
| 満3歳~満5歳 | 14.5~16.5未満 |
※出典:福祉教科書 保育士完全合格テキスト 上 2015年版(翔泳社)
●ローレル指数とは
ローレル指数とは小学生の児童や中学生の生徒に用いられる体格指数です。計算式は下記の通りで、計算から導き出される数値により判定します。ローレル指数=体重kg÷(身長mの3乗)×10
| ローレル指数 | 判定 |
| 100未満 | 痩せすぎ |
| 100以上~115未満 | 痩せ気味 |
| 115以上~145未満 | 標準 |
| 145以上~160未満 | 太り気味 |
| 160以上 | 太りすぎ |
※出典:長崎県長与町「長与町健康増進計画(第2次 健康ながよ21) 6取り組む目標」
子どもの肥満について

●肥満傾向児の割合は増加傾向
文部科学省は、満5歳から17歳までの幼児・児童と生徒を対象に「令和2年度学校保健統計調査」を実施。肥満傾向児の割合は増加傾向という発育状態調査結果が出ました。最も肥満度の割合が高かった年齢は、10歳の男子「14.24%」、10歳の女子「9.47%」です。
なお、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により調査時期が例年と異なるため、単純な数値の比較はできないと記されています。しかし、肥満傾向児が増えているという事実は教育の場において心に留めておくべき事項と言えるでしょう。
●子どもの肥満の原因
子どもの肥満の原因として、「食生活」「運動不足」「生活習慣の乱れ」の3つが考えられます。
・食生活……食べた量のエネルギー、カロリーが運動によって消費される量よりも多い、食事のバランスが悪い、朝ごはんを食べない、早食い、脂っこい食事やファストフードが多い、ジュースや清涼飲料水の水分補給が多い
・運動不足……塾や習い事が多く体を動かす機会が少ない、遊びは室内でスマホやゲームが多い、車での移動が多い
・生活習慣の乱れ……夜更しをする、睡眠時間が短い、ストレスを溜める
令和3年度にスポーツ庁が国公私立の小学校5年生と中学校2年生を対象に行われた「全国体力・運動能力、 運動習慣等調査」の結果で、体育の授業を除いた児童生徒の運動時間が減少していて、特に男子が顕著だという事が判明しています。また、合計点は令和元年度調査と比べて小・中学生の男女ともに低下したという概要が記されています。
スポーツ庁は、低下の主な原因としてゲーム・スマートフォン・テレビの視聴時間が増加したことや、体育の授業以外で体力を向上させる取り組みが減少したことと考えています。
この調査結果から、運動不足は子どもたちの体に大きな影響を及ぼしていると言えるでしょう。
●子どもの肥満による影響
肥満による子どもへの影響は大きく、動脈硬化・高血圧・肝障害・睡眠時無呼吸などにつながる恐れがあります。また、腰・股関節・膝などに負担もかかることも懸念されます。
こうした影響は身体面だけでなく、自尊心の低下やいじめによる心の不調を引き起こすことも見逃せません。
加えて幼少期の肥満傾向は成人肥満に移行しやすくなります。なぜなら、子どもの頃の生活習慣が定着しているからです。成人になってから生活習慣を変えることはなかなか難しく、後に成人病や生活習慣病の2型糖尿病・心筋梗塞などを患う可能性も高くなってしまいます。
-
―カウプ指数・ローレル指数・子供の肥満に関する記事―
・子どもの肥満予防におすすめの外遊びと欲しい設備 カウプ指数やローレル指数にも注視を
・肥満度チェックで子どもの健康管理! 肥満度計算と個別指導時のプライバシー対策
コミュニケーション力を高める運動で肥満を解消する

●コミュニケーション力を高める運動とは
子どもの肥満を予防するためには食事や生活習慣はもちろんのこと、コミュニケーション力を高める運動も有効な手段です。コミュニケーション力を高める運動とは、人と関わりながら体を動かすことで、運動力を高めるだけでなく、人と人とのコミュニケーションの基本を学ぶ事も出来ます。子どもにとって一人で定期的な運動を行うことは難しいため、子どもの運動習慣を作るためには人と対話しながら体を動かすことが重要です。
コミュニケーション力を高める運動は、チームで行うスポーツがイメージしやすいですが、保育園や幼稚園に通う小さな子どもたちにとっては、鬼ごっこ・ボール遊び・散歩なども十分な運動と言えるでしょう。
●子どもたちが安心して運動できる環境
子どもたちが楽しく、安全に運動を楽しむためには、開放感のある広い場所やホール・体育館などが必要です。
また、歩行が安定しない小さな子ども達が動き回ることを想定して、畳のスペースがあると安心です。カビやダニ、色あせに強く、耐久性・メンテナンス性に優れた製品もあり、不必要なときは簡単にしまえる置き畳も便利です。
子どもの肥満を解消するための糸口として、運動に適した環境づくりが重要になりますが、その際に欠かせないのが安全性の確保と子ども目線の空間設計です。子どもたちにとって安全で子供らしく遊べる空間づくりについて、次の記事で紹介しています。
⇒「こどもがこどもらしくいられる空間づくり~幼保施設の設計」
保育園の室内で可能な運動遊びについて、下記の記事でもまとめていますので、こちらもチェックしてみてください。
⇒「室内で楽しめる運動遊び! 転びやすい子どものための身体づくり」
おすすめ製品