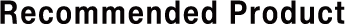軒天を木目にするメリット・デメリットは?採用時の注意点や施工事例

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
目次
軒天は、建物の外観デザインに影響する重要な部分であり、どのような素材の建材を選ぶかによって印象が大きく変わります。中でも木目の軒天は、温もりのある雰囲気や高級感を演出できることから、住宅・商業建築等で採用が進んでいます。一方で、耐久性や防火性、地域の景観条例など、意匠以外にも配慮すべき点は少なくありません。
本記事では、軒天に木目を用いるメリットとデメリットを整理し、建材選定時に押さえておきたい設計上のポイントや施工事例を解説します。
※「もくめ」には「木目」と「杢目」がありますが、本記事では「木目」で統一しております。
軒天に用いられる主な素材
まずは、軒天材に用いられる素材の種類について解説します。主に木材・合板、金属、不燃材の3種類が広く使用されています。
●木材・合板
木材や合板を使った軒天材は、建物に自然の温もりを与えます。特に木造建築物との相性が良く、意匠に統一感を持たせることができます。合板は複数の板を薄く加工して接着した材料で、強度とコストのバランスに優れているのが特徴です。
ただし、本物の木を使う性質上、湿気や水分に弱いため、屋外使用時には防腐処理や防カビ塗料を用いて塗装するなどの保護措置が欠かせません。定期的なメンテナンスも求められるため、設計段階から維持管理を視野に入れることが大切です。
●金属
ガルバリウム鋼板をはじめとする金属材を用いた軒天材は、モダンな意匠に適した建材です。金物ならではのシャープさによりスタイリッシュな印象を与え、耐久性や耐火性にも優れています。軽量なため施工性も高く、メンテナンスの手間を抑えられる点も特徴です。
一方で表情が無機的になりやすいため、他の素材とのバランスを考慮した設計が求められます。
●不燃材
ケイカル板やセメント板などの不燃材を用いた軒天材は、防火・準防火地域での軒天に広く採用されています。化粧シートや塗装によって木目調やリブ柄などを表現した製品が多く、カラーバリエーションなどの意匠性と法規制への適合を両立できる点が強みです。住宅・非住宅を問わず採用可能なため、用途や地域の要件に応じた柔軟な設計が可能です。
軒天に木目を取り入れるメリット
軒天に木目を取り入れると、建物の印象を柔らかく整え、周囲の環境と調和した意匠を実現できます。ここでは、木目の軒天に期待できるメリットを解説します。
●空間に温もりと落ち着きを与える
木目のある軒天は視覚的に穏やかな印象を与えるため、建物のファサードにおいて柔らかな雰囲気を演出するのに適しています。
特にエントランスまわりやアプローチ部分に木目を取り入れることで、無機質になりがちな外観に温かみが加わります。来訪者に与える印象や利用者の心理的な快適性の向上も期待でき、建物の顔としての安心感や親しみのあるイメージを与えられるでしょう。
●経年変化を楽しめる
天然木を使用した場合、時間とともに木肌の色味や質感が変化し、自然素材ならではの味わいが深まっていきます。この経年変化により、建物の表情に個性や深みをもたらし、より印象的な外観になっていくでしょう。適切なメンテナンスを施すことで、古びるのではなく、本物の木材が成熟していく美しさを持たせることが可能です。
軒天に木目を採用する際の注意点
軒天に木目を取り入れると、より魅力的なデザインを演出できますが、法規制や地域性、維持管理の観点から慎重な検討が求められます。ここでは、設計時に留意すべきポイントを解説します。
●法規制に適合した建材を選ぶ
防火・準防火地域では、建築基準法により軒裏に不燃材料の使用が求められるケースがあります。特に延焼のおそれがある部分に該当する軒天では、階数や建築面積に応じて、耐火構造や準耐火構造が義務付けられています。
したがって、天然木そのものを使用するのではなく、不燃材に木目調の化粧シートを貼付した製品や、不燃認定を取得した木材を用いる必要があります。製品ごとの認定番号や性能表示を確認し、地域条例とも照らし合わせた上で適切な建材選定を行うことが重要です。
参考:
「建築基準法 第六十一条」(e-Gov 法令検索)
「建築基準法 第六十二条」(e-Gov 法令検索)
●メンテナンス性と耐久性に配慮する
天然木を使用する場合、経年劣化や湿気による腐食、塗膜の劣化といった懸念があります。風雨にさらされやすい軒天では、素材の耐候性が特に問われます。そのため、定期的な塗り直しや清掃などの維持管理を前提に、採用の可否を判断することが必要です。軒天のボードと見切やシーリングの耐久性も異なるため、軒天全体を含めて検討してください。
一方で、木目調の化粧板やアルミ製のラッピング材などは、見た目が木目でありながらメンテナンス性に優れており、コストと手間を抑えたいケースでは有効な代替手段となります。
●景観条例や地域性との整合性を考慮する
伝統的な街並みや景観形成重点地区などでは、外観色や素材に関する規制が設けられている場合があります。
木目柄であっても色味が濃すぎたり、周囲の建築群と色合いが調和しない建材を選んだりすると、指導を受けたり設計変更を求められたりするかもしれません。特に歴史的建造物が多い地域では、行政からガイドラインや指定色の一覧が提示されているケースもあるため、設計の初期段階で規制の有無や内容を確認しておきましょう。
地域性を尊重した建材選びが、周辺環境との調和の取れた設計につながります。
参考:「京の景観ガイドライン 建築デザイン編」(京都市情報館)
木目柄の軒天井材『ダイライト軒天30』
DAIKENでは、木目の風合いを活かしながら、防火性にも配慮した軒天井材『ダイライト軒天30』を取り扱っています。
本製品は不燃材である『ダイライト』を基材とし、その表面にリアルな木目柄の化粧シートを施すことで、不燃性能と天然木のようなナチュラルな仕上がりを実現しています。準防火地域にも対応できる不燃材料認定を取得しており、建築基準法上の要件を満たした設計が可能です。
厚さは12mm、重量は1枚あたり約12kgと扱いやすく、化粧シート品や現場塗装品など、施工現場に応じたバリエーションも揃っています。
外観デザインに木目を取り入れつつ、耐久性や施工性にも配慮したい場合に、有効な選択肢となる製品です。
軒天に木目を採用した施工実例
木目の軒天は、建物の外観に温もりと洗練さをもたらすデザイン要素として、さまざまな施設で採用されています。ここではDAIKENの軒天井材を採用した事例を紹介します。
※製品は採用当時のものです。生産中止品も掲載されている場合があります。
●船橋競馬場/千葉県

【使用製品】
軒天井材:ダイライト軒天30<ティーブラウン柄>

【使用製品】
軒天井材:ダイライト軒天30<トープグレー柄>
●北上市立東桜小学校 校舎・体育館/岩手県

【使用製品】
軒天井材:ダイライト軒天羽目板<ティーブラウン柄>
設計:有限会社 加藤設計
校舎施工:千田工業株式会社・株式会社 斎藤工務所JV
体育館施工:株式会社 千葉匠建設・鈴久建設株式会社特定共同企業体
●柳澤クリニック/愛知県

【使用製品】
軒天井材:ダイライト軒天羽目板<ダルブラウン柄>

【使用製品】
軒天井材:ダイライト軒天30<ティーブラウン柄>
軒天に木目を取り入れて外観の意匠性を高めよう
軒天に木目を取り入れることで、建物外観に温かみや上質感をもたらし、来訪者や利用者に安心感を与える効果が期待できます。木目の軒天は意匠性が高く、自然素材ならではの風合いを楽しめるという魅力もあります。ただし、使用する素材によっては、耐久性やメンテナンス性、防火性に注意が必要です。
設計にあたっては、地域の法規制や景観ガイドラインを把握したうえで、必要に応じて木目調の不燃材を選ぶなど、性能と意匠性を両立させた建材の選定が求められます。特に防火地域・準防火地域では、不燃材料であることが必須となるため、認定製品の使用が基本となります。
軒天材の建材選定で悩むようであれば、ぜひ以下のカタログをご覧ください。様々な建材を知ることで、設計の引き出しを増やせるでしょう。
「2025-26総合カタログ[公共・商業施設向け製品]」を資料請求する
また、施設設計では軒天材に限らず、様々な建材を比較検討していくことになります。プロ向けの情報サイトを活用し、最新の情報に触れておきましょう。
おすすめ製品