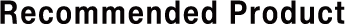バリアフリーデザインの基本概念とは?主な基準やデザインの実例

バリアフリーデザインとは、生活における物理的・心理的な障害(バリア)を取り除き(フリーにする)、特に高齢者や障がい者にとって快適な生活環境の実現を目指す設計の考え方です。具体的には、段差の解消や手すりの設置、視覚や聴覚に障がいを持つ人のための設備整備などが挙げられます。
この記事では、バリアフリーデザインの基本概念から、ユニバーサルデザインとの違い、さらに公共施設におけるデザイン例まで解説します。
バリアフリーデザインの基本概念
建築におけるバリアフリーデザインの基本的な考え方や基準、混同されやすい「ユニバーサルデザイン」との違いについて解説します。
●建築分野におけるバリアフリーとは
建築におけるバリアフリーでは、高齢者や障がい者が安全に移動し、快適に生活ができるように環境を整えます。たとえば、段差の解消や手すりの設置、滑りにくい床材の採用や通路幅の十分な確保などが挙げられます。建築士は物理的・心理的な障壁が生まれないように配慮して、設計を行うことが大切です。
参考:『知っていますか?街の中のバリアフリーと「心のバリアフリー」』(政府広報オンライン)
●バリアフリーデザインとユニバーサルデザインの違い
バリアフリーデザインとユニバーサルデザインは、どちらも快適に生活できる環境を目指す設計概念です。ただし、アプローチや対象者の捉え方に違いがあります。
●バリアフリーデザイン
主に高齢者や障がい者に焦点を当て、日常生活や社会生活を妨げる障害を取り除くことを目的としています。たとえばスロープや手すりの設置、昇降リフトの導入などにより、スムーズな移動を助け、安全性を高めます。
●ユニバーサルデザイン
年齢・性別・国籍・障がいの有無などにかかわらず、誰もが使いやすい環境づくりを目指す考え方です。対象者を特定せず、多様な人々の利用を想定した設計が求められるのが大きな特徴です。また、ケガや病気といった一時的な体の不具合や、災害などによる特殊な環境下においても、対応できるように配慮して設計を行います。
参考:「バリアフリーとユニバーサルデザイン」(総務省)
●建築物におけるバリアフリーデザインの基準とは
2006年に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)が制定され、交通機関や建築物、道路におけるバリアフリー化が強化されました。この法律は、従来のハートビル法と交通バリアフリー法を統合・拡充したものです。施行以降も、時代のニーズに合わせて改正が続けられています。
●バリアフリー化の対象建築物
バリアフリー法の対象となる建築物には、「特定建築物」と「特別特定建築物」の2つがあります。特定建築物とは、多数の人が利用する建物を指します。一方、特別特定建築物は不特定多数、または主に高齢者・障がい者が利用する建物が該当します。
特定建築物・特別特定建築物の一例
特定建築物 |
特別特定建築物 |
|---|---|
学校 |
特別支援学校 |
病院または診療所 |
病院または診療所 |
老人ホーム・保育所・身体障害者福祉ホームなど |
老人ホーム・身体障害者福祉ホームなど、 |
博物館・美術館・図書館 |
博物館・美術館・図書館 |
ホテルまたは旅館 |
ホテルまたは旅館 |
卸売市場または百貨店・マーケットなど |
百貨店・マーケットなど |
●バリアフリー化の基準
バリアフリー法では、「建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動等円滑化誘導基準」という2つの基準が設けられています。建築物移動等円滑化基準は、高齢者や障がい者が円滑に利用するために必要な構造・配置を求めた基準です。一方、建築物移動等円滑化誘導基準は、さらに高い快適性を目指し、より望ましい構造・配置が求められます。
不特定多数の人や、高齢者・障がい者などが利用する床面積が2,000平方メートル以上の特別特定建築物では、最低限のバリアフリー化が求められ、建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けられています。一方、2,000平方メートル未満の特別特定建築物や特定建築物に対しては、努力義務が課されます。
●高度なバリアフリー化により認定を受けるメリット
建築物移動等円滑化誘導基準等に適合する、より高度なバリアフリー化を実現した特定建築物は、容積率の緩和や税制上の特例措置など、複数のメリットを得られます。
利用できる制度 |
具体的なメリット |
|---|---|
表示制度 |
シンボルマークを表示することで、施設の利便性を可視化できる。 |
容積率の特例 |
高齢者や車いす利用者への配慮を目的としてトイレや廊下などの面積を増やす場合、延べ床面積の1/10を限度に容積率の計算から除外できる。 |
税制上の特例措置 |
特定建築物については、所得税や法人税の割増償却が可能になる。 |
補助制度 |
人口5万人以上の市等における、不特定多数が利用する公共施設や高齢者・障がい者が利用する施設において、整備費が助成される。 |
参考:
「バリアフリー法の概要について(建築物関連)」(国土交通省)
「【文部科学省】公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する取組について」(国土交通省)
「建築物のバリアフリー化に係る制度の概要について」(国土交通省)
「特定建築物及び特別特定建築物の範囲」(国土交通省)
公共施設におけるバリアフリーデザインの例
公共施設では、多様な人々が安心して利用できる、バリアフリーデザインの導入が求められています。代表的な例を見ていきましょう。
●ゆとりのある通路
車いすや歩行補助具を使用する人が安心して移動できるよう、通路幅は十分確保することが求められます。建築物移動等円滑化基準では幅120cm以上、より高度な建築物移動等円滑化誘導基準では幅180cm以上の確保が必要です。また、滑りにくい加工を施した床材や、衝撃吸収効果のある素材を使用することで、転倒リスクを軽減できます。たとえば、DAIKENの『コミュニケーションタフ』は滑りに配慮した床材で、良好な歩行感を生み出します。
●手すりの設置
階段や廊下・スロープといった移動経路には、手すりをできるだけ途切れないように設置する配慮が求められます。また手すりの上端には、点字や文字による案内を表示し、現在地や誘導先が確認できるように配慮することも大切です。建築物移動等円滑化基準では片側に、より安全性に配慮した建築物移動等円滑化誘導基準では両側に、手すりの設置が求められます。
●車いすも通りやすい出入口
車いす利用者がスムーズに移動できるよう、居室などの出入口には段差を設けず、幅を広めに設定し、さらに出入口の前後にも十分なスペースを確保する必要があります。出入口の幅の基準は、建築物移動等円滑化基準で80cm以上、建築物移動等円滑化誘導基準で90cm以上です。また、出入口の扉は、車いす利用者でも安全に開閉できる構造が求められます。DAIKENの『おもいやりドア』は、自動でゆっくりと扉が閉まる自閉機能や、扉を全開にしたまま維持できる機能を備えています。さらに指挟み防止にも配慮しているため、出入りの際の安全性を向上させることが可能です。
参考:「バリアフリー法の概要について(建築物関連)」(国土交通省)
●『おもいやりドア』の施工事例
DAIKENの『おもいやりドア』が採用された実例として、北海道の介護付ホーム「ふれあいの里 藍華(あいか)」を紹介します。
開口幅が広い扉が必要な高齢者施設では、材料や金物に強度や耐久性が求められます。『おもいやりドア』は、「木材特有の狂いが少ない」「スムーズに開閉できる」「耐久性が高い」といった機能が備わっていることから、採用につながりました。また、標準仕様のバリエーションが豊富にあるため、機能性とデザイン性を両立でき、快適な高齢者施設の実現につながりました。


-
実例の詳細は、以下のリンクからご覧ください。
▼採用製品をチェック
介護付ホーム ふれあいの里 藍華
▼採用に至った経緯をチェック
耐久性に優れた『おもいやりドア』で入居者も職員も快適な高齢者施設に
「●『おもいやりドア』の施工事例」の内容は、上記記事の要約です。
バリアフリーデザインの普及で快適な社会に
バリアフリーデザインの採用は、高齢者や障がい者はもちろんのこと、多様な人々が安心して暮らせる社会の実現につながります。DAIKENでは、バリアフリーデザインを叶えるためのさまざまな製品を取り扱っています。詳細は、以下のカタログをご覧ください。
「2024年おもいやりシリーズ新製品・新対応のご案内」を資料請求する
また、最新の施設設計や建材情報については、以下のサイトにご登録いただくと、具体的な事例も含めてご覧いただけます。登録は無料ですので、気になる方は登録して情報収集にお役立てください。
おすすめ製品