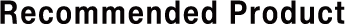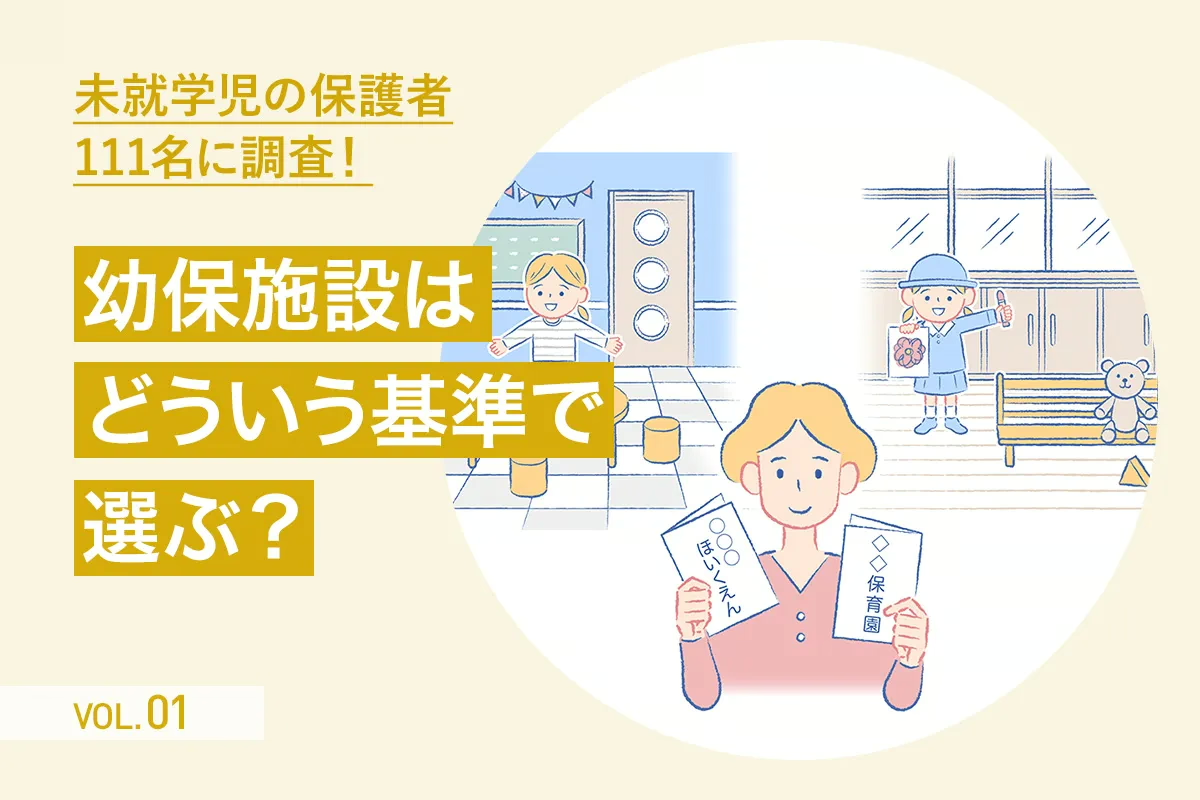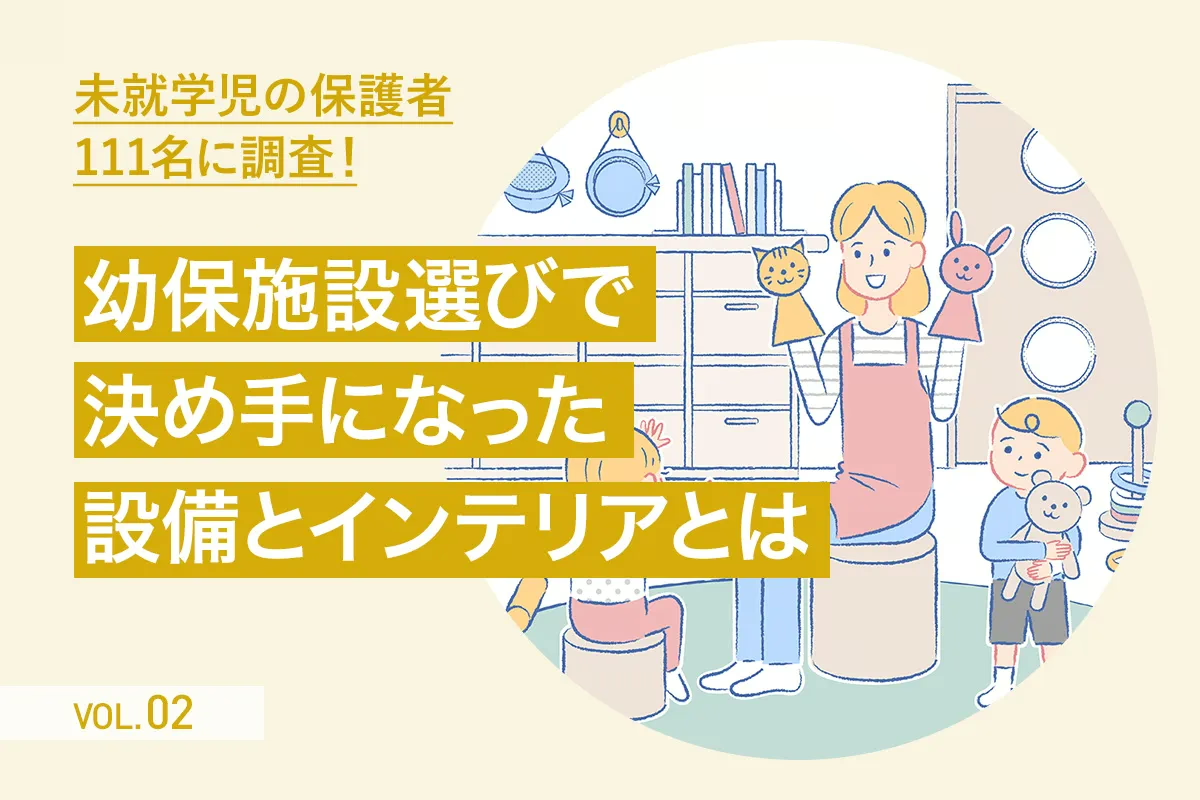待機児童問題の現状は? 保育士不足を解消するために施設としてやっておくべきこと

一時期は大きな社会問題だった保育園の待機児童問題。現在は大幅に解消されたといわれていますが、未だに解決していない地域や、隠れ待機児童の問題もあるようです。一方、保育士不足も以前から問題となっており、保育業界では人材確保の競争が激化しています。少子化が進行する中で施設を継続運営していくにためは、保育園が保護者だけでなく保育士にとっても魅力的な施設であることが大切です。本記事では、待機児童問題と保育士不足の現状や、保育士の負担を減らす施設の環境づくりをご紹介します。
待機児童は本当に減っている?

待機児童は、保育所の利用資格があって入所申し込みをしているものの、利用できていない未就学児です。保育が必要な子どもがいるにもかかわらず、保育園を利用できずに育休を延長せざるを得ない保護者も増えています。また、待機児童問題が原因で仕事に復帰することが難しくなり、保護者が退職を選択しなければならず、結果的に家計が圧迫されることもあります。
厚生労働省が実施した調査によれば、直近の待機児童数は2017年の2万6081人がピークでしたが、2023年4月時点では過去最少の2680人となっています。一時は社会問題となっていた待機児童がピーク時の約10分の1まで減少したという結果は大きな進歩といえるでしょう。
※出典:厚生労働省「令和5年4月の待機児童数調査のポイント」
待機児童が減少した理由としては、「認定こども園の増設」「0~2歳児の受け入れ施設の拡充」「保育士の処遇改善」など、国によって様々な取り組みが行われたことが挙げられます。
とはいえ、全国的なレベルで解消されたわけではなく、現在も都市部を中心に待機児童は存在します。中でも沖縄県は待機児童が400人を超えており、まだまだ子どもが保育園に入れずに悩んでいる家庭は少なくありません。さらに、共働き世帯や核家族が増加していることから、待機児童を解消させるための取り組みは今後も必要なこと予想されます。
隠れ待機児童問題とは

待機児童は国や自治体の取り組みなどで大幅に減少しましたが、それとは別に隠れ待機児童という問題も残っています。
隠れ待機児童というのは希望の認可園などに入園できていないにもかかわらず、国や自治体の判断で待機児童としてカウントされない子どものことです。その理由としては「特定の園に入園を希望している」「保護者が求職活動を中止している」などが挙げられます。
例えば、入園できる保育園があっても、「兄弟で同じ園に通わせたい」「なるべく早い時間から開園している保育園を選びたい」など、特定の保育園を希望している保護者もいるでしょう。このように、保育園を利用したくても預けられない事情があって育休を延長している家庭の子どもは待機児童に含まれません。また、保護者が求職活動を中断してしまうと、その子どもには保育の必要性が認められなくなり、隠れ待機児童となってしまいます。
隠れ待機児童問題を解消するためには、保護者のニーズに合った施設を増やす必要があります。保護者が通わせたいと思えるような保育園が増えれば、隠れ待機児童問題の解消も期待できるでしょう。さらには保育園側にも施設の質を高めたり、安心して預けられる環境を整えたりする努力が欠かせません。
深刻化する保育士不足

しかし、待機児童の数は減少しているものの、保育施設の慢性的な人手不足は続いています。保育資格の取得者数は年々増加しているのですが、実際に保育士として働いている人が非常に少ない現状があり、理由として過剰な業務負担や待遇の悪さなどが考えられます。
保育士の業務内容は、子どもたちの見守り以外にも行事の企画、安全・衛生管理、保護者対応など多種多様です。そのため、保育士の仕事が好きで働いていたとしても、家庭と両立できずに離職したり、収入を考えて異業種転職を検討したりする人も少なくありません。したがって、待機児童問題は保育施設が増えても保育士不足が続く限り本当の意味で解決されないでしょう。
今後は少子化に伴って定員割れで閉園を余儀なくされる園の増加も予想されますが、保育の質を維持しながら向上させていくためにも、人手不足を解消することは必須といえます。
保育士不足の解決策は? 国と自治体の取り組み

保育士不足の解決に向けて、国や自治体は様々な対策を講じています。例えば、保育士資格を持たない「保育補助者」の雇用を推進したり、短時間勤務の保育士が活躍できる場を整えたりすることです。新たな人材を確保する取り組みによって保育士の負担を減らし、離職率を低下させることを目的としています。
また、就職支援を行う「保育士・保育所支援センター」の機能強化にも力をいれています。このセンターでは保育士の資格取得を目指す人や、資格はあるものの保育所で働いていない潜在保育士の就職をサポートしています。その内容は就職先の紹介や見学日程の調整に加え、再就職に不安を感じている保育士の相談に応じることです。こうしたサポート機関は各自治体に設置されているため、地域に根差した支援を期待できるでしょう。
離職を防ぐためには、保育士が働きやすい環境を整えることも欠かせません。そのため、保育所の勤務環境を改善する「アドバイザーによる巡回支援事業」の拡充も行われ、業務の負担軽減や働き方の見直しを促して働きがいのある職場の実現を目指しています。
保育士が安心して働くためには、賃上げや家賃補助など、金銭面の改善も重要です。国はこれまで賃金向上のために待遇改善を行ってきましたが、保育士の賃金は一般的にわかりにくいという課題がありました。なぜなら、待遇改善の費用は園の裁量によるところが大きく、保育士への配分が一律ではないからです。
そこで、国は都道府県に対し、保育士等キャリアアップ補助金の交付を受けた施設に「モデル賃金」の公開を求める方針を固めました。将来の給与額をイメージしやすくするモデル賃金は、保育士が就職先を検討する際の参考となります。さらに、今後は待遇を改善するための予算が適正に使われているのか検証できるように、保育所等の財務情報や職員の給与額を都道府県に報告することを義務化する方針です。新制度のスタートは、2025年4月を目指しています。
各自治体が独自に行う「保育士宿舎借り上げ支援事業」は、家賃負担を減らすための取り組みです。宿舎を借り上げる費用の全額または一部を自治体が負担すれば、安定した生活を送れる保育士が増えます。家賃補助制度を導入する保育所もあり、就職先を選ぶ際に判断基準の一つとなっています。
保育士が働きやすい環境づくりを

保育業界では保育士不足による人材の確保競争が激化しています。しかし、求められている状況下であっても、働く環境や条件が合わないことや、家庭との両立に難しさを感じ、保育士として働くのを躊躇している人もいるでしょう。
保育士不足を解消させるためには、不安要素である業務負担を減らす環境づくりがとても重要です。例えば、施設内に安全性や耐久性、メンテナンス性を高めたドアや壁材などを取り入れることで、多忙な保育士の業務負担を減らす効果が期待できます。
中でも施設内での声の反響は、子どもたちの落ち着きをなくしたり、保育士へのストレスに影響を与えます。子どもや保育士が快適に過ごすことのできる、施設内の音環境の改善に関する実例については、下記でご紹介していますので、こちらもご確認ください。
⇒「声の反響がストレスに 音環境向上改修で子どもも保育士も快適な保育園に」
また、待機児童問題が解消されたとしても、「2025年問題」が生じる可能性は保育施設にもあります。下記の記事でその内容をまとめていますので、ぜひ併せてご確認ください。
⇒「2025年問題は保育園にも! 待機児童問題から一転、利用児童数ピーク後を考えた施設設計」
保育の様々な社会課題を解決するため、まずは保育士が安心して働けるように、あらためて保育環境の見直し、改善を検討してみてはいかがでしょうか。
公開日:2023.03.27 最終更新日:2024.04.22
おすすめ製品