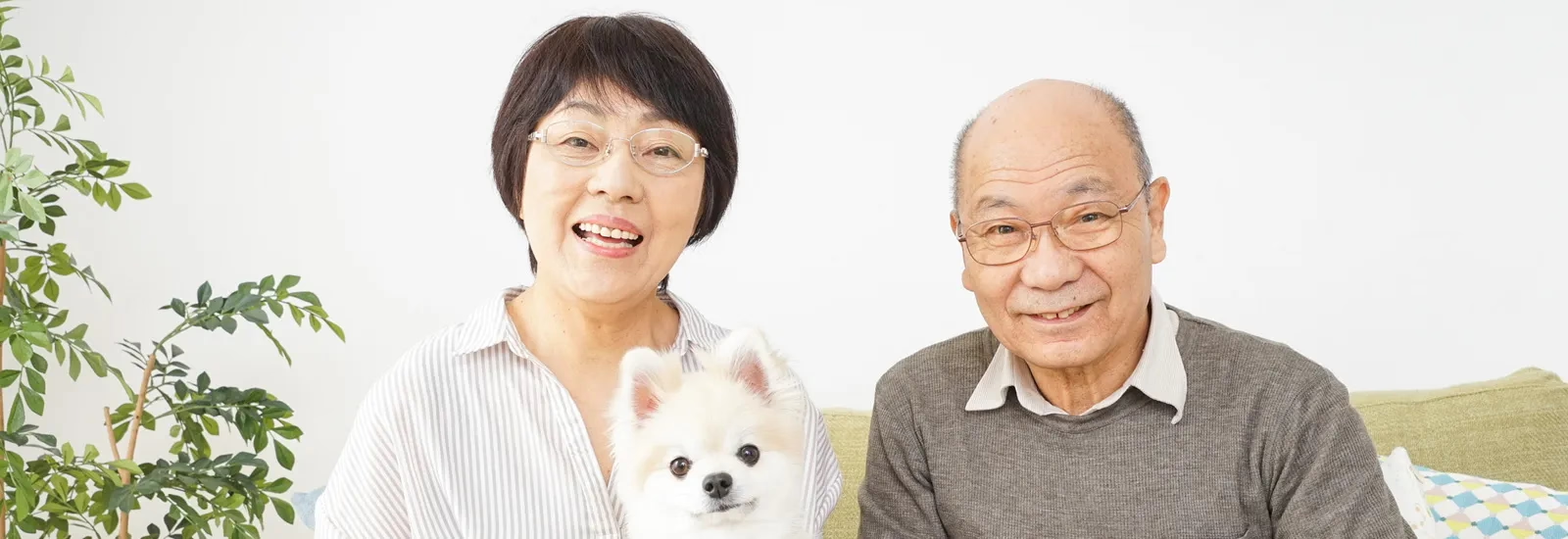自宅内での転倒・転落・落下を防止したい! 階段の滑り止めや手すりリフォームで対策を
※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
目次
高齢者の事故で注意したいものの1つに“転倒”がありますが、その発生場所の多くが家の中だということをご存じでしょうか? 高齢者にとっての転倒は、その後の生活に影響を残してしまうケースもあります。家族の生活を守るためにも、転倒の防止策は可能な限り講じておきたいものです。
今回は、高齢者が転びやすい場所や転倒する原因、そして高齢者の転倒・転落防止に役立つ手すり製品をご紹介します。
家の中で高齢者が転倒しやすい場所はどこ?

「救急搬送データからみる高齢者の事故」という東京消防庁が公開しているデータがあります。この調査によると2021(令和3)年までの5年間で高齢者が救急搬送された原因の第1位は「ころぶ」事故で、なんと全体の8割以上を占めています。さらには、転倒する事故のうち5割以上が住宅内で発生していることもわかりました。
転倒事故が起こる場所は居室・寝室が最も多く、次いで玄関・勝手口、廊下・縁側・通路、トイレとなっています。
リビングや個室、寝室といった居室で転倒する事故が多発しているのはなぜなのでしょうか。
年齢を重ねると歩く際につま先が上がりにくくなるため、カーペットや敷物のわずかな段差に加えて、電気コードや床に置いてある新聞、敷きっ放しの布団も転倒する原因になってしまいます。このように、これまで意識せずに回避できていた物にひっかかったり、段差につまずいたりする事例が増えてしまうのです。
これらの対策方法として、高齢者の通り道となる床をスッキリとした状態に整えることが大切です。床の上はこまめに片付け、電気コードは壁に寄せて固定しましょう。そして、高齢者が歩く場所はなるべく広くします。カーペットを敷いている場合はズレ防止シートを活用したり、端を両面テープで固定するなど、転倒につながるリスクを回避しましょう。
高齢者が転倒する原因には病気や薬の影響も

高齢者の転倒は自然な身体能力の衰えからだけでなく、隠れた病気が原因となっている場合もあります。また、飲んでいる薬の影響から注意力が散漫になったり、ふらついて転倒する方もいます。
高齢者が転倒する要因のうち、老化・病気・薬など、高齢者個人に関係したものは“内的要因”、段差や障害物の有無など環境的なものは“外的要因”として分けられます。高齢者の転倒は2つの要因が複合して起こるケースが多いといわれており、その両面から防止することが大切です。
玄関・階段での転倒や転落、落下を防ぐには
玄関や階段で起こる転倒・転落事故にも注意が必要です。階段を踏み外したり、玄関の段差につまずいて転倒する事例は数多くあります。
体力があるうちは関節の動く範囲が広いので段差があってもつまずきにくく、よろけたとしても踏みとどまれますが、年齢を重ねるにつれて関節の動く範囲は狭くなっていきます。ほかにも認知機能が衰えたり薬の影響からめまいが生じたりと要因はさまざまで、若い頃には気にならない程度の段差でも、高齢者にとっては転倒するリスクとなるのです。
このような理由から、階段からの転落・落下を防ぐには床での転倒対策に加え、さらに十分な対策が必要になります。
階段滑り止め(ノンスリップ)で転落防止の対策を メリット・デメリットも

●階段滑り止め(ノンスリップ)とは
階段滑り止め(ノンスリップ)とは、階段の踏板に付けるパーツのことです。名前のとおり階段の滑り止めとして作用し、転倒を防ぎます。駅やデパートの階段のように土足で上り下りする階段には、主に金属製の滑り止めの使用が一般的です。一方、家庭用階段の滑り止めには樹脂製やゴム製の製品が多く使われます。
階段の滑り止めは後付けできるので、足腰に不安を感じたら設置を検討してみましょう。
●階段滑り止め(ノンスリップ)の種類
階段の滑り止めとして、どのタイプの製品を使うのがよいのでしょうか。まずは種類ごとの特徴を見ていきましょう。
・コーナータイプ
コーナータイプは階段の角の部分を覆うL字型をした階段滑り止めです。やわらかい素材の製品は、万が一の転倒時にも衝撃を和らげてくれるでしょう。両面テープで貼り付け可能で、カットも簡単です。
・マットタイプ
階段の足を乗せる部分である踏面(ふみづら)に敷いて使うタイプの階段滑り止めです。踏面全体を覆うものや一部のみをカバーするものなど、バリエーションがあります。さまざまなデザインの製品が市販されているため、インテリアにこだわりたい方におすすめです。
・テープタイプ
テープタイプの階段滑り止めは、踏面の一部にカットして貼るだけで対策ができます。価格も比較的安価なため、まずは手軽に滑り止め対策したいという方におすすめです。厚みもあまりなく、些細な段差も避けたい場合に向いています。
●階段滑り止め(ノンスリップ)のメリット
階段滑り止めを設置すると、転倒防止になるだけでなく、階段の保護にもつながります。階段の滑り止めが設置された部分は破損や摩耗から守られ、傷みにくいです。また、階段滑り止めには、踏板の端を目立たせることで踏み外しを防ぐ役割もあります。光を蓄積して暗闇で光るタイプの製品なら、停電時の上り下りも安心です。
●階段滑り止め(ノンスリップ)のデメリット
階段滑り止めにはデメリットもあります。吸着力が弱いと滑り止め自体が階段上で滑ってしまうのがリスクです。また、階段滑り止めの溝部分や繊維部分にゴミがたまると、掃除しづらく感じるかもしれません。
後付けの階段滑り止めは元の階段に別のパーツを継ぎ足すことになります。製品のデザインによっては元の階段の雰囲気と合わず、見た目が悪くなったと感じてしまうかもしれません。また、シールタイプは剥がしたときにシールが残りやすいので、汚れたときの交換や賃貸などで使用する場合は注意が必要です。
このように、階段滑り止めにはメリットとデメリットがあるため、よく検討してから設置するとよいでしょう。
転倒や転落、落下を防ぐ対策として、階段滑り止め以外によく用いられているのが手すりです。玄関や階段、またその近くをはじめとした高齢者が手を伸ばしやすい位置に設置し、移動を補助します。
転倒や転落、落下防止の手すりを設置する際のポイント

玄関や階段に転倒や転落・落下防止の手すりを設置する際のポイントを見ていきましょう。
手すりは高齢者がしっかり握れるサイズや形状を選びます。全体が使いやすい形かどうかも確認しましょう。手すりの材質によっては夏になると熱く感じたり、冬に冷たく感じる材質もあります。年間を通して気持ち良く使える触り心地の良いものを選びましょう。
手すりの設置は使う人の身長に合った高さにするのもポイントです。階段の場合は、段差が終わってからの水平部分にも設置するとよいでしょう。これは、斜めの部分で始まる手すりはつかみ損ねて転倒する危険があるためです。また、踊り場や階段を上りきったところに縦型の手すりを設置しておくと、高い場所からの転落・落下防止につながります。
玄関・階段での転倒や転落、落下防止に配慮した手すり建材
DAIKENでは後付けが可能な手すりを豊富に取り揃えており、玄関・階段での転倒や転落、落下を防止する際は、用途に合わせたものをお選びいただくことができます。
例えば『手摺セット32型』は手の小さな人が握りやすい直径32mmのL字型手すりです。玄関のちょっとしたスペースに設置すれば、立ち座りする際の補助としても役立ちます。手すりの裏側は浅い凹みのあるディンプル加工を施しており、握りやすく滑りにくい仕様になっています。
階段に手すりがない場合や、今の手すりが使いにくい場合は『システム手摺35型』を使った階段手すりのリフォームをおすすめします。『システム手摺35型』は直径35mmの丸棒ストレート型の製品で、手すりを支えるブラケットには固定式と着脱式の2種類をご用意しています。着脱式は本体と着脱ベースが分離しているのが特長で、手すりの施工時や壁紙を貼り替えるリフォームの際も作業がスムーズです。滑り止め効果のある『手摺用グリップ(35型用)』も取り付け可能です。

『手摺セット32型』と『システム手摺35型』の「ベーシックタイプ手摺 丸棒ストレート」と「ゴム集成材タイプ手摺 グリップ付丸棒ストレート」にはSIAA認証の抗ウイルスマークを取得したもの(※)もあります。ぜひチェックしてみてください。
(※)抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また、すべてのウイルスに効果があるわけではありません。
こちらの記事もチェックしてみてください。
関連記事⇒「フローリングが滑る! その対策法と高齢者やペットが歩きやすい床リフォーム」

-
監修者
志鎌のり子(しかまのりこ)
一般社団法人日本模様替え協会 理事/COLLINO一級建築士事務所代表。日本女子大学住居学科卒業、五洋建設でマンション・ビルの設計監理/内装デザインを10年担当。その後、日本ERIにて住宅検査など10年担当、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。現在は部屋を「機能による空間分け」「動線」「収納」の観点から模様替えする独自のメソッドにより、機能的な部屋づくり/仕組みづくりなどを提案。書籍「家具配置のルール」のほかSUUMO、AERAwithKids、建築知識ビルダーズ、住まいの設計など著書多数。
保有資格:模様替えアドバイザー 一級建築士 建築基準適合判定資格者 住宅性能評価員 建物耐震診断士 フラット35適合証明検査員 など
公開日:2021.12.15 最終更新日:2025.03.19



















![部位別(分冊版)5:階段 手摺 造作部材 掘こたつ[住宅向け製品]](../img/1528.avif)