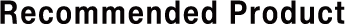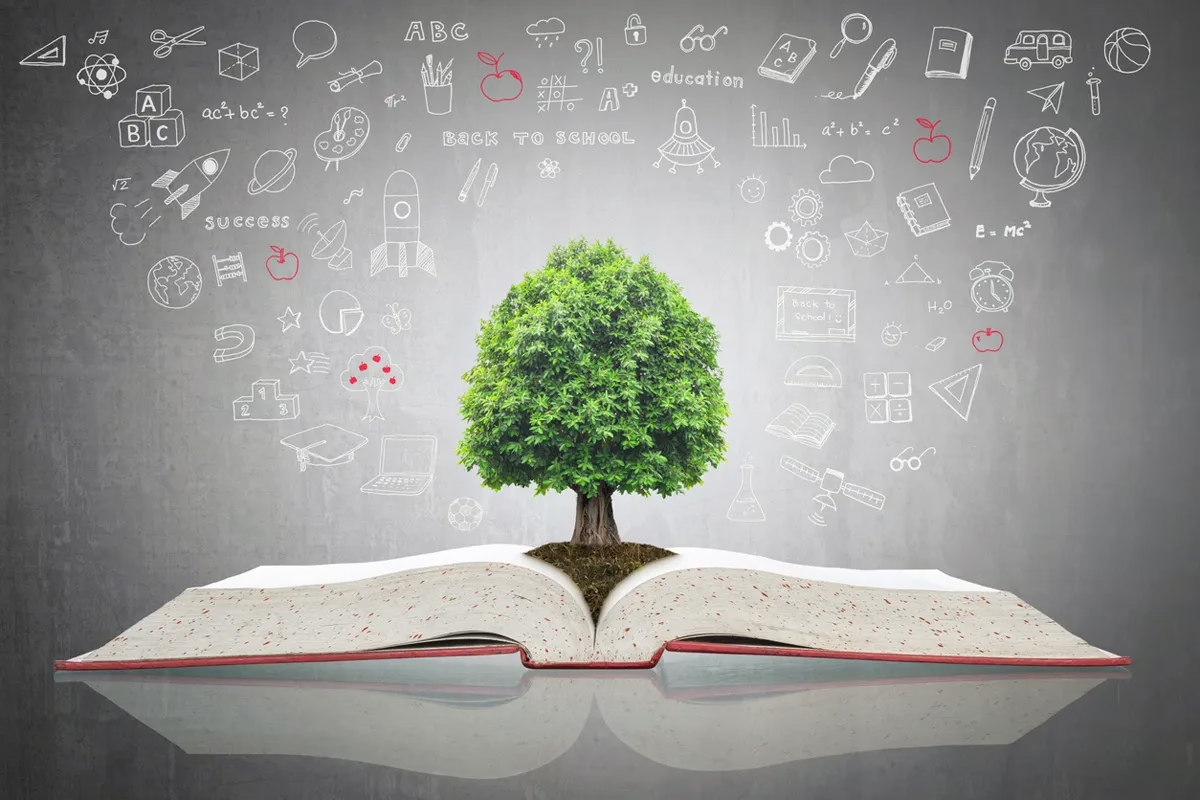図書館建築の考え方│必要な要素と設計のポイントは?【事例付き】

図書館は幅広い利用者がいるため、誰でも使いやすい施設であることが求められます。「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下、バリアフリー法)により「特定建築物」および「特別特定建築物」に指定されていることからも、多くの基準を満たす必要のある設計難易度の高い施設であるといえるでしょう。
また、近年の図書館は、本の貸出だけでなく、学習スペースやクールシェアスポットとしても利用されています。図書館は、多様な利用目的に対応するべく、多くの機能が求められているのです。
本記事では、図書館の設計をする際のポイントを紹介します。また、図書館建築で生じる課題を解決するDAIKENの製品を紹介しますので、参考にしてください。
図書館建築に必要な要素
はじめに、図書館建築で必要な要素をピックアップして紹介します。これらの要素は、図書館の形態や利用者層によって重要度が変わります。発注者が希望するイメージや近隣住民の雰囲気、地域の特性などに合わせて重みづけを調整しましょう。
●バリアフリー化
図書館は、バリアフリー法にて「特定建築物」および「特別特定建築物」に指定されています。そのため、以下の「適合努力義務」および「適合義務」が課せられています。
・図書館の新築・増築・改築・用途変更・修繕・模様替えを行う場合
→建築物移動等円滑化基準への「適合努力義務」
・2,000m²以上の図書館の新築・増築・改築・用途変更(※)を行う場合
→建築物移動等円滑化基準への「適合義務」
※面積要件は地域の条例による
建築物移動等円滑化基準とは、お年寄りや障がいをお持ちの方、妊婦、小さな子どもなど、誰もが利用しやすい建築物をつくるため、バリアフリー法が「最低限のレベル」として定めている基準です。以下に、基準の概要をピックアップして紹介します。
・玄関出入口の幅:80cm(120cm)以上
・廊下幅:120cm(180cm)以上
・スロープの手すり:片側(両側)
・スロープの幅:120cm(150cm)以上
・車いす使用者用駐車施設の数:1つ(原則2%)以上
・車いす使用者用トイレの数:建物に1つ(各階ごとに原則2%)以上
なお、上記の括弧内に記載しているのは「望ましいレベル」とされる「建築物移動等円滑化誘導基準」として定められている数値および仕様です。発注者が「バリアフリーに配慮した図書館をつくりたい」という意向を強く持っている場合は、「建築物移動等円滑化誘導基準」への適合を提案してみても良いでしょう。
参考:「バリアフリー法の概要について(建築物関連)」(国土交通省)
●用途に合わせたゾーニング
通常の建築物と同様に、図書館の設計においてもゾーニングに配慮したフロア構成が大切です。まずは利用者ゾーンとスタッフゾーンを明確に分け、利用しやすく、管理しやすい図書館を目指しましょう。以下に、それぞれのゾーンにおける設計のポイントを抜粋して紹介します。
【利用者ゾーンの設計のポイント】
・サービスカウンターは入口付近の見通しの良い位置に設置する
・閉架書架や移動棚が多い場合は、OPAC(オンライン蔵書目録検索システム)を効果的に配置する
・サインや基調色を効果的に使い、ゾーニングをわかりやすく表示する
・キッズスペースやイベントブースを設ける場合は、音に配慮してゾーニングを心掛ける
【スタッフゾーンの設計のポイント】
・資料の特性に合った資料保存室を用意する(温湿度、紫外線など)
・資料のメンテナンスを行うときのホコリや温熱環境に配慮した設備を設置する
・スタッフラウンジを設置する
参考:「図書館建築と設備」(筑波大学附属図書館)
参考:「図書館資料 保存の基本」(東京大学)
●利用者とスタッフの動きを考慮した動線
図書館の動線は、利用者・スタッフ・資料動線の3つに区分できます。使いやすく働きやすい図書館にするには、利用者とスタッフの動線ができるだけ交差しないように設計することが大切です。このとき、利用者とスタッフの出入口を別々に設けると、設計の自由度がアップします。また、資料を運搬するトラックの搬入口を裏側に設けられると、スタッフと資料の動線がクリアになるでしょう。
利用者ゾーンにおいては、滞在スペース、通過動線、検索動線を分けることが大切です。ここで、滞在スペースは本の閲覧や勉強をするスペース、通過動線は目的地に向かう動線、検索動線は本を探す動線を指します。これらのスペースと動線を分けることで、落ち着いた空間をつくりやすくなります。
参考:「ハイブリッド図書館のためのフロアレイアウトに関する一考察:九州大学中央図書館への適用事例」(九州大学学術情報リポジトリ)
参考:「日本の公共図書館における館内環境要素」(J-Stage)
図書館を設計する際のポイント
ここでは、図書館を設計する際のポイントをみていきましょう。課題解決に役立つDAIKENの製品も併せて紹介します。
●防音対策を施す
快適に利用できる図書館を設計するには、防音対策が重要です。防音対策には主に「遮音」「吸音」という2つのアプローチがあり、それぞれについて解説します。
遮音
遮音とは、音のエネルギーを障壁によって遮り、障壁の背後へ抜ける音を小さくすることです。つまり、「音漏れを小さくすること」といえます。図書館を設計する場合は、上階から下階に伝わる軽い足音や物の落下音(軽量床衝撃音)を小さくできると、快適な図書館を実現できます。
遮音を実現する具体策としてはDAIKENの『コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ』の採用が挙げられます。本製品は、防音性能に優れた土足対応のフローリングです。DW3/FW3はΔLL(Ⅰ)-3、DW4/FW4はさらに優れたΔLL(Ⅱ)-4S相当の防音性能を有しています。
吸音
吸音とは、音を吸収し、音の反射を小さくすることです。図書館では、天井や壁に吸音材を設置して音の反響を抑えることで、読書や勉強をしている人の不快感を抑えられます。
吸音を実現する具体策としてはDAIKENのロックウール吸音板『ダイロートン』の採用が挙げられます。本製品は、人が敏感であるとされる250~2,000Hzの音を効果的に吸収する吸音板です。デザインバリエーションが豊富なので、発注者の好みに合わせた空間を演出できます。
●耐久性を高める
図書館は、多くの方が利用する施設なので、傷や汚れに強い床材を使用することが大切です。清潔感をアピールできるよう、きれいさを保ちやすい床材を選定しましょう。
DAIKENの『コミュニケーションタフ バイオリーフシリーズ』は、土足対応の傷に強いフローリングです。木材組織をプラスチックで硬化させるDAIKEN独自の加工技術「WPC加工」を施し、高耐久の床材を実現しています。
図書館の機能多様化に対応する
2000年代以降、滞在型図書館が増え、図書館が地域活性化の拠点として活用される事例が増えています。このような図書館の多くは、地域産材を活かした特徴的な内装デザインを持ち、地域貢献やデザイン性をアピールすることで人気を集めています。また、内装に木材を使用すると利用者の心理面や身体面にプラスの影響をもたらすというメリットもあります。
DAIKENでは、床材や壁材、造作材などの一部製品で地域産材対応が可能です。図書館建築を通して、地域に根差したものづくりをしたいという希望があれば、お気軽にお問い合わせください。
図書館の建築事例
最後に、DAIKENの製品が採用された図書館の事例を紹介します。
●地域産材を活かした図書館
【大崎市図書館/宮城県】

床材:国産材活用厚単板WPCフロア〈大崎産杉〉

壁材:大崎産スギ突板張りダイライト不燃パネル
大崎市図書館の建設の経緯や設計のポイント、こだわりについては下記の記事でご紹介しています。ぜひご覧ください。
地域に愛される図書館設計が重要
図書館建築で重要なのは、バリアフリーに配慮しながら、利用しやすく、働きやすい環境を整えることです。さらに、防音性や耐久性に配慮することで「快適かつ美しい図書館」、地域産材の活用で「地域に愛される図書館」といったデザインコンセプトを取り入れられます。
DAIKENでは、図書館をはじめとした公共施設の設計をサポートするカタログを提供しています。お気軽にお問い合わせください。
図書館の設計に役立つカタログ「DAIKENとつくる公共施設 2024-25」を請求する
また、施設設計・建材選びに役立つプロ向け情報サイト『D-TAIL』では、公共・商業施設の設計やプレゼンテーションに役立つ情報を提供しています。建材選びの課題解決にお役立てください。
●本記事に関連する製品
・コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ DW3/FW3
・コミュニケーションタフ 防音 バイオリーフ DW4/FW4
・コミュニケーションタフ バイオリーフ DW(地域産材対応突板)
・ダイロートン
・グラビオルーバーUS
・グラビオUS
※建築事例に採用されている製品は取材当時(2017年7月)のものです。
おすすめ製品