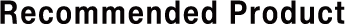オフィス設計に関わる消防法について│基礎知識や設計時の注意点

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
目次
オフィス設計においては、利用者の安全確保と法令遵守が求められます。オフィスの設計に関わる法律は多くあり、その中でも消防法は火災発生時の被害を最小限に抑えるための重要な法律です。消防法は建築基準法とも密接に関連するため、建築士や設計関係者はこれらの法律を正しく理解し、適切に対応することが求められます。
本記事では、消防法の概要やオフィス設計における具体的な注意点をわかりやすく解説します。
オフィス設計に関わる「消防法」とは?
消防法とは、簡単に言えば火災の防止や被害の軽減を目的とした法律です。建物内での火災リスクを最小限に抑えることを目的としており、特にオフィスでは、火災予防策や避難設備の設置が義務付けられています。そのためオフィスの設計においては、避難経路や消火設備の配置、警報設備の設置など、消防法で定められた基準に従って計画することが大切です。
消防法違反を指摘され措置命令違反や虚偽の報告などをした場合、罰金や懲役刑といった法的な罰則が科せられる可能性があるため、設計時には十分な注意が求められます。内装工事等の途中に消防法違反が発覚した場合は、工事が中断して費用が余計にかかり問題となる可能性もあるので注意してください。
消防法に基づく設計を行うことで、法令遵守にとどまらず、利用者の安全確保と円滑な避難の実現に繋がります。そのため、建築士や設計関係者は法令で求められる内容をしっかりと理解し、確実に反映した設計を行うことが求められます。
参考:
「消防法 第一条」(e-Gov法令検索)
「消防法施行令 第七条」(e-Gov法令検索)
オフィス設計に関連する消防法の主な義務
オフィス設計において、消防法で定められた主な義務には、以下のような消防設備の設置があります。
・消火設備:スプリンクラーや消火器など
・警報設備:火災報知器や非常ベルなど
・避難設備:避難はしごや誘導灯など
・消防活動用設備:排煙設備や連結送水管など
例えば、消火設備にはスプリンクラーや消火器が含まれ、火災の初期段階で火を消す役割を果たします。また、警報設備には火災報知器や煙感知器、非常ベルが含まれ、火災発生時に迅速な対応を促す目的で設置します。
参考:「消防法施行令 第七条」(e-Gov法令検索)
消防法に対応したオフィスを設計するには?
消防法に対応するオフィスを設計するには、燃えにくい建材の使用や基準に沿った消防設備の設置、避難経路の確保が必要です。
●燃えにくい建材の使用
オフィスの内装設計では、壁や天井が消防法及び建築基準法の内装制限の対象となる場合があります。内装制限を受ける場合には、一定以上の防火性能がある建材の使用が必要です。
消防法と建築基準法とでは、内装制限の規制の適用範囲や求められる防火性能に違いがあります。例えば、建築基準法では床面から1.2mを超える壁が内装制限の対象ですが、消防法では、床面から天井までの全面が内装制限の対象です。また、建築基準法では大規模建築物に該当する居室の壁や天井は難燃材料以上、通路や階段の壁と天井は準不燃材料以上を使うことが定められています。一方、消防法においては難燃材料以上の使用を求めています。
内装制限については、下記の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はご確認ください。
⇒「建築基準法における内装制限とは?対象となる建築物や緩和の要件」
参考:
「建築基準法 第三十五条の二」(e-Gov法令検索)
「消防法施行令 第十一条」(e-Gov法令検索)
「建築基準法施行令 第百二十八条の五」(e-Gov法令検索)
●基準に沿った消防設備の設置
消防法では床面積や階数など一定の基準を満たすオフィスに対して、さまざまな消防設備の設置を求めています。設置が必要になる条件は消防設備によって若干異なるため、ここでは主要な設備の設置基準について解説します。
スプリンクラー
消防法施行令第12条等に基づき、地上11階以上に位置する場合はスプリンクラーの設置が義務付けられています。天井の高さやスプリンクラーの種類に応じて設置基準が異なるため、基準を満たすように設計することが重要です。
参考:「消防法施行令 第十二条」(e-Gov法令検索)
消火器
消火器については、消防法施行令第10条等に基づき、延床面積が300m²以上の場合に設置が義務付けられます。設置位置についても通行や避難に支障がなく、かつ使用する際に容易に持ち出せる場所に置くことと定められています。
参考:「消防法施行令 第十条」(e-Gov法令検索)
屋内消火栓
屋内消火栓は、消防法施行令第11条等により、延床面積が1,000m²以上の建物や、4階以上かつ床面積が200m²以上の場合などに設置が義務付けられます。火災時に迅速に操作ができるよう使用者の動線に配慮した設計が求められます。
参考:「消防法施行令 第十一条」(e-Gov法令検索)
非常警報設備
消防法施行令第21条や同24条等に基づき、火災発生時に即座に避難を促すための非常警報設備(自動火災報知器や非常ベルなど)の設置が必要です。
自動火災報知器は延床面積が1,000m²以上の建物や3階以上かつ300m²以上の場合に設置が求められます。非常ベルは収容人数によって設置義務が変わりますが、自動火災報知機が設置されている場合は設置義務が免除されることがあります。
参考:
「消防法施行令 第二十一条」(e-Gov法令検索)
「消防法施行令 第二十四条」(e-Gov法令検索)
「火災警報設備等に関する主な規定について」(総務省消防庁)
誘導灯
誘導灯は、消防法施行令第26条等に基づき、非常時の安全な避難を確保するために設置されます。11階以上の階に誘導灯の設置義務があり、避難口や廊下、階段などに設置する必要があります。
参考:「消防法施行令 第二十六条」(e-Gov法令検索)
消防法や消防法施行令は定期的に改正されているため、最新の基準は各法令を確認しましょう。それぞれの基準を十分に理解し、適切に設置することが設計上の要点となります。
●避難経路の確保
避難経路の確保は、消防法において義務付けられている重要な要素です。消防法に具体的な通路幅の規定はないものの、労働安全衛生法施行令第543条に基づき、主要な通路幅は0.8m以上の有効寸法を確保することが求められます。また、建築基準法施行令第119条に従い、通路の片側のみに部屋がある場合は1.2m以上、両側に部屋がある場合は1.6m以上の通路幅を設ける必要があるため、これらの基準を満たすように避難経路を設計しましょう。
参考:
「労働安全衛生規則 第五百四十三条」(e-Gov法令検索)
「建築基準法施行令 第百十九条」(e-Gov法令検索)
消防法に基づいたオフィス設計の注意点
オフィス設計の際、個室ブースやパーテーションを設置すると消防法の規制対象となる場合があります。例えば、天井まで壁のある個室ブースを設けると居室や散水障害とみなされ、追加の消防設備の設置義務が生じる場合があります。
一方で、天井まで壁を立てずに欄間オープンを採用することで、消防法の規制の適用を回避できる可能性があります。欄間オープンの場合、完全に壁で囲われていないことから独立した居室と判断されず、消防設備の設置対象とならないためです。
なお、欄間オープンは上部に開口があるものの、個室になっているため音が響きやすいという課題があります。また、複数の欄間オープンの個室が並ぶ場合、互いの声が聞こえてしまうといった問題も生じます。これらの問題を解決するためには、欄間オープンの個室の壁に吸音パネルを設置することがおすすめです。
例えば、DAIKENの『OFF TONE(オフトーン)』を設置すれば、個室内の音の反響を軽減し、集中しやすい環境を実現できます。ちなみに、欄間オープンの個室に『OFF TONE(オフトーン)』を設置することで、室外から届く声の明瞭度が低下することがわかっています。そのため、欄間オープンの個室が複数並ぶレイアウトであっても、利用者の集中力を妨げにくくなるでしょう。
消防法への対応で実現する安全なオフィス環境
オフィス設計における消防法への対応は、法令を遵守するという観点だけでなく、従業員の安全を確保するために欠かせない重要な要素です。しかし、消防法の内容は非常に複雑なため、正しく理解できていないと法令に適合しない設計をしてしまう可能性があります。建築主の信頼を得るためにも、設計に関わる法令への理解を深めていきましょう。
DAIKENが運営する建築士や設計関係者向けの会員制情報サイト『D-TAIL』では、オフィスをはじめとした施設の設計や建材選びに役立つさまざまな情報を掲載しています。会員登録の上、日々の業務にお役立てください。
おすすめ製品