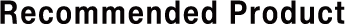木造校舎のメリットは?設計時の注意点、木造建築を支える新たな技術

※掲載している画像は、記事の内容をわかりやすくするイメージであり、実在する製品や実現するものとは異なる場合があります。
一昔前は、木造校舎には「危ない」「古い」というイメージがあり、校舎の新築や建て替えの際は、S造(鉄骨造)やRC造(鉄筋コンクリート造)が採用されるケースが一般的でした。しかし近年は、建築技術の進歩によって安全性が向上したほか、生徒や教師、地域社会への好影響が認知され、木造校舎が見直されるようになってきました。
2025年1月14日に文部科学省が公表した「公立学校施設における木材利用状況(令和5年度)」によると、令和5年度に新しく建築されたすべての学校施設691棟のうち、15.6%の108棟が木造でした。さらに、全体の70.3%(486棟)が構造や内装に木材を使用していることがわかっています。このデータからも、今、木材を用いた校舎づくりが注目を集めていることがわかるでしょう。
本記事では、木造校舎が与えるメリット・デメリットを整理しながら、設計時の注意点や木造校舎を支える新たな建築技術について解説します。
木造校舎が与える影響とメリット
近年、木材がもたらす効果や環境配慮の観点から、木造建築が再評価されています。木造校舎においても、生徒や教師、そして環境へもポジティブな影響をもたらすことがわかってきました。ここでは、木造校舎のメリットを「人」と「環境」の観点から解説します。
●人への影響
ストレスの軽減
木造校舎がもたらすメリットの一つは、子どもたちや教師への心理的・身体的な好影響です。木材が持つ自然の温かみや柔らかな質感は、心を落ち着かせ、ストレスの軽減に寄与するとされています。実際に木造校舎で過ごすことで、子どもたちの情緒が安定し、教師側も鉄筋コンクリート造の校舎と比べて疲労感が少ないと感じているとわかっています。
学習効率の向上
木造校舎は、学習環境の質にも良い影響を与えるとされています。木材には優れた断熱性能があり、室内の温度を一定に保ちやすいため、夏は涼しく冬は暖かい、快適な空間をつくれます。こうした環境は集中力を高め、眠気やだるさの抑制につながることから、学習効率の向上が期待できるのがメリットです。木材が持つ視覚的・触覚的な心地良さと相まって、木造校舎は学びに適した空間を実現する有効な選択肢となるでしょう。
●環境への影響
地球温暖化の抑制
木造校舎の建築は、環境保全の観点からも注目されています。植物は成長過程において二酸化炭素(CO2)を吸収し、炭素として固定する性質を持っています。さらにこの性質は、木材として伐採・加工された後も維持されることがわかっています。そのため、建築に使用することで、大気中のCO2を長期にわたり固定できます。これによりCO2の削減に貢献し、地球温暖化の進行を緩和する効果が期待されています。
森林の整備
木造校舎の建築は、森林整備の促進にもつながります。現在、日本の人工林の多くは手入れが十分に行き届いていない状態です。木材は「植える→育てる→収穫する」という再生可能な資源であり、継続的な利用によって森林の健全なサイクルを維持することが可能です。木造校舎を国産材で建てることで、林業の活性化や森林の環境保全にも貢献できます。
地域産材の活用
木造校舎の建築に地元の木材を使用すれば、林業従事者の収入増が期待でき、地域全体の経済活性化につながるのもメリットの一つです。地域産材は輸送距離が短く済むことから、燃料消費やCO2排出量の削減にも寄与し、環境負荷の軽減に結びつきます。このように、木造校舎の建築は、環境・森林・地域の三位一体で持続可能な社会の形成に貢献できるのが魅力です。
参考:
「建物の内装木質化のすすめ ─科学的データが示す内装木質化の効果─」(林野庁)
「(2)環境への配慮」(林野庁)
「令和2年度 森林・林業白書 第1部 第1章 第2節 森林整備の動向(2)」(林野庁)
木造校舎を設計する際の注意点
ここでは、木造校舎を設計する際の注意点について解説します。建築基準法や地域区分等について理解を深め、実務に活かしましょう。
●建築基準法を遵守した木造建築か
木造校舎を設計する際には、建築基準法に基づく防火対策に十分留意する必要があります。学校は「特殊建築物」に該当し、規模によっては耐火構造とすることが求められるため注意しましょう。
具体的には、周辺からの火災が内部に燃え抜けて侵入しないよう、屋根や外壁を含め、すべての部位に燃えにくい材料を使用しなければなりません。木材を活用する場合でも、法令に適合した構造とすることが設計上の必須条件です。
参考:「建築基準法 第二十七条」(e-Gov 法令検索)
●高い遮音性能があるか
木造校舎の設計にあたっては、遮音性能にも十分な配慮が必要です。木造はRC造やS造と比べて音や振動が伝わりやすく、上下階の足音や騒音が校舎内に広がりやすい傾向があります。音は柱や梁といった構造体を通じて伝わることがあるため、設計時には対策が不可欠です。
具体的には、内装に使用する木材に密度の高い樹種を選定したり、壁や床を二重構造にしたりするなどの工夫によって、音漏れを抑えることが可能です。
●建てる場所が防火地域以外になっているか
木造校舎を設計する際は、建設予定地が防火地域等に指定されていないかを事前に確認することが重要です。「防火地域」には1時間準耐火構造の木造3階建て校舎は建てられず、準防火地域では延べ面積1,500m²以下に限られるという制限があります。1,500m²を超える場合は、特定の構造基準を満たす必要があります。
またそれ以外の地域では、壁等により3,000m²毎に区画すれば、面積の制限なしに建てられるという決まりがあります。ルールに沿った建築を行うためにも、地域区分を十分に確認し、適切な計画を立てましょう。
参考:
「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」(国土交通省)
「木の学校づくり-木造3階建て校舎の手引-」(文部科学省)
「木の学校づくり-木造3階建て校舎の手引-(一部変更)」(文部科学省)
木造校舎の建築を支える新たな技術
近年、木造校舎の建築には多様な技術が導入されており、これにより木造建築の性能や施工性が向上しています。ここでは、木造建築と関わりの深い新たな技術について紹介します。
●CLT
CLT(直交集成板)は、複数の板材を繊維方向が直交するように積層・接着して作られる建材です。強度や断熱性、調湿性に優れ、S造やRC造に匹敵する構造性能を持ちつつ、木材ならではの快適性も兼ね備えています。
従来の柱や梁に代えてCLTを構造材として用いる「CLTパネル工法」では、壁や床、屋根を一体的に構成でき、施工の効率化も図れます。またCLTは耐力壁としての利用も可能で、耐震性や耐火性の確保が可能です。
2020年にはCLTを用いた日本初の小学校が完成しており、今後、教育施設への本格的な活用が見込まれています。
参考:「木の学校づくり|学校施設等のCLT活用事例」(文部科学省)
●プレカット工法
プレカット工法とは、柱や梁、桁などの構造材をあらかじめ工場で機械加工することで、現場での作業の手間を抑える施工方法です。従来のように現場で加工する必要がなく、精度の高さと施工スピードの向上が大きなメリットです。
木造校舎のような大型の木造建築においても、均一で安定した品質の構造体を迅速に組み上げられるため、工期短縮と人手不足の対策にも貢献しています。また、CADデータ等と連動させることで設計通りの構造を正確に再現でき、設計意図をより正確に反映できる点もメリットと言えます。
●BIM
BIM(Building Information Modeling)とは、3Dモデルに加え、構造や設備、仕上げ、コスト、工程などのさまざまな情報を統合的に管理できるデジタル設計手法です。木造校舎においては、設計段階から施工、その後の維持管理まで、全ライフサイクルを通じて高い精度と効率性を実現します。
BIMはCLTやプレカット工法などと組み合わせることで、構造部材の干渉チェックや施工順序のシミュレーション、工程管理が容易になり、設計の整合性を高められます。また、関係者間で情報を共有しやすくなるため、設計ミスや手戻りの防止、意思決定の迅速化といった効果も期待できます。今後の木造校舎の設計において、BIMの活用は欠かせない要素と言えるでしょう。
BIMについての詳細は以下の記事で解説していますので、併せてご確認ください。
⇒「BIMとは?設計に取り入れるメリットやデメリット、導入のポイント」
木造校舎の建築におすすめの製品
ここでは、木造校舎の建築におすすめの製品を取り上げます。DAIKENでは国土交通大臣認定の不燃材料等も扱っているため、求められる性能やデザインに応じて採用をご検討ください。
●コミュニケーションタフ バイオリーフ DW(地域産材対応突板)
『コミュニケーションタフ バイオリーフ DW(地域産材対応突板)』は、地域産材に対応した突板仕上げの土足対応フローリングです。耐傷性と耐汚染性を備え、落ち着いた木質空間をつくります。
※対応可能な樹種や数量については時期や地域によって異なるため、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
●グラビオUS
『グラビオUS』は不燃仕様の壁材で、防火性能が求められる木造校舎にもおすすめの製品です。軽量で施工性に優れており、樹種のバリエーションも豊富なため、木造校舎の内装イメージに合わせて選択ができます。地域産材にも対応しているので、地元の木材を取り入れたい建築主の意向にも沿えるでしょう。
※対応可能な樹種や数量については時期や地域によって異なるため、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
●オトユカベースN
『オトユカベースN』は、階下への床衝撃音の低減が期待できる防音床下地材です。木造校舎の音問題を軽減し、快適な学習環境づくりに役立ちます。仕上材の自由度が魅力で、無垢材以外の多様な床材と組み合わせられます。
●ダイロートン スクールトーン
『ダイロートン スクールトーン』は、木造校舎などの文教施設におすすめの天井材です。吸音性能があり反響音を抑えられるため、授業中の教師の声を聞き取りやすくする効果が見込めます。さらに、調湿機能やホルムアルデヒドの吸着性能を備えており、安心して学びに集中できる環境づくりに役立ちます。
新しい技術を取り入れて安心・快適な木造校舎を設計しよう
木造校舎は生徒や教師の心身に良い影響を与えるだけでなく、地球環境や地域社会への貢献も期待できます。近年ではCLTやBIMなどの新しい技術の導入により、安全性や施工性も大きく向上しています。設計時には法令や遮音性能、防火対策などさまざまな観点への配慮が必要ですが、適切に対応することで、持続可能で快適な学びの場をつくれるでしょう。
DAIKENでは、学校の設計に役立つ資料をご用意していますので、気になる方はぜひご請求ください。
学校の設計に役立つ「2025-26公共・商業施設向け製品 学校・文教施設」を資料請求する
また建築士や設計関係者向けの会員制情報サイト『D-TAIL』では、施設設計や建材選びに役立つさまざまな情報を掲載しています。会員登録の上、日々の業務にお役立てください。
●本記事に関連する商品
・コミュニケーションタフ バイオリーフ DW(地域産材対応突板)
・グラビオUS
・オトユカベースN
・ダイロートン スクールトーン
おすすめ製品