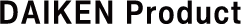天井ルーバーと床材の木質材料が生み出す調和 県産材による温かみのある美術館の佇まい

目次
-
◆課題
ルーバー:
・地域産木材を使った温かみがあり居心地のよい空間を実現するため天然木を検討したが、溶脱や白華が心配だった
・まちのシンボルとなるような象徴的でありながら、下地や納まりが目立たない抽象的な天井にしたかった
床:
・県産材の杉を使いたいが、杉特有の色のバラつきと耐久性が懸念だった
・展示室は長く滞在するため、床の防音性や歩行感が心配だった◆解決策&ソリューション
ルーバー:
・地域産材を突板で使いながら、メンテナンス性にも優れたルーバーを提案
・平使い、縦使いを組み合わせにすることで、立体感のある天井に仕上がった
床:
・何度も着色の試作を重ね、希望の仕上がりに近づけることが出来た
・突板フローリングでありながら、裏面に防音の不織布がついており、歩行音・歩行感に配慮した
鳥取県立美術館 | 鳥取県倉吉市
鳥取県倉吉市に鳥取県立美術館がついに竣工、2025年春のオープンを控えています。槇総合計画事務所による意匠設計、竹中工務店による構造設備設計・施工で"人々が集い、楽しみ、交流し、鳥取のアートを発信する拠点"として注目を集めています。
美術館は3階建て。水平にのびやかに広がる大屋根のもと、建物内部の中心には3層吹き抜け「ひろま」が配置されています。
「ひろま」は特徴的なパターンのルーバーが印象的な天井となっています。個々のルーバーは、同一の形状でありながら平使い、縦使いといった取付方や、角度を変えて組み合わさり、鳥取砂丘の風紋や伝統工芸である倉吉絣(かすり)の織模様を思わせる意匠になっています。

鳥取砂丘の風紋や伝統工芸である倉吉絣(かすり)の織模様を思わせる存在感のあるルーバー
その独特の雰囲気を演出しているのが、DAIKENの『グラビオルーバーUS直付式〈鳥取県産杉〉』です。また、ルーバーと呼応するような木質の床材として廊下や展示室では『コミュニケーションタフⅡDW(地域産材対応突板)〈鳥取県産杉〉』と『コミュニケーションタフ防音ⅡDW3(地域産材対応突板)〈鳥取県産杉〉』が採用されました。
本記事では関係者様へのインタビューを通じて、美術館の設計コンセプトやDAIKEN製品の採用経緯について詳しく紹介します。
お話を聞いた方々

-
(写真右)
株式会社槇総合計画事務所
主任所員
松田 浩幸 氏(写真左)
株式会社竹中工務店
広島支店
作業所長
吉田 義典 氏
鳥取県立美術館の設計コンセプト
―鳥取県立美術館の誕生について
槇総合計画事務所 松田氏
鳥取県は日本で最後発に近い県立美術館の整備を行う自治体でした。この美術館には、県全体の経済的発展や文化的水準の向上、倉吉市を中心とする中部地域の地震からの復興という様々な思いが込められています。美術館に興味がある方だけでなく、県民全体に利益をもたらすような施設を作りたいという強い思いがありました。
その中で我々は、お越しになる様々な方に日常的に永く親しまれ、アートに纏わる活動の拠点となる美術館を目指しました。美術館という従来のイメージに固執せず、コミュニティセンターとしての要素も持ち合わせたイメージで設計をスタートしました。

株式会社槇総合計画事務所 松田氏
―設計コンセプトは?
槇総合計画事務所 松田氏
県からの希望・要望の資料から想いを読み解き、現地に赴き鳥取の空気に触れながら感じたこと。それは旧来の美術館に多くある権威性、象徴性、格、静けさを表現した強い意匠性の建築ではなく、より親しまれるような居心地の良い「おうち」のようなイメージだということでした。
洗練された非日常空間で美術作品を見るというだけではなく、用事がなくても長くいられるような居心地のいい空間といったイメージを抱きながら試行錯誤していきました。
3層吹き抜けの「ひろま」を美術館の中心に
槇総合計画事務所 松田氏
美術展示のみにとらわれない空間を象徴的に表しているのが、館内の全フロアを縦に貫く3層吹き抜けの「ひろま」です。15メートルの天井高があるこのスペースは、大規模な展示のみならず、ワークショップ、コンサート、ユニークベニューなど様々な用途で使えます。「ひろま」を中心に、展示室やテラス、カフェなどが緩やかに立体的につながる、まさに美術館の中心となる空間です。

「ひろま」
「ひろま」を包み込む大屋根
槇総合計画事務所 松田氏
設計のプロセスの中では、内部空間と連動する形で外観もイメージをします。その中で、穏やかな外観、街や人に対して開かれて包み込むような「大きな屋根のおうち」というイメージが出来あがってきました。内外観ともに、親しみがあり開かれて、集まれる美術館という思いが通底しています。
その中で、山陰地方、特に鳥取の穏やかな地域性や気候も考慮しました。強い日差しが照りつける沖縄や広大な平野がある北海道とは異なり、人の生活が肌で感じられるような穏やかな地域性の中で、周りの方々にどう親しまれ、思い出の場所となっていくかを考えました。
そこで、日本の伝統建築を思わせる抽象的なボキャブラリーとして、水平性と細い垂直性を取り入れました。神社や屋敷の軒の水平性と、それを支える木造の細い柱の垂直性がこの地域に相応しい鳥取らしさに繋がるのではないかと考えています。 鳥取県にある投入堂やこの地域に古くからある長谷寺をレファレンスしながら、地域の文化に根差した親しみのある姿を目指しました。

美術館外観 日本の伝統建築を思わせる穏やかな外観 ※屋外のルーバーは、他社製品が採用されています。

大屋根の水平性と細い柱の垂直性 ※屋外のルーバーは、他社製品が採用されています。
「ひろま」と大屋根をつなぐDAIKENの天井ルーバー
―天井のデザインはどのように発想した?
槇総合計画事務所 松田氏
天井の木ルーバーのデザインは当初、ワンウェイ(一方向へ流れる)ものを想定していましたが、より効果的に天井面の木質を感じることはできないかと思い、違う方法を考えた結果、平使いと縦使いを組み合わせて使う考えに至りました。平使いは長方形ルーバー断面のより広い面を表に出し、縦使いは長方形ルーバー断面のより狭い面を表に出すことです。

『グラビオルーバーUS』の平使いと縦使い
下から見上げると、人間の認知として平面が卓越して見え、横から見ると縦面が卓越して見える傾向があります。この視点による変化が、動きのある視覚的な効果を生み出すと考えたのです。
その中でルーバーの配置もワンウェイではなく、斜めに互い違いに組み合わせることで、立体的で凹凸の深い形状と相まって、より視覚的な豊かさを追求できました。
その組み合わせは鳥取砂丘の風紋や、倉吉の伝統工芸の絣織の文様を想起させることにもなっています。

「ひろま」の天井 『グラビオルーバーUS』
―DAIKEN製品の採用経緯は?
竹中工務店 吉田氏
当初、天井のルーバーは、不燃木で検討していました。しかしながら、不燃木では溶脱・白華などの不具合事例が多々あり、別の手段を探していました。特に今回は天井高の高い吹き抜けのため、不具合が起きた際のメンテナンスも難しいことが容易に想像できました。
様々な材料を検討した中で、
・外部天井の天然木に意匠性を近づけられるもの
・溶脱・白華などのリスクの少ないもの
・コストなどのバランス
をクリアできるものを選定していたところ、DAIKENの営業からの提案もあり、『グラビオルーバーUS』を選びました。

株式会社竹中工務店 吉田氏
槇総合計画事務所 松田氏
『グラビオルーバーUS』の良さは、練り付けの持つ木の風合いや肌感覚をいい意味でのばらつきも含めて表現できることです。鳥取県の智頭産の杉を使ったということもあり、色や木目が揃って、非常にクオリティの高い仕上がりになりました。

本来、杉は赤みや白みの色の差が出やすい樹種ですが、智頭産はそのばらつきがほどよかったです。着色についても木の持つ表情を生かせるやり方を追求しました。
槇総合計画事務所はこれまで、木材の仕上げにはホワイトバーチやフローリングでも明るい発色の木材を選び、軽やかな空間を追い求める傾向がありました。その中で杉は軽くて柔らかく、色味も赤み白みのばらつきが大きいため、使う機会はあまり多くはありませんでした。
一方で、昨今の県産材活用が進む建築業界や日本で一番の生育の多い樹種でもある杉をしっかりと生かす方法を考えるようになりました。今回DAIKENの『グラビオルーバー』は杉本来の風合いと着色のバランスがとてもうまくいったと感じています。
木のぬくもりで美術館を包み込むDAIKENのフローリング

展示室にはクッション性のある『コミュニケーションタフ防音Ⅱ DW3(地域産材対応突板)』を採用
槇総合計画事務所 松田氏
フローリングも天井ルーバーと同じくDAIKEN の営業からの提案もあり、鳥取県の智頭産杉を使った『コミュニケーションタフⅡDW』シリーズを採用しました。居心地のよい美術館を目指す中で、天井と共に、床もフローリングの木のぬくもりで空間を包むイメージがありました。
また、人の動線として、通行の多いゾーンと展示室のような長く滞在する空間で同じ材料でいいのかという考えから、展示室にはクッション性のある『コミュニケーションタフ防音ⅡDW3』を採用しました。
DAIKEN 製品は歩行音の試験で防音性能(軽量床衝撃音)が検証されていること、製品の裏面に防音の不織布がついているため、フローリングの下地に防音シートを敷く施工の手間が省けることもメリットに感じました。
こちらについても着色は何度もやり取りを重ねました。杉特有の色のばらつきを抑えつつ、木の風合いを感じる仕上がりを狙いました。DAIKENから大量にサンプルをいただき(笑)、そこから何段階か手順を踏んで最終的な色味を決定しました。おかげさまで意匠面、性能面で納得のいくフローリングとなりました。

杉など柔らかい樹種を土足用フローリングに活用するために、木材組織にプラスチックを染み込ませて硬化。風合いを保ちつつ、耐傷性や耐汚染性が向上する。
竹中工務店 吉田氏
今回のフローリングは現場から車で15分ほどのDAIKENの工場で製造されていました。工場と現場がここまで近いということは珍しいのですが、これもご縁だなと思い、製造中に何度か足を運びました。DAIKENの工場の方も鳥取県立美術館向けのフローリングということで、一層熱意を込めて特注色の対応をしてくれました。その点は本当に感謝しています。施工業者の職長もいい施工管理をしてくれました。内覧会ではDAIKENの工場の方が30人ほど来てくださり、最後は作り手の思いがよい建築を完成させるのだとつくづく感じました。

写真右 株式会社槇総合計画事務所 松田氏 写真左 株式会社竹中工務店 吉田氏
竣工後の感想と美術館の未来
槇総合計画事務所 松田氏
鳥取県立美術館は、シンプルなデザインやおさまりとなっていますが、設計から施工まですべての要素が高い精度でバランスよく調和できたと思っています。窓のおさまり、扉のおさまり、天井ルーバーの配置、フローリングの割り付けひとつにも明確な意図を込めることができました。その中でDAIKENの木質建材は、仕上がりのクオリティが高かったため、精度の高い空間に仕上げることができました。
訪れた人が肌感覚としてその雰囲気を受け取っていただけるような空間がしっかりとできたのではないかなと思います。美術館なので、やはり建物というのはよき背景になる、美術館の主役が作品や様々な活動、それをする人々になればと願っています。
竹中工務店 吉田氏
クオリティの高い設計だったので、施工もいいものになりました。どこを取っても違和感がない空間、というのが率直な感想です。細部までこだわりが感じられる建築だと思います。
―美術館の未来像は?
槇総合計画事務所 松田氏
さまざまな人が訪れ、たくさんの思い出を作ってほしいということです。人生の記念すべき1ページの背景に、この美術館を選んでもらえるような場所になることを期待しています。
竹中工務店 吉田氏
鳥取出身者として、この地域にこのような一流の施設ができたことを非常に嬉しく思います。若い人たちがこの建物や美術品に触れることで、様々な感性を養ってくれることを願っています。また、県外からもたくさんの人が訪れ、長期的にはしっかりとしたメンテナンスを行い、この素晴らしい状態を保ち続けられることを期待しています。
―DAIKENに期待すること
槇総合計画事務所 松田氏
槇総合計画事務所では、ほぼすべての物件で建材をカタログ標準品から選ぶことは少なく、必要な性能をどのように実現するか素材から検討するところから発想します。DAIKENは大きな企業ですが、そういった特注対応にもしっかりと付き合っていただけることが今回わかりました。今後もそのような特注対応の体制を維持していただけると設計事務所としては助かります。大手企業としての信頼感もあります。
竹中工務店 吉田氏
特注対応の範囲が予想以上に広く、今回は色々と対応いただきとても助かりました。今回の良い経験を今後の体制づくりに展開し、新しい製品の開発に生かしてほしいと思います。

●施設データ
鳥取県立美術館
鳥取県立美術館は、地域性を活かしつつ最新の技術と設計思想を取り入れた、新しい形の美術館として注目を集めています。木のぬくもりが感じられる穏やかな吹き抜け「ひろま」を中心に、様々な風景や感覚に出会える空間として、多くの人々に親しまれることが期待されます。2025年3月30日にオープン予定。
※掲載内容は取材当時(2024年12月)のものです。
採用製品