日本における地震対策への取り組みとは?
防災情報の調べ方も解説
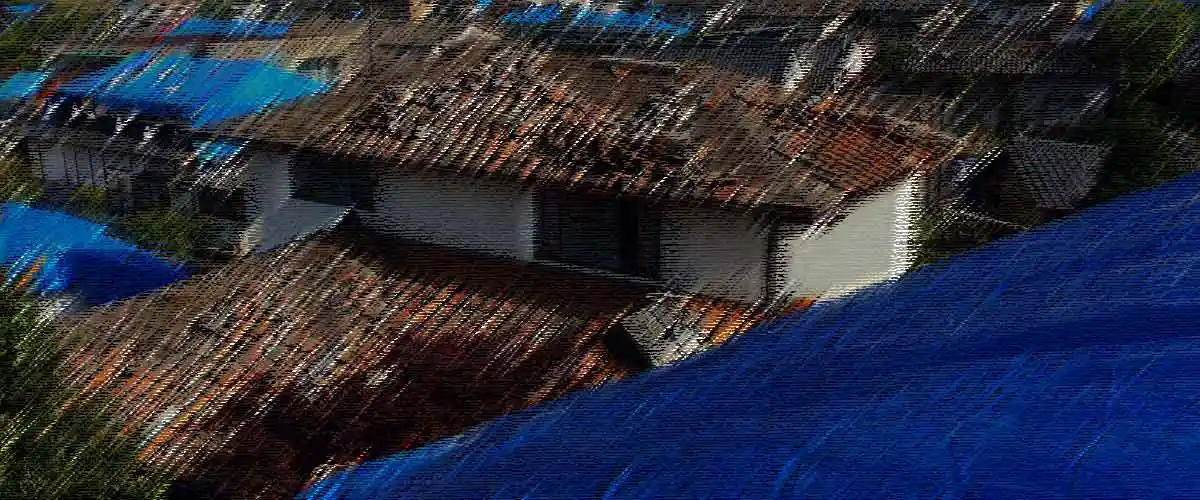
住宅購入の意思決定において、地震対策が講じられているかは重要な指標のひとつです。
日本は地震が多い国。地震対策は住宅購入からリノベーションに至るまで、必ず問われるでしょう。
今後、住宅の売買に携わる際は、地震対策の知識があるかどうかで、販売率に大きく関わるでしょう。
そこで、この記事では地震の多い日本の住宅における地震対策のあり方から、地域の防災情報を調べる方法までを解説します。
日本は地震が多い国?

日本は災害大国と呼ばれるほどに、毎年多くの自然災害が発生しています。
自然災害には豪雨や台風、火山の噴火などがあり、中でも多いのが地震です。日本の周辺で起こる地震の割合は、世界で起こるマグニチュード6.0以上の地震の約20%を占めています。他国に比べると非常に高い確率で地震が起こっているのが分かるでしょう。
以下では日本の周辺で地震が多い理由や地震のタイプなどを紹介します。
地震が発生する要因
地震の要因は地下にあるプレートのずれです。地球の表面は固いプレートで覆われていて、1年に数cmの単位でゆっくりと動いています。
プレートには陸のプレートと海のプレートがあります。
日本の周辺は陸のプレートであるユーラシアプレート、北アメリカプレートと海のプレートであるフィリピン海プレート、太平洋プレートと4種類のプレートに囲まれているので、ずれが起こる可能性が高く、地震が多い国になっているのです。
日本で発生する3種類の地震
日本周辺で発生する地震は3種類あります。以下では地震が発生する仕組みとこれまで日本で実際に起こった地震を紹介します。
1.プレート境界で発生する地震
プレート境界の断層運動による地震をプレート境界型地震と言います。
太平洋プレートやフィリピン海プレートの沈み込みに伴い、陸のプレートの端が海のプレートに引きずりこまれ、限界に達すると陸側のプレートが跳ね上がることで、地震が発生します。
これまで過去に日本で発生したプレート境界型巨大地震は以下のとおりです。
- ・関東大地震
- 発生年 : 1923年
規模 : マグニチュード7.9
死者・行方不明者 : 約140000人 - ・東南海地震
- 発生年 : 1944年
規模 : マグニチュード7.9
死者・行方不明者 : 1223人 - ・十勝沖地震
- 発生年 : 2003年
規模 : マグニチュード8.0
死者・行方不明者 : 2人 - ・東日本大震災
- 発生年 : 2011年
規模 : マグニチュード8.4
死者・行方不明者 : 18423人
※2022年3月9日時点
2.プレート内で発生する地震
プレートの内部で大規模な断層運動が起こって発生する地震がプレート内の地震です。プレート内の地震には、沈み込むプレート内の地震と陸の浅いところで発生する地震があります。
これまで過去に日本で発生したプレート内の地震は以下の通りです。
- ・昭和三陸地震
- 発生年 : 1933年
規模 : マグニチュード8.1
死者・行方不明者 : 約3000人 - ・釧路沖地震
- 発生年 : 1993年
規模 : マグニチュード7.5
死者 : 2人 - ・北海道東方沖地震
- 発生年 : 1994年
規模 : マグニチュード8.2
死者 : 0人
陸のプレートの浅いところで起きる地震
日本の周辺では岩盤の中に大きなひずみが蓄えられています。陸の浅いところで起きる地震とは海のプレート境界やプレート内のほか、陸域の浅い所(深さ約20kmより浅い所)で発生する地震のことです。
浅い陸域の地震は、プレート境界で発生する地震に比べて規模が小さいものが多いですが、人の居住地域に近いところで発生するため、大きな被害を伴うことも少なくありません。
過去に日本で発生した陸のプレートの浅いところで発生した地震は以下の通りです。
- ・阪神・淡路大震災
- 発生年 : 1995年
規模 : マグニチュード7.3
死者 : 6437人 - ・新潟中越地震
- 発生年 : 2004年
規模 : マグニチュード6.8
死者・行方不明者 : 46人 - ・熊本地震
- 発生年 : 2016年
規模 : マグニチュード7.3
死者・行方不明者 : 211人
3.内陸部の活断層を震源とする地震
内陸部にある活断層で起こる地震を内陸型地震または、直下型地震と言います。
陸のプレートが海のプレートに引き込まれると、押されたり引っ張られたりする力が生じます。
陸のプレートにどんどんひずみが蓄積して岩盤に割れ目ができ、さらには押されたり引っ張られたりする力が加わることで、断層が一気に動いて上下左右にずれが生じます。この時に起こる揺れが内陸型地震(直下型地震)です。
地震の震度とマグニチュードの違いとは?
震度とは?
震度は、ある規模の地震が起きた時の生活圏における揺れの強さです。
同じ地震であっても、震源からの距離や地盤の揺れやすさなどで、震度は変わってきます。
マグニチュードとは?
マグニチュードは、地震そのものの規模を表す数値です。
マグニチュードの小さい地震でも震源からの距離が近いと地面が大きく揺れるので震度は大きくなります。
また、マグニチュードの大きな地震でも震源からの距離が遠いと地面はあまり揺れなないため、震度は小さくなります。
地震の震度階級とは?

日本の震度は0から7までの数字で決められています。震度5と6は弱と強の2つに分かれているので、合計で10段階あります。以下では震度階級について表で揺れた時の状況をまとめています。
震度階級 揺れの状況 震度0 ・人はほとんど揺れを感じません。 震度1 ・屋内の静かな空間ではわずかに揺れを感じる 震度2 ・屋内の静かな空間では大半の人が揺れを感じる 震度3 ・屋内の静かな空間ではほとんどの人が揺れを感じる 震度4 ・ほとんどの人が驚くほど揺れを感じて、電灯などのつり下げ物は大きく揺れる
・不安定な置物が倒れる可能性がある震度5弱 ・大半の人が恐怖を覚えて物に捕まろうとする
・棚の手前にある食器や本が落ちる可能性がある
・固定されていない家具が移動したり、不安定な物は倒れる可能性がある震度5強 ・物につかまらないと歩くことが困難になる
・棚の手前にある食器や本が落ちることが多くなる
・固定されていない家具が倒れる可能性がある
・補強が済んでいないブロック塀が崩れる可能性がある震度6弱 ・立っていることが困難になる
・固定されていない家具の大半が移動して倒れる
・ドアが開かなくなる
・壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する可能性がある
・耐震性が低い木造建築などは瓦が落下したり建物が傾き崩れる可能性がある震度6強 ・はわないと移動できない
・固定されていない家具のほとんどが倒れる
・耐震性が低い木造建築など、ほとんどの建物が傾いたり、崩れたりする可能性が高くなる
・大きな地割れが発生する可能性がある
・土砂崩れによる被害の可能性がある震度7 ・耐震性が低い木造建築など、ほとんどの建物が傾いたり、崩れたりする可能性がさらに高くなる
・耐震性の高い木造建築でも稀に傾くことがある
・耐震性の低い鉄筋コンクリートの建物は傾くものが多くなる出典:国土交通省 気象庁ホームページ「震度について」(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/index.html)
日本の地震への備え、地震対策について
世界の中でも地震の多い日本ですが、その分国家で取り組んでいる地震への備えや国民一人ひとりが地震対策に向けた意識が高いことでも知られています。
以下では国が定めている大規模地震に対する応急対策と、これから起こる可能性のある地震についての概要などを紹介します。
大規模地震・津波災害応急対策対処方針
1.初動体制の確立
行政や自治体による緊急災害対策本部と現地対策本部等の設置を行います。地震が発生した後の対策に関する考え方や役割を決定します。
2.被害情報等の取扱い
被害情報等の迅速な収集を行います。被害情報を基に適正な整理・分析・共有をします。
3.緊急輸送のための交通の確保
負傷者を速やかに病院へ運ぶ、緊急物資を運ぶなどのために輸送ルートを啓開して点検して交通、海上交通、空路等を確保します。
4.救助・救急・消火活動等
被害がある場所に速やかな対応をするために警察、消防、自衛隊等が救助・救急活動を行い、支援等を行う国土交通省TEC-FORCEの活動と共に対応していきます。
5.医療活動
医療活動を迅速に行うためにDMATの派遣や広域医療搬送、地域医療搬送、避難所等における保健・医療・福祉サービスの提供等を行います。
6.物資の調達
物資の調達にはプッシュ型支援、物資輸送における役割分担を的確に行い、広域物資輸送拠点の確保を行います。
7.燃料供給
「系列BCP」に基づく石油供給の早期構築、重点継続供給、優先供給を確保します。
8.ライフラインの復旧
生活するために優先して復旧が必要なことを考え、優先復旧方針を決めます。方針が決まったらすぐに応急復旧を実施します。
9.避難者支援
地震によって建物が倒壊した際は、生活するための避難所や避難所の確保、応急仮設住宅等の提供が必要です。広域一時滞在を実施します。
10.帰宅困難者等への対策
被害によって帰宅が困難になる、多くの人々が容易に帰宅できないなどの場合があるため、一斉帰宅の抑制、一時滞在施設の確保、徒歩帰宅者への支援を行います。
11.保健衛生等に関する活動、災害廃棄物等の処理
保健衛生、防疫、遺体の処理等に関する活動や、災害廃棄物等の処理を行い、二次災害を防止します
12.社会秩序の確保・安定等
物価・供給体制を安定させるために、治安の維持と首都中枢機能の確保を行います。
13.二次災害の防止活動
二次災害を防止するために、被害情報を基にした迅速な注意喚起、調査や点検、応急措置、避難誘導を実施します。
14.防災関係機関の応援体制の確保
国、都道府県の役割分担に基づく広域応援体制を確保します。
15.内外からの支援の受入れ
海外からの物的・人的支援の受入れ手続きや、復旧活動や物資供給などの手助けになるボランティア・NPOの受入れを行います。
これからの日本における地震対策

活断層による地震は数千年単位の間隔で発生しますので、そこから今後の地震を予測できます。
これから日本で予測されており、備えておかなければならない大規模地震はいくつかあります。
例えば、日本列島を二分する糸魚川静岡構造線断層帯の平均活動間隔は約1000年です。
過去の地震は約1200年前で、今後30年以内にマグニチュード8程度の地震が起こる確率は14%、50年以内は20%、100年以内なら40%です。
今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率を見ると、多くは0.1%未満ですが、安全を意味するわけではありません。実際に2024年1月1日には震度7で大規模な被害を出した令和6年能登半島地震が起こっています。
以下では地震が発生する周期なども併せながら、これから起こる可能性のある地震の概要や対策内容を紹介します。
東海地震
東海地震は、南海トラフ沿いで想定されている大規模地震のひとつで、駿河湾から静岡県の内陸部を想定震源域とするマグニチュード8クラスの地震です。
想定震源地では1854年の安政東海地震の発生から現在まで、160年以上にわたって大規模地震が発生していません。
さらに、駿河湾地域では御前崎の沈降や湾を挟んだ距離の縮みなど、地殻のひずみの蓄積が認められていることから、東海地震はいつ発生してもおかしくないと考えられています。
東海地震は、概ね100~150年間隔で繰り返し発生しており、前回の東海地震である1944年に発生した昭和東南海地震、1946年に発生した昭和南海地震からは70年以上が経過しています。
東海エリア近辺にお住まいの方は、事前の備えをするためにも、以下の東海地震における被害想定をチェックしておきましょう。
建物の災害項目ごとの倒壊数と合計
| 揺れ | 静岡県、山梨県南部、愛知県西部等強い揺れが生じる地域を中心に、約17万棟 |
|---|---|
| 液状化 | 揺れの大きい地域や軟弱地盤を中心に、約3万棟 |
| 津波 | 静岡県、三重県等の沿岸部を中心に、約7千棟 |
| 火災 | 約1万棟〜5万棟 |
| 土砂崩れ | 静岡県等を中心に崖崩れが発生し、約8千棟 |
| 合計 | 約23万棟〜25万棟 |
ライフラインに影響する人口
| 水道 | 断水人口(発生直後)約550万人 |
|---|---|
| 電気 | 停電人口(発生直後)約520万人 |
| ガス | 供給支障人口(1週間後)約290万人 |
| 交通施設 | 道路、鉄道等にも被害が発生。一定期間利用困難となることも想定 |
| 避難者 | 地震発生の1週間後には約190万人の避難者 |
| 医療対応 | 地域内で対応困難な重傷者は最大で約2万7千人 |
死者数と経済被害
| 死者数 | 約7900~9200人 |
|---|---|
| 経済被害 | 約31兆円~37兆円 |
首都直下地震
首都直下地震は東京を震源として起こる地震と思っている方も多いですが、実際は、東京都、茨城県、千葉県、埼玉県、神奈川県、山梨県を含む南関東地域のどこかを震源として起こるマグニチュード7クラスの大規模な直下型地震です。
発生の確率に関して、政府は30年以内に70%程度という数値を発表しています。これは過去に発生した巨大地震から推測された値です。
30年間起こらない可能性もあり、今日起こる可能性があるのが首都直下地震です。
関東エリア近辺にお住まいの方は、事前の備えとして以下の首都直下地震における被害想定をチェックしておきましょう。
建物の災害項目ごとの倒壊数と合計
| 揺れ | 首都圏等強い揺れが生じる地域を中心に、約15万棟 |
|---|---|
| 液状化 | 揺れの大きい地域や軟弱地盤を中心に、約2万棟 |
| 火災 | 約65万棟 |
| 土砂崩れ | 静岡県等を中心に崖崩れが発生し、約8500棟 |
| 合計 | 約85万棟(※冬夕方18時 風速15m/s時) |
ライフラインに影響する人口
| 水道 | 断水人口(発生直後)約1100万人 |
|---|---|
| 電気 | 停電人口(発生直後)約160万軒 |
| ガス | 供給支障戸数(1週間後)約159万戸 |
| 避難者 | 地震発生1日後に約300万人 |
死者数と経済被害
| 死者数 | 最大約37600人 |
|---|---|
| 経済被害 | 約90兆円〜95兆円 |
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震は、房総半島の東方沖から三陸海岸の東方沖を経て択捉島の東方沖までの、日本海溝および千島海溝並びにその周辺の地域内部を震源とします。最大マグニチュード8クラスの大規模な地震です。
発生の確率は今後30年間で60%程度とされており、かなりの高確率です。日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震のような巨大地震については、来るのか来ないのかではなくいつ来るのかと考えた上での準備が不可欠です。
北海道、東北、関東南部エリア近辺にお住まいの方は、事前の備えとして以下の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震における被害想定をチェックしておきましょう。
建物の災害項目ごとの倒壊数と合計
| 揺れ | 強い揺れが生じる地域を中心に、約2800棟 |
|---|---|
| 液状化 | 揺れの大きい地域や軟弱地盤を中心に、約9000棟 |
| 津波 | 東北地方の太平洋沿岸を中心に約29万棟 |
| 火災 | 約3200棟 |
| 合計 | 約31万棟 |
ライフラインに影響する人口
| 上下水道 | 断水人口(発生直後)約394万人(日本海溝モデル) |
|---|---|
| 電気 | 停電人口(1週間後)約22万件(日本海溝モデル) |
| ガス | 供給支障戸数(1週間後)約17万戸 |
| 避難者 | 地震発生の翌日には約139万人の避難者 |
| 医療対応 | 地域内で対応困難な重傷者は最大で約1万9千人(日本海溝モデル) |
死者数と経済被害
| 死者数 | 約20万人(日本海溝モデル) |
|---|---|
| 経済被害 | 約48兆円 |
中部圏・近畿圏直下地震対策
中部圏・近畿圏直下地震は、東海地方や近畿地方、中国・四国地方を中心とした最大マグニチュード8クラスの大規模な地震です。
発生の確率に関して、政府は30年以内に70%程度という数値を発表しています。東海、近畿、中国・四国エリア近辺にお住まいの方は、事前に備えるため、以下の中部圏・近畿圏直下地震における被害想定をチェックしておきましょう。
建物の災害項目ごとの倒壊数と合計
| 揺れ | 強い揺れが生じる地域を中心に、約71万棟 |
|---|---|
| 液状化 | 揺れの大きい地域や軟弱地盤を中心に、約4万棟 |
| 火災 | 約51万棟 |
| 土砂崩れ | 約8000棟 |
| 合計 | 約129万棟 |
ライフラインに影響する人口
| 水道 | 断水人口(発生直後)約1651万人 |
|---|---|
| 電気 | 停電件数(発生直後)約277万件 |
| ガス | 約510万戸の機能支障 |
| 交通施設 | 影響人流量約1億1900万人 |
| 避難者 | 約800万人 |
死者数と経済被害
| 死者数 | 約42000人(上町断層帯の場合) |
|---|---|
| 経済被害 | 約74兆円(上町断層帯の場合) |
個人でできる地震の防災活動とは

前述のような大規模地震における防災とは、どのような行動をとることを指すのでしょうか。
防災というものを考える上では、地震でどんな危険やトラブルが起こるのか予測するところから始めると分かりやすくなります。具体的な危険やトラブルが分かれば、それに対応する形でどうすればよいかが見えてきます。
例として、次のような予測と地震対策が考えられます。
| 予測される危険・トラブル | 考えられる地震対策 |
|---|---|
| 家具の転倒 | ・家具はL字金具などで壁に固定する(壁に固定できない場合は天井に固定する) ・子ども部屋や寝室にはなるべく家具を置かない ・家具を置く場合はなるべく背の低いものを選ぶ |
| 施設や家屋の倒壊 | ・家族の安否確認方法を確認する(災害伝言ダイヤルや災害用伝言板の活用) ・避難経路、避難口を確認する |
| ブロック塀などの破損による落下物の発生 | ・ブロック塀や墓、石灯籠など、重たいものの近くには近づかないことを確認する |
| 電気や暖房器具等を原因とする火災の発生 | ・揺れを感知して電源を強制遮断する感震ブレーカーを設置する
・暖房器具の周りに余計なものを置かないようにする ・住宅用消火器を備えておく ・住宅用火災警報器を設置する |
| 津波の発生 | ・地域の防災マップ、ハザードマップを確認する |
| 水道、ガス、電気など、ライフラインへの影響交通障害による移動・流通への影響 | ・非常持ち出し袋を用意する ・非常食、水3日分と日用品、常備薬を備蓄する ・地震の情報を得るための方法を知っておく |
「防災とは何か」知りたい時に役立つ資料

地震の多い日本では子どもから高齢者まで、様々な人が地震に備えなければなりません。防災とは何か分かりやすく学べる資料がたくさんありますので、これらを活用して地震に対する備えを進めていきましょう。
以下に地震防災を考える上で役立つ資料を紹介します。参考の一つにしてみてください。
・「災害が起きる前にできること」 首相官邸
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/sonae.html
防災に関する問いかけがコンパクトにまとめられています。防災の役に立つリンクも充実しています。
・「防災カードゲーム このつぎなにがおきるかな」 国土交通省
https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kids/cardgame/index.html
災害が起きたときのシミュレーションや、どうしたら危険を回避できるか学べるカードです。ゲームとして遊べるので、子どもに地震防災とは何かを教えたい方は、ぜひ参考にしてください。
・「防災・危機管理eカレッジ」 総務省消防庁
https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/index2.html
子ども、一般、市町村長向けに幅広い防災知識を提供しているサイトです。実際に起きた地震の事例から防災を学ぶコンテンツも掲載されています。
地震に関する情報の調べ方

地震が発生した時は避難が最優先ですが、避難後の行動も大切です。地震の続報や避難状況、住んでいる地域の対応等を知っておくと不安定な生活になるかもしれないという懸念を少しでも軽減できるでしょう。
以下では地震に関する情報の調べ方を紹介します。
気象庁地震情報
気象庁の地震速報は迅速にかつ精巧な情報を届けてくれる国のツールです。地震速報の発表の基準や内容は以下のとおりです。
地震情報の種類と発表基準
地震情報は新たな情報が入ると時系列で以下の表の通りに発表されます。
情報の種類 発表基準 内容 震度速報 ・震度1以上 地震発生約1分半後に、震度3以上を観測した地域名と地震の揺れの検知時刻を速報する。 震源・震度に関する情報 ・震度3以上(津波警報・注意報を発表した場合は発表しない) 「津波の心配がない」または「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はない」旨を付け加えて、地震の発生場所やその規模を発表。 各地の震度に関する情報 ・震度1以上
・津波警報
・注意報発表または若干の海面変動が予想された時
・緊急地震速報発表時地震の発生場所やその規模、震度3以上の地域名と市町村毎の観測した震度を発表。
震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合は、その市町村名を発表。長周期地震動に関する観測情報 ・震度1以上を観測した地震のうち、長周期地震動階級1以上を観測した場合 地域ごとの震度の最大値・長周期地震動階級の最大値のほか、個別の観測点毎に、長周期地震動階級や長周期地震動の周期別階級等を発表。(地震発生から10分後程度で1回発表) 遠地地震に関する情報 ・マグニチュード7.0以上
・都市部など著しい被害が発生する可能性がある地域で規模の大きな地震を観測した場合国外で発生した地震について、地震の発生時刻、発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)を概ね30分以内に発表。
日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表。その他の情報 ・顕著な地震の震源要素を更新した場合や地震が多発した場合など 顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度1以上を観測した地震回数情報等を発表。 推計震度分布図 ・震度5弱以上 観測した各地の震度データをもとに、250m四方の格子毎に推計した震度(震度4以上)を図情報として発表。 出典:国土交通省 気象庁ホームページ「地震情報」(https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/joho/pdf/jishin.pdf)
緊急地震速報
気象庁は平成19年10月1日から緊急地震速報の発表を開始しました。緊急地震速報とは地震の発生直後に、各地における強い揺れの到達時刻や震度を予想し、可能な限り素早く知らせる仕組みです。
地震の強い揺れに備えて自らの身を守ったり、列車のスピードを落としたり、工場等で機械制御を行うなどに活用されています。
緊急地震速報の発表条件
一般人に伝えられる緊急地震速報の発表条件は、2点以上の地震観測点で地震波が観測され、最大震度が5弱以上と予想された場合です。
2点以上の地震観測点で地震波が観測された場合とした理由は、地震計のすぐ近くへの落雷等による誤報を避けるためです。
最大震度5弱以上が予想された場合とした理由は、震度5弱以上になると顕著な被害が生じ始めるので、事前に身構える必要があるためです。
緊急地震速報の内容
発表する内容は、地震が発生した場所や、震度4以上の揺れが予想された地域名称などです。
具体的な予測震度の値は、+1程度の誤差を伴うものであることやできるだけ続報は避けたいことから発表せず強い揺れと表現されます。
震度4以上と予想された地域まで含めて発表するのは、震度を予想する際の誤差のため実際には5弱である可能性があることや震源域の断層運動の進行により、しばらく後に5弱となる可能性があるという2つの理由によります。
緊急地震速報で続報を発表する場合
緊急地震速報を発表した後の解析により、震度3以下と予想されていた地域が震度5弱以上と予想された場合は、続報が発表されます。
続報では、新たに震度5弱以上が予想された地域及び新たに震度4が予想された地域を発表します。
日本の地震対策まとめ
地震対策はご自身ですぐにできることがほとんどです。これから起こる可能性のある大規模な地震に備えて、必要なものを準備するなど、万全の対策をしましょう。後回しにせず行動することが緊急時を生き抜く力に繋がります。
※ここに掲載されている情報は2024年1月時点のものであり、ご覧いただいている日と情報が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



















