R&Dセンター音環境ラボラトリー
『音ラボ』
音の技術を結集し、
多くの人を集める。
“SOUND”は「音」を意味する英語ですが
もうひとつ、「健全な」という意味もあります。
よく知られている「健全な肉体に健全な精神が宿る」は
英語では“SOUND MIND , SOUND BODY”と表現されます。
私たちが生活する現代の環境においては、“GOOD SOUND, GOOD MIND”
~「いい音があれば、心も健全になる」とも言えるでしょう。
DAIKENが長年培ってきた音の技術。
それは言い換えれば、人の心地よさの追求です。
多くの人が集う空間の快適性をさらに高めるため、
DAIKENでは、今日も音に関する英智と技術を結集させ、
よい音環境づくりに取り組んでいます。

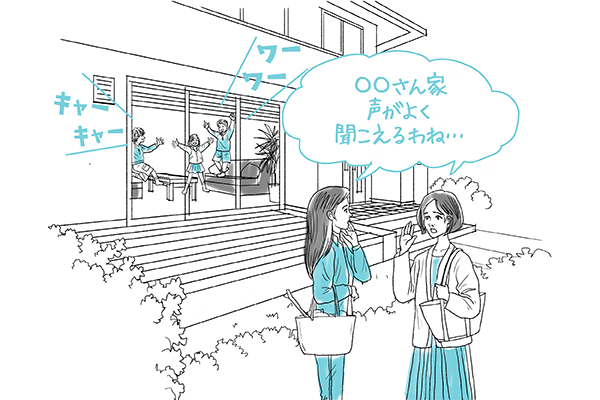
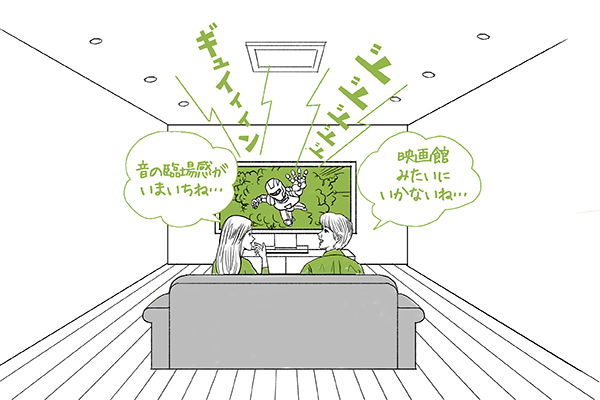
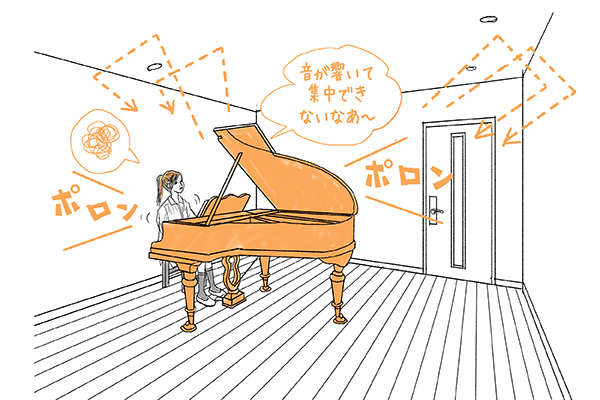
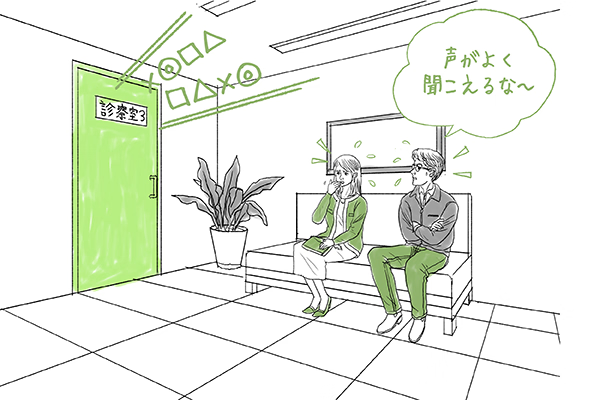
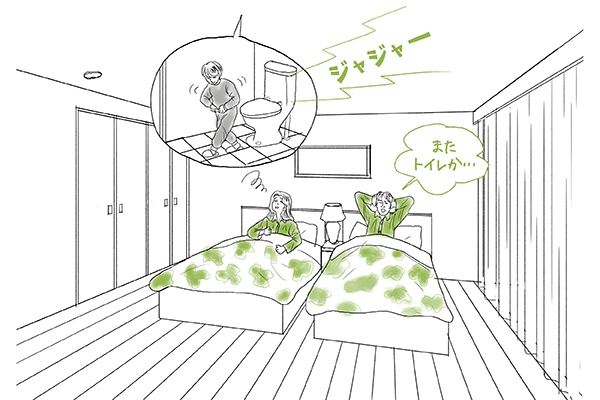
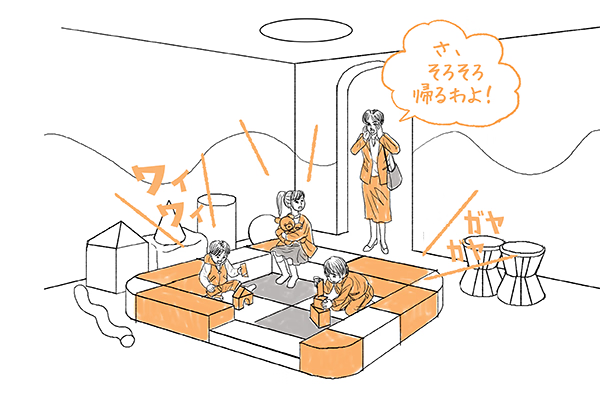
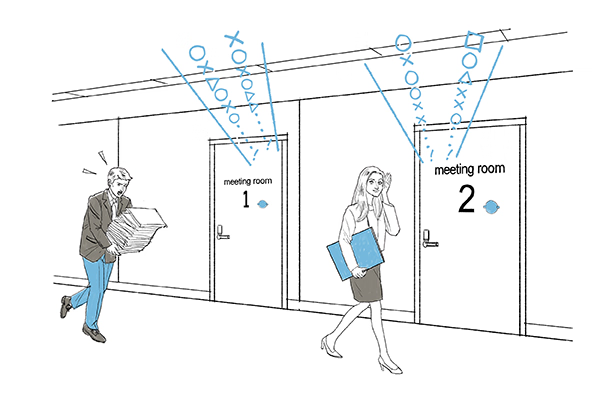

音環境の未来を創る
『音ラボ』の機能と今後の技術開発
『音ラボ』には、建築材料や構造の基本的な音響性能を測定する「残響室」、「無響室」、「箱型実験室」に加え、構造躯体にCLTを用いた「木造実験室」を備えています。各実験室には高性能の実験・測定装置を設置しており、音に関わる様々な性能評価や実験が可能です。
より高性能な「建築音響製品の開発」や「音環境の可視化」、あらゆる建築物に対応した音響設計を可能とする「シミュレーション技術の向上」など、さらなる音の技術開発を進め、顧客が求める幅広い要望にお応えするべく検討を行います。
平面図

立面図

※図面は簡略化しています。
【測定可能項目一覧】
| 項目 | 内容 | 対象室 |
|---|---|---|
| 残響室法吸音率 | 材料がどの程度音を吸収できるか(吸音性能)を測定します。 (JIS A 1409:1998、ISO 354:1985) |
残響室 |
| 音響透過損失 | 材料がどの程度音を遮るか(遮音性能)を測定します。 (JIS A 1416:2000、ISO 140-3:1995) (JIS A 1441-1:2007、ISO 15186-1:2000) |
残響室-残響室 残響室-無響室 |
| 散乱係数 | 材料に当たった音がどの程度散乱して跳ね返るかを測定します。 (JIS 未制定、ISO 17497-1:2004) |
残響室 |
| 床衝撃音遮断性能 | 階上で発せられる床衝撃音の測定を行います。 (JIS A 1418-1:2000、JIS A 1418-2:2019) (JIS A 1440-1:2007、JIS A 1440-2:2007、ISO 3822-1:1999) |
木造(CLT)実験室/箱型実験室 |
| 音響パワーレベル | 音の発生源のパワーを測定します。 (JIS Z 8734:2021、ISO 3741:1999) (JIS Z 8732:2021、ISO 3745:2000) |
残響室 無響室 |
| 心理実験 | 疑似的な音響空間での人の感じ方を測定します。 (規格はありません) |
無響室 |
| 模型実験 | 構造物のミニチュアを用いて音のふるまいをシミュレートします。 (規格はありません) |
無響室 |
| 垂直入射吸音率 | 材料がどの程度音を吸収できるか(吸音性能)を測定します。 (JIS A 1405-2:2007、ISO 10534-2:1998) |
計測室(音響管) |
無響室 残響室A 残響室B
主に遮音性能と吸音性能を測定します。

1:無響室 2:残響室A 3:残響室B

ラックとカセット
遮音性能を測る材料を
このカセットに施工します。
試料を施工したカセットを移動して遮音性能を測定
CASE①:無響室と残響室Aとの間に移動
CASE②:残響室Aと残響室Bとの間に移動

無響室

音が響かないよう、特殊な吸音材で囲まれています。遮音測定(音響インテンシティ法)や心理実験を行います。
残響室A

音の響きを良くするため、吸音材は用いず、コンクリートがむき出しのままになっています。
残響室B

構造は残響室Aと同様で、吸音性能測定はこの部屋を用いて行います。
箱型実験室A・B
主に床衝撃音遮断性能の測定を行います。

4:箱型実験室A 5:箱型実験室B

箱型実験室A(上部)
床、プレキャストコンクリート、CLTなど(可変)
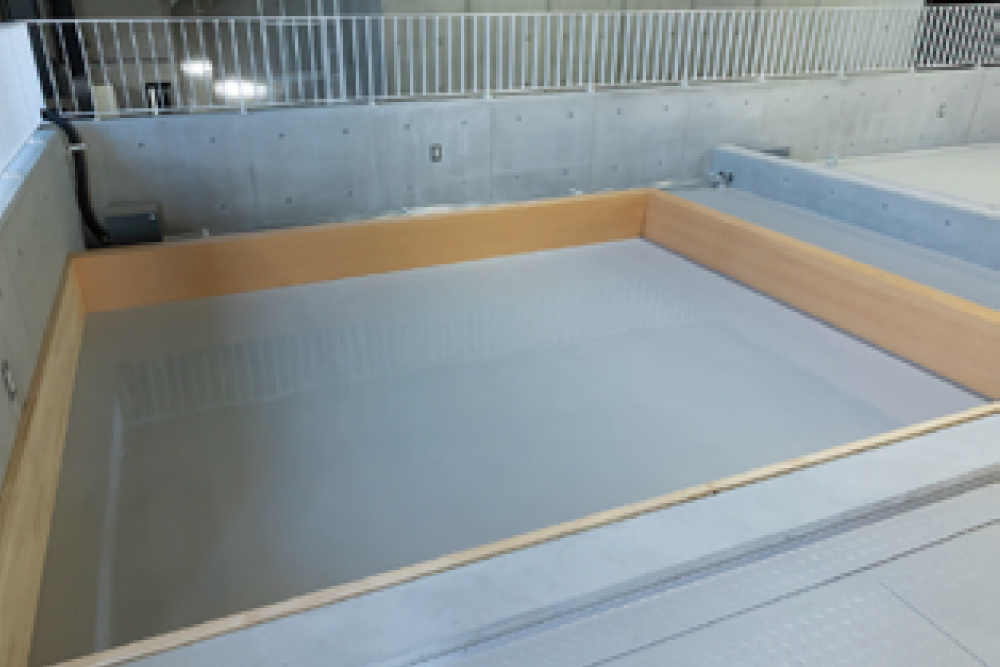
箱型実験室B(上部)
床、鉄筋コンクリート 厚200㎜(固定)
箱型実験室A

箱型実験室B

階下で床衝撃音を測定します。
一般住宅に音の響きを近づけるため、吸音処理をしています。
(こちら側に、天井を施工することも出来ます。)
木造(CLT)実験室
CLT(Cross Laminated Timber)で作られた木造の実物大の実験棟です。
木造と鉄筋コンクリートでは重量床衝撃音の伝わり方が著しく違うため、鉄筋コンクリートの実験棟で得られた性能が木造で発揮されることはありません。木造固有の床衝撃音対策を検討するためには欠かせない設備です。
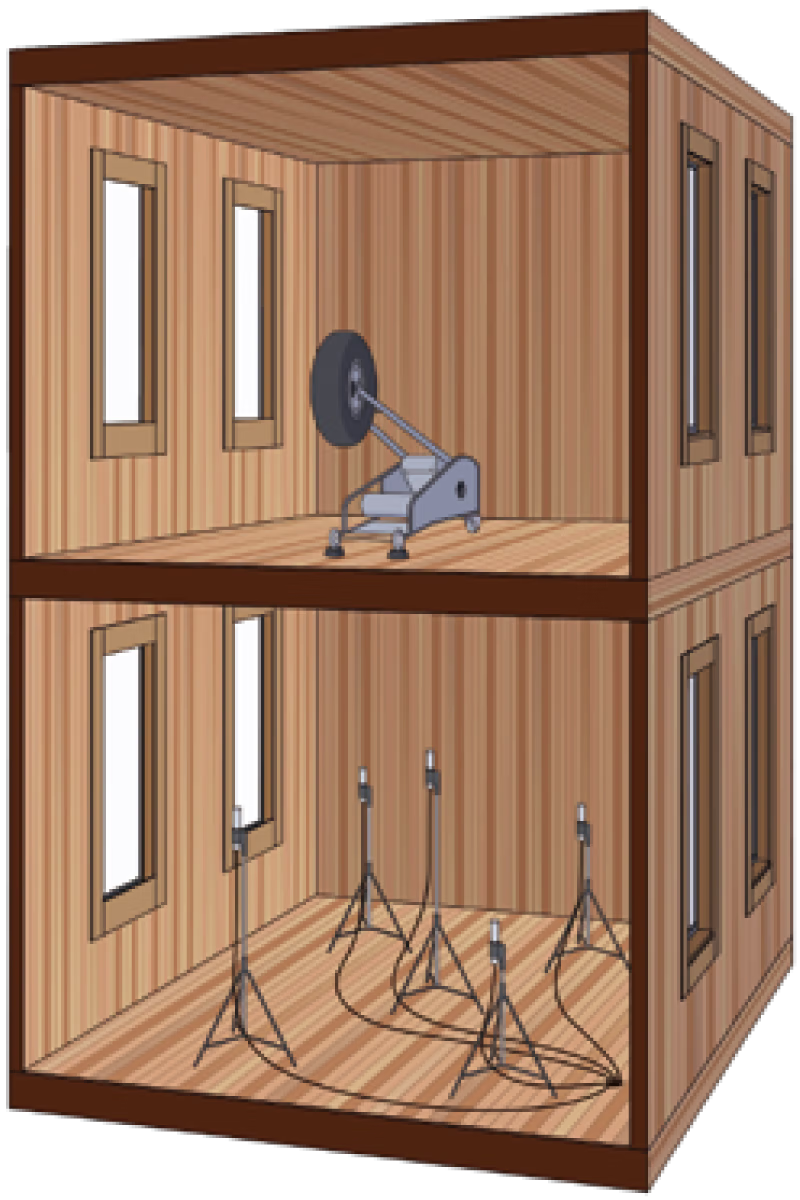
計測室
無響室ー残響室、残響室ー残響室の遮音性能測定や残響室での吸音性能測定の機器制御や、音響管での遮音/吸音測定はこの部屋で行います。

音響管(WinZac8)
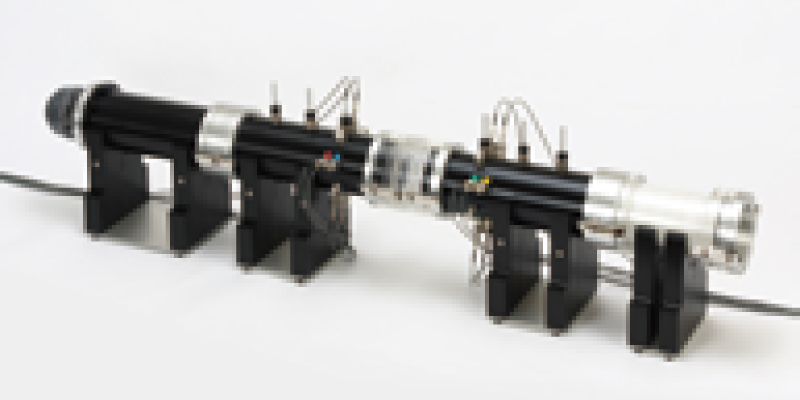
垂直入射吸音率と
透過損失を測定します。
ドア開閉試験室
防音ドアの繰返し開閉試験を行います。
発売前の防音ドア試作品は必ず数十万回の開閉テストを行い、耐久性に問題がない事を確認します。


| 名称 | 音環境ラボラトリー『音ラボ』 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県岡山市南区海岸通2丁目5番8号 |
| 敷地面積 | 1,170㎡ |
| 延床面積 | 926㎡ |
| 設備 |
|
音とDAIKEN
- 1958
- 岡山工場でインシュレーションボードの生産開始吸音板レギュラー
- 1964
- 岡山工場でロックウール吸音板『ダイロートン』の生産開始
- 1982
- 岡山工場に「開発部 防音課」を新設本格的な音事業のスタート
- 1982-83
- 基幹商品の販売開始オトテン、オトカペ、遮音シート/マット、防音ドア、防音換気扇など
- 1985-86
- 防音床材の販売開始オトユカスペースH、オトユカフロア、DADシステム
- 1989
- 音事業が岡山工場から独立(防音事業部)
- 1991
- ホームシアター提案を開始「防音」、「音響」に「創音」を加えた新コンセプト
- 2011
- コンセプトに『快音』を追加
- 2016
- 公共・商業施設向け本格対応開始OFF TONE マグネットパネル、OFF TONE クリアパネル
- 2023
- 『サウンドマルチルーム』の提案を開始
R&Dセンターに音技術研究室を新設
- 2025
- 『音ラボ』始動















