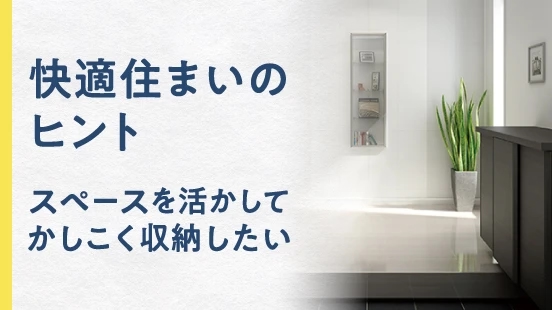【整理収納アドバイザー監修】汚部屋脱出のための片付け手順やコツを紹介

※画像はイメージです
「気づけば部屋が散らかっていて、どこから手をつけていいかわからない」そんな悩みを抱えている人は多いです。この記事では、整理収納アドバイザー監修のもと、汚部屋を脱出するための具体的な片付け手順やコツを紹介します。「片付けられない自分」を卒業して、気持ちまでスッキリ整う暮らしを目指しましょう。
片付けるのが苦手な人の特徴
・モノを手放せない人
・モノの優先順位がつけられない人
・一気に片付けようとする人
・片付けの仕組みが整っていない人
片付けが苦手な人にはいくつか共通する特徴があります。モノを「もったいない」と感じて手放せない、必要なモノの優先順位をつけられないなどです。また、一度に片付けようとして、余計に片付けのハードルが高く感じてしまう点も挙げられます。そのほか、モノの定位置が決まっていないなど片付けの仕組みが整っていないことも、部屋が散らかる理由といえるでしょう。
片付けのハードルを下げるポイント
・時間を決めて片付ける
・好きな音楽や気分が上がる曲をかけて楽しく片付ける
・片付ける前と後に部屋の写真を撮る
・ご褒美を準備する
片付けのハードルはちょっとした工夫でぐっと下げることが可能です。ここでは、4つのポイントをご紹介します。
時間を決めて片付ける
片付けをする際は、キッチンタイマーやスマホなどを使い、時間を設定するのがコツです。片付ける場所にもよりますが、10~30分を目途にアラームをセットしてみてください。時間を区切ることで「10分って結構あっという間だな」と集中できたことに気づけたり、「1時間も頑張れた!」という達成感が味わえたりします。集中できる時間は人それぞれなので、「もう少しできそう!」という場合は、繰り返しタイマーをセットしてみましょう。
好きな音楽や気分が上がる曲をかけて楽しく片付ける
無音で集中して片付けるのも効果的ですが、好きなアーティストの曲やテンポのよいノリノリの音楽をかけるのもおすすめです。音楽によって気分が上がり、作業がスムーズになります。さらに、音楽に合わせて体を動かしたりリズムに乗ったりしながら片付けると、楽しく取り組めるうえ作業効率もアップするでしょう。片付けが億劫に感じるときのモチベーション維持にも役立ちます。
片付ける前と後に部屋の写真を撮る
写真を撮ることで、自分の部屋を客観的に見ることができます。散らかった部屋が見慣れた景色になっていませんか。テレビや雑誌などでも「ビフォーアフター」の画像が出てきます。片付け前と、片付け後の画像を見くらべれば、すっきりした気持ちになるでしょう。片付けのたびに写真を撮れば、片付けのモチベーションやプラスイメージを維持できます。
ご褒美を準備する
片付けが苦手な方は、あらかじめ頑張った自分へのご褒美を用意しておくと、モチベーションが高まり取り組みやすくなります。お菓子や好きなドリンク、ちょっとした休憩時間でも十分効果的です。お子さんと一緒に片付ける場合は、お子さんが喜ぶ小さなご褒美を用意することで、楽しみながら片付けを進めることができます。
【監修者コメント】
片付けの3つのポイントを紹介!
【ポイント①「見せ場」を作る片付け】
お気に入りの一角を決め、そこだけ毎日リセット。香りや音楽で気分を上げ、終わったら写真共有。小さな自慢が継続を後押し。
【ポイント②進捗を見える化】
1日10分をカレンダーにチェック、最初に2マスを“ボーナス”で埋め勢いづけ。週末は家族で発表会&称賛タイムにして楽しむ。
【ポイント③ルールで習慣化】
「帰宅→鍵は皿、郵便は箱、机は1分で白紙化」など実行意図を3つに絞る。守れたらご褒美ドリンク。迷わない仕組みで楽しく続く。
片付け始める前に準備をしておきたいモノ

※画像はイメージです
ゴミを捨てるのに必要なモノは片付けを始める前に準備しておきましょう。スムーズに片付けができれば、やる気も維持しやすくなります。
ゴミ袋
まずは、各地域で決められたゴミ袋を用意してください。分別する場合にはそれぞれの種類ごとのゴミ袋が必要です。ゴミ袋の指定がない地域の方は、レジ袋やスーパー・100円ショップで購入できる袋でも問題ありません。複数箇所を片付けたり不必要なモノが多かったりする場合は、大きめのゴミ袋を用意すると一度にまとめられるためおすすめです。不必要なモノは片付けの途中でこまめに仕分けていきましょう。
紐とはさみ
紐とハサミも片付けを始める前に用意しておくとよいでしょう。不必要な本や雑誌、段ボール箱などが出てきたとき、紐でまとめておくと持ち出しやすくなります。足をぶつけたり転んだりして、積んでおいたモノを散らかす心配もありません。
片付けの際の3ステップ
・【ステップ1】モノを全て取り出す
・【ステップ2】モノを分別する
・【ステップ3】モノを使いやすい場所に収納する
片付けを効率よく進めるには、まず、家にあるモノの全体量の把握が重要です。そのうえで、これから紹介する3つのステップに沿って片付けを進めましょう。迷わずスムーズに作業が進み、部屋を短時間で整えることができます。
【ステップ1】モノを全て取り出す

※画像はイメージです
・引き出し収納の中を片付けるときは一か所ずつ片付ける
・作業しやすい場所から片付ける
ステップ1では、片付ける場所のモノを全て取り出すことから始めます。引き出し収納などは一か所ずつ、手が届き作業しやすい場所から進めると、無理なく効率的に片付けが進むでしょう。
引き出し収納の中を片付けるときは一か所ずつ片付ける
「キッチンの引き出し」や「衣類収納」など、引き出しタイプの収納を片付けるときは、一か所ずつ中のモノを全部取り出すのがポイントです。一度に全ての引き出しの中身を出してしまうと、モノの量や種類を把握しにくく、片付けに時間がかかってしまいます。さらに、大量に出すと視覚的に圧迫感を感じることもあるでしょう。作業負担を軽減するためにも、一か所ずつ全部取り出すのがおすすめです。
作業しやすい場所から片付ける
比較的作業しやすい場所から始めると、その後の片付けもスムーズに進めやすいです。たとえば下駄箱は手が届きやすく、中のモノをすべて取り出して掃除もできるためよいでしょう。家の顔である玄関がスッキリすると気分も明るくなり、次の片付けへのモチベーションにもつながります。目に見える変化を感じながら進めることで、やる気を維持しながら片付けられるでしょう。
【監修者コメント】
・ステップ1は“全出し”で量を把握しつつ、一箇所ずつ進めて圧迫感を回避。玄関・下駄箱など成果が見えやすい場所から着手し、全出し→必要/不必要の仕分けを15分単位で回すのがおすすめです。
【ステップ2】モノを分別する

※画像はイメージです
・「1年に1回使う」モノは残す
・「もったいない」でモノを残さない
・「今」の暮らしを基準に考える
ステップ2では、全部取り出した モノを「使う」「使わない」に分けていきます。判断に迷ったときは、「今の暮らしに本当に必要か」を基準に考えることが大切です。
「1年に1回使う」モノは残す
「使うモノ」はすぐに判断できますが、「使わないモノ」を仕分けるのは意外と難しいです。そんなときは、「1年に1回でも使うかどうか」を基準に考えるとよいでしょう。季節の行事や特定のイベントなど、年に数回しか使わないモノでも、必要なタイミングがあるなら残してOK。逆に、1年以上使っていないモノは手放すことを検討しましょう。
「もったいない」でモノを残さない
「まだ使えるから」といった「もったいない」気持ちは、片付けを妨げる原因です。実際には、使わないことこそが本当にもったいないといえます。使わずに眠らせているモノは、思い切って手放すのも大切です。ネットオークションに出品するのも方法の一つでしょう。手放すことに迷うときは、「なぜ使っていないのか」を考えると判断しやすくなります。
【「捨てる」以外の不必要なモノの処分方法】
・フリマアプリで販売する
・リサイクルショップに持って行く
・各自治体の引き取りサービスを利用する
・リサイクルボックスを利用する
「今」の暮らしを基準に考える
モノの仕分けに迷うときは、「今の暮らしに本当に必要か」も大切な基準の一つです。「使いにくい」と感じたモノは、今後も使う機会が少ない可能性が高いでしょう。「いつか使うかも」と思っていても、長年使っていないモノはその「いつか」が訪れない場合がほとんどです。今の自分の生活をより快適にするために、使うモノ・大切なモノを厳選して収納していきましょう。
【監修者コメント】
・使っているか、使っていないかで仕分け。年1回使っているモノは残し、1年以上使っていないモノは手放す。「もったいない」は理由を言語化すると、明確に判断できます。迷うモノは保留箱で再判定。売る・自治体ルールで安全に処分し、「今」の暮らしに必要かで判断しましょう。
【ステップ3】モノを使いやすい場所に収納する

※画像はイメージです
・使用頻度ごとに分けて収納する
・カテゴリー別に収納する
・使用する人ごとに分けて収納する
・動線を考えて収納する
ステップ3では、必要なモノを使いやすい場所に収納していきます。モノの住所をしっかりと決めることで、部屋が散らかるのを防ぎます。大切なのは「探しやすい、取り出しやすい、片付けやすい」ことです。使用頻度やカテゴリー、動線を意識して収納場所を決めていきましょう。
使用頻度ごとに分けて収納する
「毎日のように使うモノ」や「1年に1回使うモノ」など、使用頻度で分けて収納することで、よく使うモノがわかりやすく、出し入れしやすくなります。モノを探すストレスがなくなり、時間の節約にもつながるでしょう。とくに使用頻度の高いモノは、出し入れしやすいように、腰くらいの高さの位置に収納するのがおすすめです。
カテゴリー別に収納する
モノは、カテゴリー別の収納が基本です。たとえば、クローゼットの中なら「トップス」「ボトムス」の2つのカテゴリーに分けられます。さらにトップスの中でも、コート、ジャケット、シャツ、Tシャツなど複数のカテゴリーに。ボトムスもパンツやスカート、短パンなどに分けられます。それぞれをカテゴリー別に収納することで、持っているモノの種類や数を把握できるため、適切な量を持つことにもつながるでしょう。
使用する人ごとに分けて収納する
ご家族の場合は、収納する場所を使用する人別で分けると、それぞれモノの管理がしやすくなるためおすすめです。たとえば、下駄箱の、下段は小さなお子さんたちの靴用、中段はお母さま方の靴用、上段はお父様方の靴用と分けて収納しておきます。場所を分けると、それぞれのモノが一目瞭然になり、各々が出し入れしやすくなるでしょう。
動線を考えて収納する
家の中の動線を俯瞰して見て、収納場所を決めるのもポイントです。たとえば、家に帰ってきてからの行動で、どこに何が置いてあると便利かを意識してみるといいでしょう。その場所に必要な収納があるとモノが片付けやすくなります。
【監修者コメント】
・使用頻度・カテゴリー・人別で「定位置」を決め、動線上に配置。毎日使う物は腰高に、ラベリングで可視化。重い物は上段を避けます。見せると隠す、適正量も意識して、迷いゼロの収納にしましょう。
片付けられない人必見!キレイなお部屋を維持する方法

・収納場所を見直す
・収納場所を決めてからモノを購入する
・一つ購入したら一つ捨てる
・モノを出しっぱなしにしない
お部屋を片付けたら、キレイな状態を維持するのも忘れてはいけません。ここでは、片付け後に意識したいことをご紹介します。
収納場所を見直す
収納で大事なことは「戻しやすい」ことです。いくら綺麗に収納できていたとしても、使った後に戻しにくい収納はNG。戻しにくいと、そのうちモノの住所があやふやになってしまい、結局部屋が散らかってしまいます。【ステップ3】で解説した「カテゴリー・使う人・動線」を基本として、「戻しやすい」かどうかも意識しましょう。
収納場所を決めてからモノを購入する
「買った商品をどこに収納できるか」が思い浮かばないまま買い物をしてしまうと、モノがあふれる原因になります。先に収納場所を確保してから、購入するのがポイントです。反対に、収納場所がない場合は、商品を買うタイミングではない可能性もあります。本当に必要なモノかどうかを考えるのも大切です。
一つ購入したら一つ捨てる
モノを増やさないためには、「一つ購入したら一つ捨てる」というルールを作るのも効果的です。新しいモノを迎えるときは、同じカテゴリーの不必要なモノを手放すことで、持ちすぎを防ぎ、スッキリとした空間を維持できます。
モノを出しっぱなしにしない
モノを出しっぱなしにしてしまう状態が続くときは、収納方法や持ち物の量を見直すタイミングです。収納用品の前や床の上にモノを置くようになったら、すでに管理できる量を超えている可能性があります。この場合は、【ステップ2】で説明した必要なモノ・不必要なモノの見直しから始め、持ち物を整理してから収納を整えていきましょう。
【監修者コメント】
・戻しやすさ重視で“モノの住所”を明確化。1つ買ったら1つ手放す。出しっぱなしが続く時は量を見直しましょう。使用頻度に沿って配置し、動線も意識。写真で進捗を可視化すると習慣化しやすいのでおすすめです。
汚部屋脱出!今日から始める片付け習慣とスッキリ収納のコツ

片付けが苦手でも、ステップとコツを意識すれば無理なく整理できます。まずはモノを全て出し、必要・不必要に分け、「今の暮らし」に合った場所へ収納することが大切です。さらに、時間を決めたりご褒美を用意したりするなどの工夫で、片付けを習慣化できます。少しずつでも実践することで、部屋も心もスッキリと整えていきましょう。
快適で使いやすい収納を実現したいなら、まずDAIKENの収納製品をチェックしてみてください。暮らしや用途に合わせた豊富なラインナップで、片付けやすい空間作りをしっかりとサポート。施工例も掲載されているので、イメージがつかみやすいのも特徴です。詳しい情報やお問い合わせは公式ホームページから。あなたにぴったりの収納プランが見つかります。