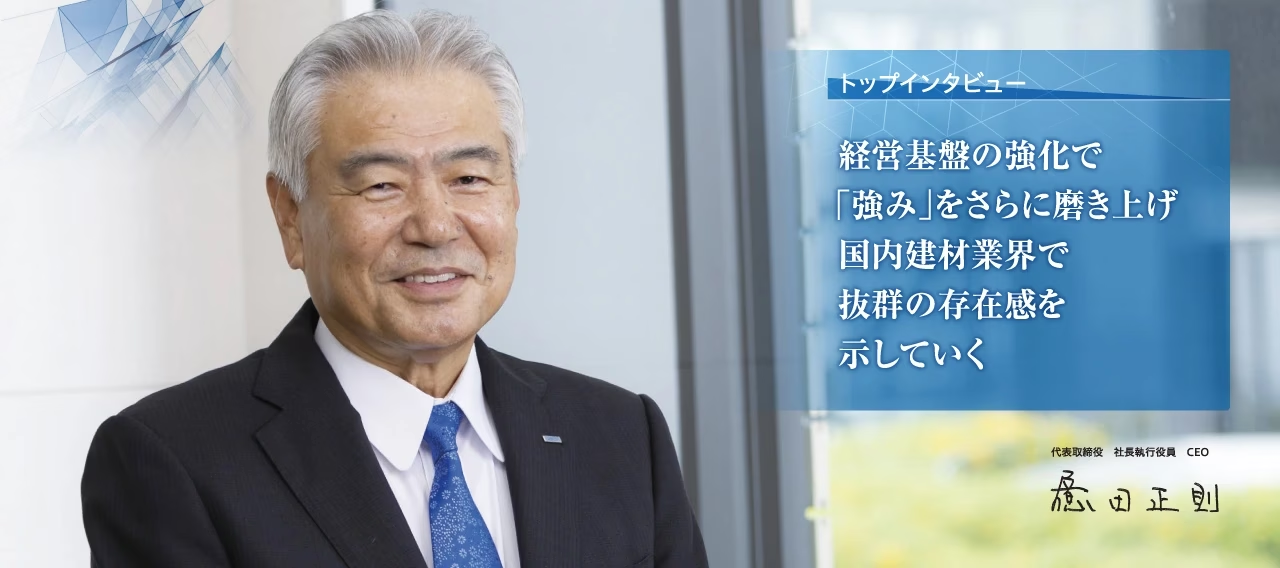トップインタビュー
- 2025年3月期の業績と、今期の展望をお聞かせください。
- 2025年9月に創立80年となりますが、節目の年を迎えるにあたっての所感をお聞かせください。
- ご自身にとっては代表取締役社長就任から12年目となりますが、この間に起こった出来事で印象的なことを教えてください。
-
大きな変化に見舞われた10年とのことでしたが、本年は長期ビジョン「GP25」の最終年度となります。
2015年の策定時から注力されたことや、達成度についてお聞かせください。 -
「GP25」に続き、2026年度からは次期長期ビジョンである「TryAngle 2035」が始動します。
本ビジョンの策定経緯や「GP25」との違いについてお聞かせください。 - 新たな長期ビジョンの策定に加え、本年9月には新社名「DAIKEN株式会社」となることが発表されていますが、社名の変更にはどのような狙いがあるのでしょうか。
-
社名変更、次期長期ビジョンの策定を筆頭に、本年度は80周年に関するさまざまな取り組みが進んでいます。
取り組みの内容や期待される効果についてお聞かせください。 - 最後にステークホルダーの皆様へのメッセージをお願いします。
2025年3月期の業績と、今期の展望をお聞かせください。
2024年度は中期経営計画「GP25 3rd Stage」(2022-2025年度)の3年目として、経営基盤の強靭化と成長に向けた取り組みを進めてまいりました。
国内においては、新設住宅着工戸数が引き続き減少傾向にあるものの、価格改定の浸透やコストアップ抑制、変動費削減策を着実に実行したことで、収益面において改善が進みました。また、エンジニアリング事業はオフィスビルなどの内装工事やリフォーム・リノベーション市場の需要を取り込み、業績を牽引しました。これは、当社が次期長期ビジョン「TryAngle 2035」の拡大領域として掲げる「快適ソリューション事業」の展開にとって前向きな材料であり、大きな期待を寄せています。
一方で海外事業については、急激な為替変動や市況低迷により、中核事業であるMDF事業の収益が悪化し、課題を残す結果となりました。しかしながら、昨年グループ化したDAIKEN North America Ltd(. DNAL社)において、新木質ボード『DIO woodcore』のプロトタイプが完成し、2026年4月の生産開始を目指して量産・市場投入の準備に入るなど、海外での事業拡大に向けたさまざまな施策が着実に進んでいます。これらの取り組みの結果、2025年3月期の売上高は前期比2.7%増の2,163億円、営業利益・経常利益についても前期比で増益となりました。
2025年度は中期経営計画「GP25 3rd Stage」の最終年度であり、この10年間の総仕上げの1年となります。縮小する国内新設住宅市場、各地の紛争や米国の通商政策などにより不透明感の増す世界経済など、マイナスの要素は数多くありますが、その中でも地に足を付けた事業展開を行い、次の10年を見据えた着実な成長を目指していきます。
2025年9月に創立80年となりますが、節目の年を迎えるにあたっての所感をお聞かせください。
当社は戦後間もない1945年9月に大建木材工業株式会社として創立して以来、常に社会課題や世の中のニーズに応えるために技術革新を重ね、お客様の期待を超える製品、サービスを提供してきました。その理念や想いが多くの皆様に届いたことで、80年という長きにわたり事業を継続できたと考えております。改めまして、これまで当社を支えてくださったお客様、お取引先様をはじめステークホルダーの皆様に深く御礼を申し上げます。
私自身、入社以来半世紀にわたりDAIKENとともに歩み続け、気づけば社内では最も社歴が長くなりました。思い起こせば経済に合わせて会社が大きく成長した時期、事業の存続が危ぶまれるような出来事など、山あり谷ありで決して平たんな道のりではなかったように思います。経営側に立ってからも、数多くの新たな取り組みに携わるとともに、いくつかの事業撤退も目の当たりにしてきました。市場環境の変化に伴う取捨選択には厳しい決断が伴いますが、どのような時もお客様やお取引先様と真摯に向き合ってきたことで、信頼される企業に成長してこられたと感じております。今日まで続くステークホルダーの皆様とのつながりは、当社にとっても私にとっても、何物にも代えがたい財産となりました。
ご自身にとっては代表取締役社長就任から12年目となりますが、この間に起こった出来事で印象的なことを教えてください。
最も印象に残っているのは、やはりCOVID-19の世界的な流行です。当社においても2020年4月1日、新年度を迎えるその日に社内で感染者が発生し、混乱の中でリモートワークへの切り替えを指示しました。図らずもこの大きな外的要因により、当社を含めた多くの企業で従業員の働き方や勤務地に対する議論が進み、DXの重要性を再認識させられたと感じています。さらに現在進行形ではありますが、地政学的な懸念の増大による紛争の勃発や、他国の政治体制の変化による事業リスクの高まりにより、海外でビジネスを行う難しさを痛感することとなりました。いずれも現長期ビジョン「GP25」の策定時には想定しきれなかった変化であり、企業の長期的な舵取りがいかに困難かを物語っていると思います。また、私が社長に就任した翌年の2015年には、国連サミットにおいて、よりよい社会を目指すための国際目標としてSDGs(持続可能な開発目標)が採択され、世界的にサステナビリティへの取り組みが一段と加速された年でもありました。これは創立以来、「エコ製品」を強みにしていた当社にとっては大きな追い風でした。「GP25」においても「限りある資源の有効活用を通じてサステナブルな社会の実現に貢献する」ことを掲げており、企業に求められる環境に関する社会的要請は、当社が長年取り組んできた事業と深くリンクしています。
大きな変化に見舞われた10年とのことでしたが、本年は長期ビジョン「GP25」の最終年度となります。
2015年の策定時から注力されたことや、達成度についてお聞かせください。
長期ビジョン「GP25」は「Grow(成長)」と「Glow(輝き)」をテーマに、「住宅用建材メーカー」から「建築資材の総合企業」への変革を目指してスタートしました。特に注力したのは海外市場の拡大と、公共・商業建築分野への進出です。
私の経歴の中ではビルダー・工務店などへの建材営業経験が長いのですが、当時から新設住宅着工数によって業績が左右される様を体感しており、早い時期から国内の新築依存に危機感を抱いていました。そのため、漸減傾向が明らかな国内新築住宅市場から軸足を移し、多角的な事業展開が必須であると考え、海外と公共・商業建築分野という新たな市場への挑戦を強く推進してきました。従業員のマインドや旧来の組織体制を転換させることは非常に困難でしたが、一人ひとりが変わらなければならないというメッセージを根気強く発信し続けたことで、ポートフォリオ変革に向けて大きく舵を切ることができたと感じています。2019年に北米の2社(CIPA・PWT)をグループ化し、事業展開のグローバル化を進めるとともに、事業の川下である工事分野についてもM&Aによる強化を実施しました。現在では幅広い工事能力を有した関係会社がDAIKENグループを支えています。「GP25」期間中最大の転換点は、やはり2023年12月の伊藤忠商事(株)子会社化および上場廃止です。非常に大きな決断ではありましたが、「GP25」で目指す姿を達成し、2025年以降もさらなる成長を推し進めるためには必要不可欠な判断でした。上場廃止という話題に不安を感じられる方も多かったと思いますが、トップ自らが変わるという姿勢を社内外に示し、そのシナジーを最大限活用することを訴求したことで、ステークホルダーの皆様にもご理解をいただけたと考えています。
「GP25」に続き、2026年度からは次期長期ビジョンである「TryAngle 2035」が始動します。
本ビジョンの策定経緯や「GP25」との違いについてお聞かせください。
先述のとおり、「GP25」の期間中、新市場拡大によるポートフォリオの見直しや既存製品の新規用途開発などを進めてきましたが、環境変化がさらに加速する次の10年を正確に見通すことは極めて困難です。そのように不安定な環境下でも、当社が掲げる企業理念の達成に向けた羅針盤となるのが、長期ビジョンであると考えています。
次期長期ビジョン「TryAngle 2035」の策定に関して、「GP25」の時と最も大きく異なる点は、旧来のトップダウンではなく若手・中堅社員を中心としたボトムアップ方式で草案を策定したという点です。若い世代の自由で柔軟な発想から「10年後のありたい姿」を思い描き、その達成に向けた事業展開を検討しました。
また、「TryAngle 2035」では新たな試みとして、左記の通り視覚的にビジョン内容を訴求するためのロゴを作成しました。

トライアングルという言葉は一般的に三角形のことを指しますが、3点がバランスよく成り立っていることから、近江商人の「三方良し」の精神にも通じるところがあります。さらに、「挑戦」を意味するトライ、「角度」から転じて「右肩上がりの視点」の意味を込めたアングルなど、次期ビジョンのタイトルにはさまざまな想いを込めました。ロゴの三角形を構成する色は、当社の主力事業である「素材」「建材」「エンジニアリング」のイメージカラーであり、次期長期ビジョンのタイトルとロゴには、2035年に当社が目指す姿が凝縮されています。
新たな長期ビジョンの策定に加え、本年9月には新社名「DAIKEN株式会社」となることが発表されていますが、社名の変更にはどのような狙いがあるのでしょうか。
現在の「大建工業株式会社」という社名は、1967年から約60年間使用してきた商号です。歴史ある本社名を変更するに至ったのには大きく2つの理由があります。1つ目は、当社の提供価値を「モノ」から「コト」に変革する姿勢を示すためです。社会が求める価値は徐々に変化し、消費の形態も「所有」から「経験」へと移り変わっています。
「工業」という言葉には材料を加工して製品を作るという意味があることから、いわゆる「製造業」のイメージが強く印象付けられるのではないでしょうか。今回、社名から「工業」を外すことで、当社が推進する「コト」提案の姿勢を表現しました。しかしながら、「コト」提案の根底には当社の「モノづくり」への想いが根ざしていることには変わりません。これからも、確かな品質と新しい技術で皆様のくらしを豊かにする製品・空間の提供に努めてまいります。
2つ目の理由は、DAIKENをアルファベット表記にすることで、「GP25」で推進してきたグローバル展開をさらに加速させるためです。既に海外では「DAIKEN Corporation」の表記を使用しており、社名変更を契機に国内外の垣根を越えて「DAIKEN」ブランドの浸透を図っていきたいと考えています。
これまで当社がステークホルダーの皆様と積み重ねてきた歴史とブランドイメージを大切にしたいという想いから、「DAIKEN」という名称を残すこととなりました。新社名となった後も、引き続きご愛顧いただきますようお願いいたします。
社名変更、次期長期ビジョンの策定を筆頭に、本年度は80周年に関するさまざまな取り組みが進んでいます。
取り組みの内容や期待される効果についてお聞かせください。
80周年事業のメインイベントとして企画したのが、DAIKENのミライに向けた取り組みを皆様にご紹介する展示会「EXPAND THE FUTURE ~ DAIKEN TryAngleフェア~」です。同フェアは、2025年6月4日・5日に東京、7月9日・10日に大阪で開催し、おかげさまで盛況のうちに閉幕しました。両会場合わせて9,000名近いお客様が来場され、DAIKENが考える10年先、20年先のミライの“空間”、ミライの“素材”、そしてミライの“ここちよさ”を、見て、触れて体感いただき、理解を深めていただく機会となりました。DAIKENが目指す「ミライ」に向けたビジョンに共感いただいたステークホルダーの皆様とともに、今後も『ずっと ここちいい』関係性を構築していきたい所存です。さらに、7月1日からは80周年を記念し、新製品などを広く認知いただくことを目的とした「DAIKEN販売コンテスト80」を開催しており、全国のお取引先様とともに製品拡販・市場シェアの拡大を推進しております。他にもさまざまな施策を予定しておりますが、これら80周年の取り組みを形式的な記念行事で終わらせることなく、さらなる成長戦略の実現と経営基盤の強化につなげてまいります。
最後にステークホルダーの皆様へのメッセージをお願いします。
世界的な先行きの不透明感は増すばかりで、当社の事業環境も決して楽観視できるものではありません。しかし、そのような状況だからこそDAIKENグループ一丸となって、常に新しいことに挑戦しつづける姿勢を大切にしたいと考えています。次期長期ビジョンで掲げている事業の軸は「サステナビリティ」と「ウェルビーイング」の2つですが、これはまさに創業時から綿々と受け継がれてきた「環境への貢献」と「快適な生活空間の提供」に他なりません。当社のDNAを大切にしつつも、時代に合わせたアップデートを続け、これからも長くステークホルダーの皆様から愛される「DAIKENさん」を目指してまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。